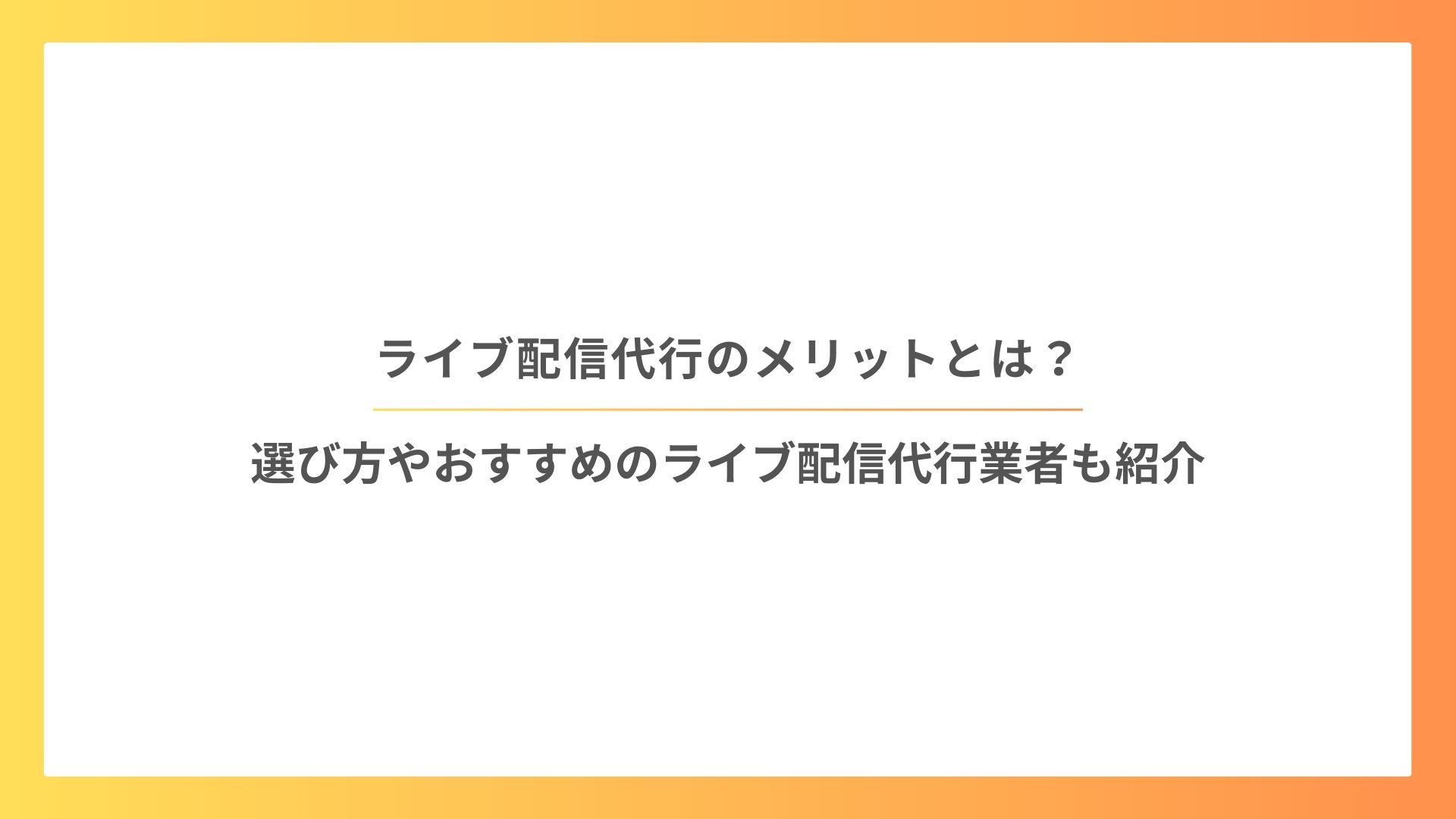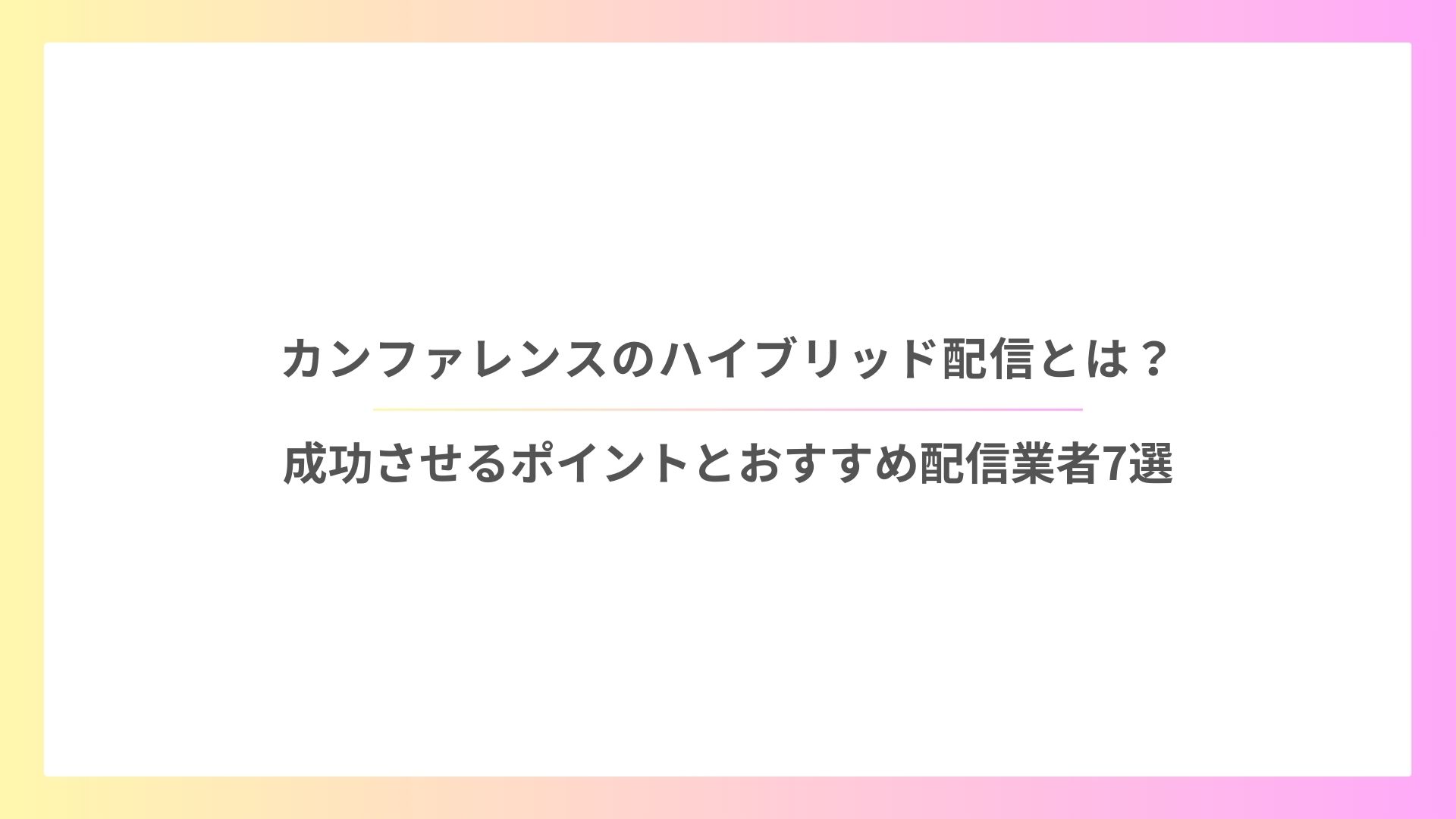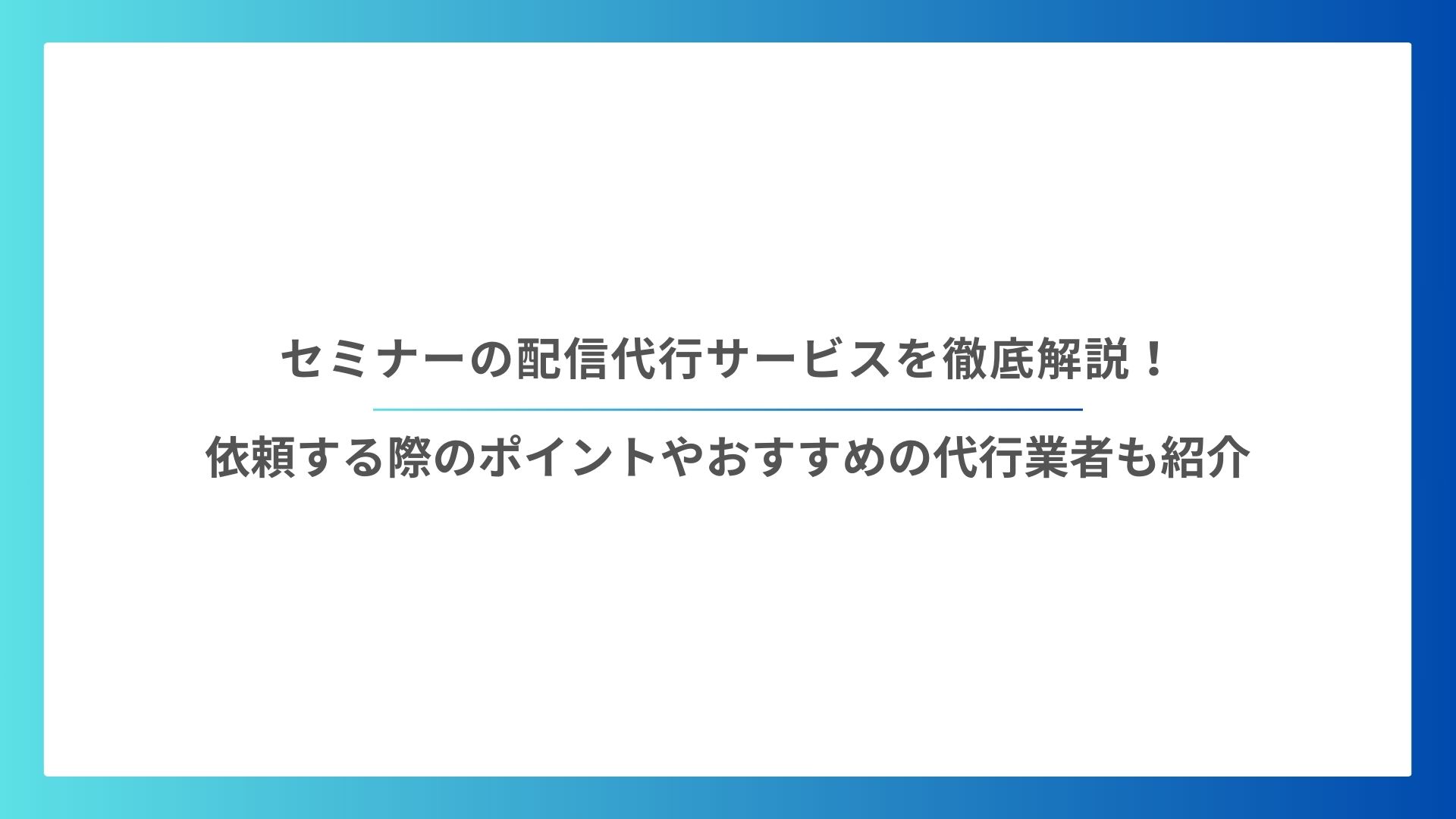記者会見をインターネット中継するには?代行サービスの重要性と活用方法を徹底解説
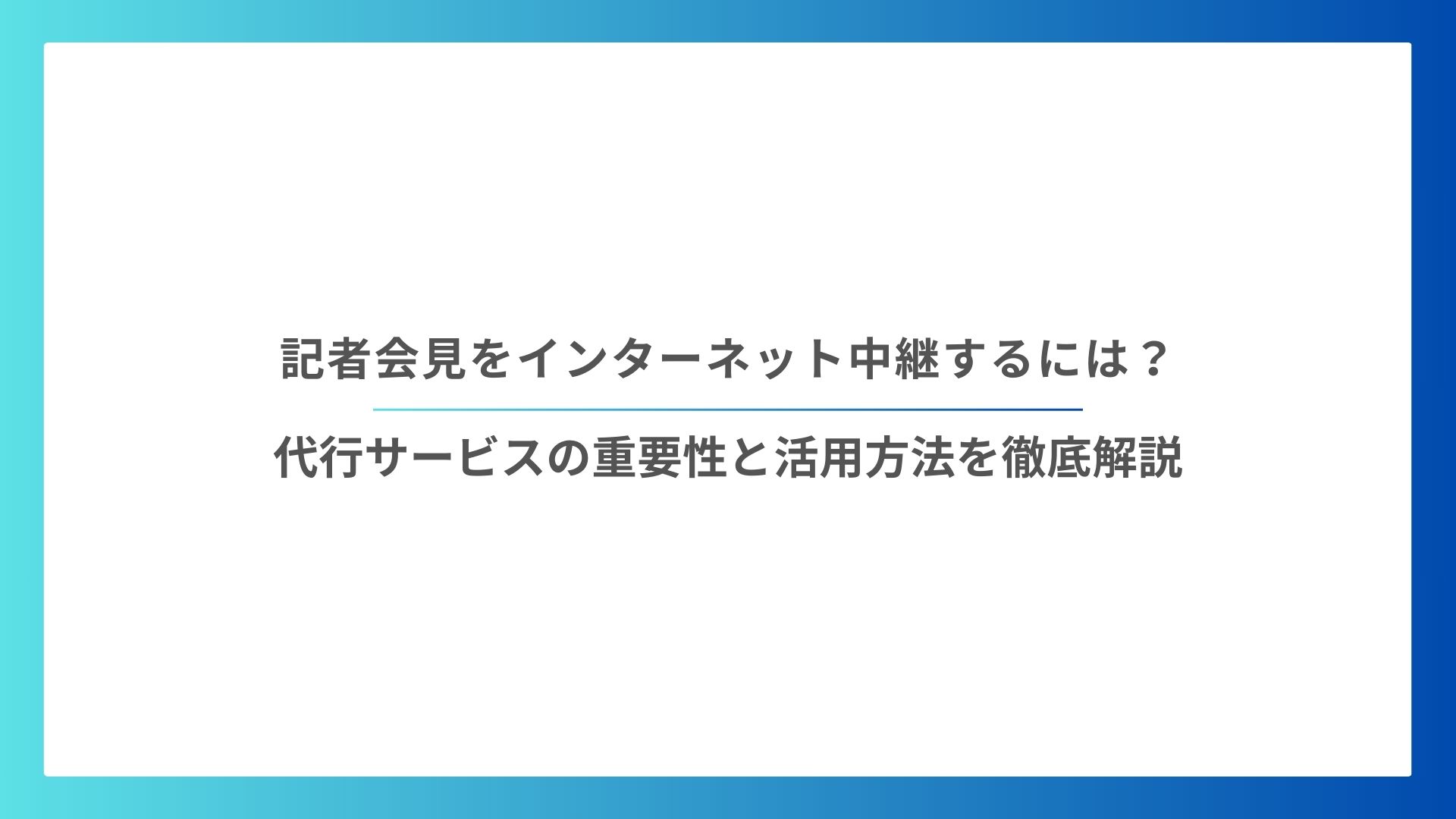
「オンラインで記者会見を開きたいが、どう進めればいいかわからない」と悩む広報担当者・経営者の方は多いのではないでしょうか。
特にコロナ禍以降はリモートで記者会見を実施するケースが増え、インターネット中継による情報発信はすっかり定着しました。
オンラインでの開催には時間や場所の制約が軽減されるなど多くのメリットがありますが、配信トラブルなく成功させるには事前の準備と技術的知識が不可欠です。
本記事では、初めてオンライン記者会見に取り組む方にもわかりやすく、「インターネット中継の基礎知識」から「必要な準備」、「費用・よくある質問」、そして「配信代行サービスの活用」まで解説します。
後半では、記者会見配信に強いおすすめのオンライン配信代行会社6社も紹介します。自社での対応と外注の違いも把握できるので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
記者会見のインターネット中継とは
インターネット中継とは、企業や団体が行う記者会見などをインターネットを通じてリアルタイム配信することです。
通常の記者会見では記者が会場に集まり対面で行いますが、オンライン記者会見では画面越しに会見を実施します。
専用のカメラで会見の様子を撮影し、事前申込者に限定配信する形式が一般的です。
2019年までは「記者会見=対面」が当たり前でしたが、コロナ禍でオンライン記者会見の重要性が一気に高まりました。
オンライン記者会見のメリット
オンライン(リモート)で記者会見を行う最大のメリットは、場所や時間の制約を大幅に軽減できる点です。
記者はオフィスや自宅から参加できるため、移動時間を気にせず多くのメディアに取材してもらえる可能性が高まります。
また配信映像を録画アーカイブしておけば、当日都合が合わなかった記者にも後日視聴してもらえます。
さらに双方向のオンライン会議ツールを使えば、その場で質疑応答に対応することも可能です。
ハイブリッド型記者会見という選択肢
最近では、現地会場とオンライン配信を組み合わせたハイブリッド型の記者会見も増えています。
ハイブリッド開催にすれば記者それぞれの希望に合わせた参加方法を提供でき、取材機会を最大化できます。
ただし、現場と配信の同時運営には高度な対応力が求められます。会場の音響や照明を整えながら、高品質な配信映像・音声を同時に提供する必要があるため、自社スタッフのみで対応するのは難易度が高くなります。
こうした場合も専門の配信代行業者に依頼することで、現地スタッフと配信スタッフが連携しスムーズなハイブリッド記者会見を実現できます。
オンライン記者会見に必要な準備と進め方
オンラインで記者会見を成功させるには、従来の対面会見とは異なる周到な準備が欠かせません。
ここでは、記者会見をインターネット中継する際の基本的な準備プロセスを見ていきましょう。
事前準備のポイント
まず記者会見の趣旨や発表内容を明確にし、日時を決定します。発表相手(誰に何を伝えるか)を意識して、ターゲットとなる記者やメディアのリストを作成しましょう。
次に完全オンラインで行うかハイブリッドで行うかを決め、使用する配信プラットフォームを選定します。一般的にはZoomウェビナーやYouTubeライブ、Microsoft Teamsなどがよく使われています。
安定した映像配信にはカメラ・マイク・照明・エンコーダーなどの専門機材が必要です。カメラは発表者全体を映すものに加え、商品や資料をクローズアップできるものがあると効果的です。
会場(自社オフィスの会議室等を使う場合も含む)には有線の高速インターネット回線を用意し、予備回線も確保しておきます。配信中に主回線が不調になっても切り替えられるよう、テザリングやポケットWi-Fi等のバックアップ通信を準備しておくと安心です。
本番前には、必ずリハーサル配信を行いましょう。発表者の映り方、音声の聞こえ方、スライド資料の共有手順、質疑応答の流れまで一通り確認します。配信ツール上で記者役のスタッフに入ってもらい、質問の受け付けや音声切替えの練習をしておくと本番でも落ち着いて対処できます。
当日の進行と配信オペレーション
記者会見当日は、進行担当(司会役)と技術担当(配信オペレーター)の役割分担を明確にしておきます。
司会担当者は開始時にオンライン参加者への案内(音声のミュートや質問方法の説明など)を行い、発表の合間や終了後に質疑応答の進行を担当します。
一方、技術担当者はカメラ映像のスイッチング(登壇者スピーカーと資料映像の切替え)、音量調整、配信ソフトの操作全般を受け持ちます。
質疑応答では、記者からの質問を円滑にさばく工夫が必要です。Zoom等ではQ&A機能やチャット機能を使って質問を受け付け、司会者が順に読み上げて回答する形式が一般的です。
万一配信中にトラブルが起こった場合に備え、事前に決めた代替策に従って対処します。例えば「映像が乱れたら音声のみで続行」「配信ツールに不具合が起これば別の予備ツールに切替える」などです。
トラブル発生時には速やかに参加者へ状況をアナウンスし、復旧見込みなどを伝えることで混乱を防ぎます。プロの配信代行会社に依頼している場合は、現場スタッフが迅速に対応してくれるので安心です。
終了後のフォローアップ
記者会見終了後も、オンラインならではのフォローが大切です。
まず参加登録した記者全員にお礼メールを送り、資料やアーカイブ動画のURLを共有します。特に映像資料は記者が記事を書く際に役立つため、見逃し配信を一定期間提供すると良いでしょう。
またオンライン会見に参加できなかったメディアにもプレスリリースやアーカイブ情報を送り、カバーしきれなかった記者への情報提供を行います。
参加者数や視聴完了率などオンライン配信ならではのデータも取得できる場合があります。可能であればアンケートを実施し、記者からフィードバックや追加質問を募るのも有効です。
こうしたデータや意見を分析し、次回の記者会見や広報活動の改善に活かしましょう。オンラインであっても記者との関係構築は継続が大切です。
終了後のフォローまで含めて丁寧に対応することで、リモート記者会見でも対面に劣らない成果を得ることができます。
記者会見配信におすすめのオンライン配信代行会社6選
ここからは記者会見のインターネット中継を安心して任せられる、おすすめの配信代行会社6社を紹介します。
それぞれ実績豊富なプロフェッショナル集団で、企業の大切な発表を高品質に配信するサポートを提供しています。
株式会社Airz

【特徴】
- 専任コンサルタントが企画立案から本番まで伴走
- Zoom・YouTube・Teamsなど主要配信ツールに対応
- 配信実績は官公庁・上場企業含め1,000件以上
株式会社Airz(エアーズ)は、記者会見やIRイベント、株主総会、製品発表会など、企業の重要な広報・PR活動を支えるオンライン中継専門の配信代行会社です。
提供する「Airz Webinar」は、機材手配から撮影、配信オペレーション、進行管理、視聴者対応、アーカイブ納品、開催後のレポート分析までをワンストップで支援するトータルサービスで、特にZoomを活用したウェビナー配信の安定性と操作性の高さに定評があります。
記者会見では、登壇者の映像演出や音響・照明調整、記者向け事前案内や質疑応答サポートにも対応しており、単なる配信業者にとどまらない「広報視点での進行設計」が強みです。
さらに、ハイブリッド型(現地+オンライン)記者会見の実施にも注力しており、3000人規模の大規模イベントまで対応可能な技術・体制を整えています。
オンライン配信に不慣れな企業でも安心して利用できるよう、専任のコンサルタントが事前相談から伴走し、要望に応じた最適なプランを提案。
料金は10万円台からの明朗プランを用意しており、初めてのオンライン会見にも導入しやすいサービス設計となっています。
実績は官公庁、上場企業、医療機関、IT企業など幅広い業種にわたり、数多くの成功事例を積み重ねています。
住所:〒106-0044 東京都港区東麻布3-8-2 麻布マルカビル4F
設立:2019年8月
URL:https://webinar.airz.co.jp/hybrid/
PR TODAY

【特徴】
- ・リリース・資料・動画などを提供し配信URLも告知する報道向け特設サイト
- ・東銀座駅すぐの高速ネット環境完備の会議室をライブ配信会場に提供
- ・メディアに精通した専門スタッフが質疑応答など最適な進行をプランニング
PR会社が運営する「PR TODAY」は、広報担当者の負担軽減を重視し、オンライン会見の準備から配信までワンストップでサポートします。
報道関係者向け特設サイトでプレスリリースや資料、関連動画を事前提供し、ライブ配信のURLや概要も告知可能です。
東京・東銀座の高速インターネット環境を備えた会議室を配信会場として利用でき、時間がない場合でも迅速に対応できます。
また、メディアの特性や会見内容に応じて質疑応答の進行方法を提案するなど、デジタルに精通した専門スタッフが最適な進行運営を実現します。
住所:〒104-0045 東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア10階
設立:1964年11月
URL:https://www.pr-today.net/online_conference/
MOPS

【特徴】
- ・演出企画立案から資料作成・メディア告知・進行運営まで一括対応
- ・ライブ配信+録画提供で視聴時間を選ばず情報発信が可能
- ・コロナ禍の安全開催・多数参加・低コストなど多様な要望に対応
PR会社「株式会社MOPS」が提供するオンライン記者会見サポートサービス。会見の企画立案から報道資料作成、メディア告知、当日の進行運用までトータルに請け負い、必要に応じ部分的な支援も可能です。
オンラインで新製品発表やキャンペーン等の記者会見をライブ配信し、視聴できなかった人向けに録画映像提供も行うため、より多くの関係者に情報を届けられます。
ZoomやYouTubeなど配信プラットフォームにも対応し、コロナ禍でも安全に予定通り情報発信したい、多くの媒体にリーチしたいといった幅広いニーズに応えます。
初めてオンライン会見を行う企業にもわかりやすい進行プランや概算見積もりを提示し、事前準備から当日の運営、開催後の露出レポート作成まで丁寧にサポートします。
住所:〒105-0012 東京都港区芝大門2-6-4 芝大門笹野ビル5F
設立:2013年1月
カーツメディアワークス

【特徴】
- ・全国11拠点のライブ配信スタジオを完備し、最短1週間で配信が可能
- ・15年以上の映像配信実績を持つプロチームが高品質かつ安全な配信を提供
- ・記者誘致から当日運営、事後フォローまでオンライン会見を一括サポート
映像配信に強みを持つ株式会社カーツメディアワークスのオンライン記者会見支援サービスです。
全国11か所の提携ライブ配信スタジオを備えており、地域を問わず高品質な配信が可能です。
準備期間が短い場合でも最短1週間でライブ配信の実施に対応できるフットワークの軽さも特徴です。
15年以上にわたり培ったライブ配信技術と実績を持つプロフェッショナルチームが撮影から配信まで担当し、安定した高画質配信を実現します。
また記者の誘致・出席管理から企画運営、アフターフォロー(掲載レポート作成)まで一括して任せられるため、煩雑な広報業務をまとめてサポートします。
多数のオンライン/ハイブリッド記者会見を成功させてきた豊富な実績があり、参加メディア数の拡大や記事掲載数の最大化といった成果も上げています。
住所:〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-11-2 フロンティア代々木4階
設立:記載なし
ONLINE KAIKEN

【特徴】
- ・独自開発のQ&Aシステムでオンライン上でも円滑な質疑応答を実現
- ・会場選定・記者誘致・配信・映像編集まで包括的に代行するワンストップサービス
- ・基本プラン20万円~から、目的に応じた柔軟なプラン提案が可能
デジタル戦略PRに強みを持つアウル株式会社が提供するオンライン記者会見サービス「ONLINE KAIKEN」です。
会場手配、記者への案内状配信、ライブ配信運営、映像編集まで一括して任せられる体制で、配信が途切れないか・質疑応答はどうするかといった広報担当者の不安をプロのノウハウで解決します。
特に独自開発のオンラインQ&Aシステムにより、記者からの質問受付や応答をスムーズに行えるのが大きな強みで、リアルの会見に遜色ない双方向コミュニケーションを実現します。
視聴ページへのログイン認証によるセキュアな参加者管理機能も備え、記者限定の安全な環境で配信を視聴可能です。
住所:〒107-0052 東京都港区赤坂2-8-5 若林ビル2F
設立:2006年1月
共同ピーアール株式会社

【特徴】
- ・PR会社の視点と経験を活かしたオンライン記者会見の企画・運営支援
- ・メディア要望や広報担当者の悩みに精通したスタッフが誘致から掲載報告まで一括対応
- ・記者会見以外の新製品発表会や決算説明など多様なオンラインイベントにも対応
国内大手PR会社である共同ピーアール株式会社が提供するオンラインイベント運営支援サービスです。
PR会社ならではの視点と豊富な経験を活かし、オンライン記者会見の企画から運営まで総合的にサポートします。
会見時によくあるメディア側の要望や広報担当者の悩みを熟知したスタッフが対応し、記者誘致・案内から当日の進行対応、終了後の掲載状況報告まで広報PR活動全般をワンストップで支援します。
オンライン会見の進め方や予算に関する相談にも応じており、経験豊富なPRパートナーとして安全で効果的なオンラインイベント開催を後押しします。
住所:〒104-0045 東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア10階
設立:1964年11月
URL:https://www.kyodo-pr.co.jp/services/digital-pr/press-conference/
まとめ:プロの力を借りてオンライン記者会見を成功させよう
インターネット中継による記者会見は、今や企業広報において欠かせない選択肢となりました。
オンライン開催のメリットを最大限に活かしつつ、デメリットを補うには綿密な準備と適切なパートナー選びが重要です。
本記事で解説したポイントを踏まえて計画を立てれば、リモート環境でも記者にしっかり情報が伝わる記者会見を実現できるでしょう。
特に配信の専門知識やリソースが不足している場合は、無理に自社だけで抱え込まず配信代行サービスの活用を検討してみてください。
費用や準備について悩んだら、株式会社Airzへの無料相談がおすすめです。プロのサポートによって、企業メッセージを最良の形で届けることができます。
記者会見のオンライン配信を強力にバックアップしてくれる心強いパートナーとともに、貴社の重要な発表を確実にメディアへ届けてください。