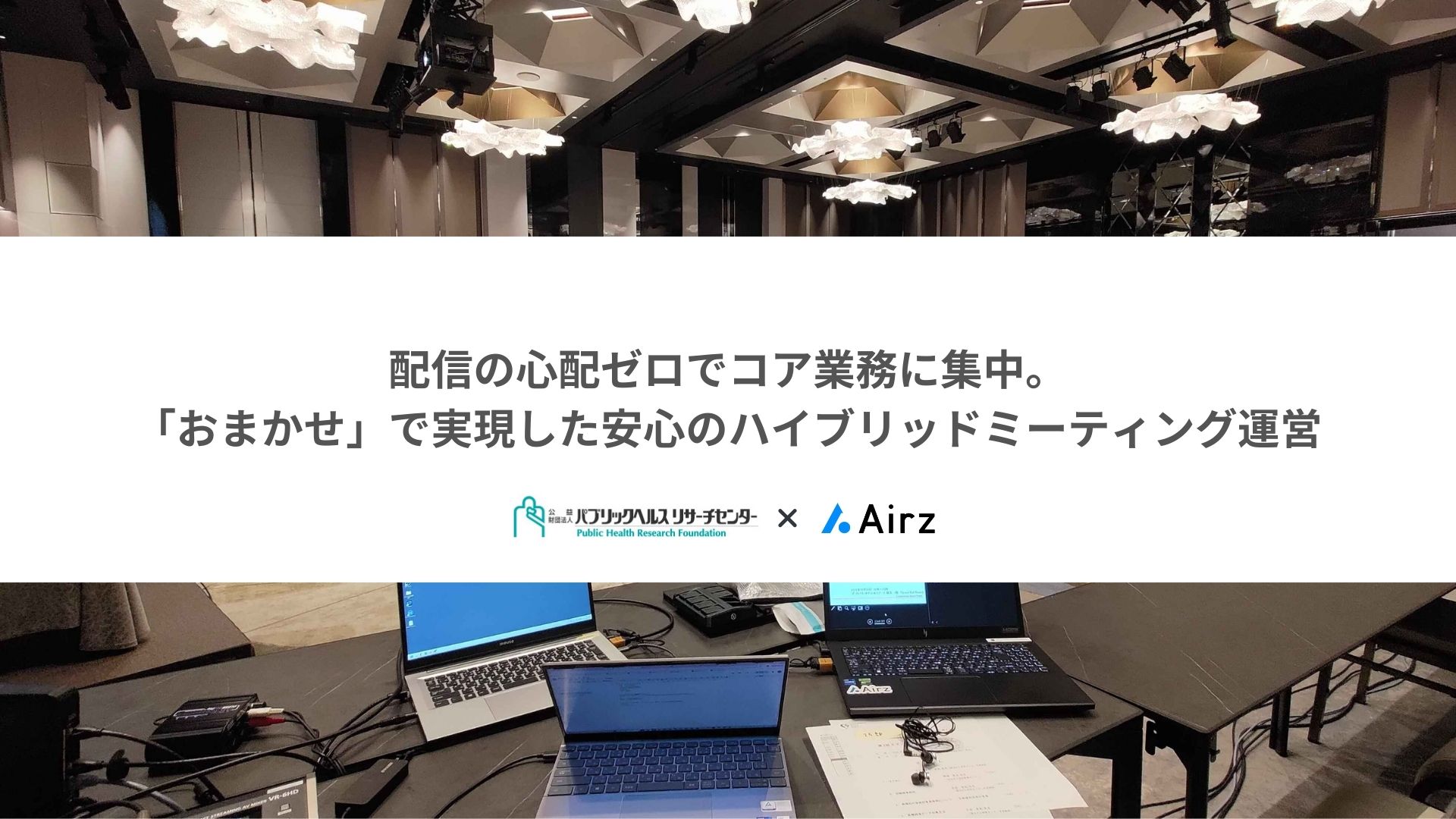企業ライブ配信のメリット・デメリットとは?導入前に知るべきポイント!
 更新日
更新日

企業がリアルタイムで情報を発信し、顧客との距離を縮める手段として注目されている「企業ライブ配信」。視聴者と双方向コミュニケーションができるだけでなく、商品やサービスの魅力を生放送で伝え、ブランド認知度の向上にも効果を発揮します。
本記事では、企業ライブ配信の基本からメリット・デメリット、配信の種類やプラットフォームの選び方、トラブル対策まで詳しく解説します。デジタルマーケティングを強化したい企業担当者必見です。
企業ライブ配信とは、企業が自社の商品やサービス、ブランド価値を視聴者にリアルタイムで発信するデジタルマーケティング手法のことです。従来のテレビCMや印刷広告とは異なり、インターネット上で生放送形式により情報を伝達します。
近年のデジタル化の進展と新型コロナウイルスの影響により、多くの企業が導入を加速させている注目の施策です。
企業ライブ配信の最大の特徴は、録画された動画ではなく生放送でコンテンツを配信することです。
この手法により、企業は最新の情報や緊急性の高いメッセージを即座に視聴者へ届けられます。新商品の発表会や重要な企業発表、株主総会などの場面で特に威力を発揮するでしょう。
リアルタイム配信では、事前に編集や修正を加えることができないため、より自然で親近感のある企業イメージを伝えることが可能です。
従来の一方向的な広告媒体と大きく異なるのが、視聴者との双方向コミュニケーション機能です。コメント機能やチャット機能を活用することで、視聴者からの質問や意見をリアルタイムで受け取り、その場で回答することができます。
この仕組みにより、企業と顧客の距離が大幅に縮まるでしょう。視聴者からの生の声を直接聞くことで、商品開発のヒントや改善点を発見できる貴重な機会にもなります。
また、コメントで寄せられる疑問や不安に即座に対応することで、購買意欲の向上や顧客満足度の改善につながります。企業側も視聴者の反応を見ながら配信内容を調整できるため、より効果的なプレゼンテーションが実現可能です。
ライブ配信では、商品やサービスの魅力を実演を交えながら詳細に紹介できます。
静止画や文章では伝えきれない使用感や機能性を、実際に使用している様子を映すことで視聴者に分かりやすく伝達可能です。
特に化粧品や調理器具、ファッションアイテムなどは、実際の使用シーンを見せることで購買意欲を大きく刺激します。配信者が商品を手に取り、質感や重量感、操作性などを詳しく説明することで、視聴者は店舗で実際に商品を手に取っているような体験を得られます。
企業ライブ配信は、ブランド認知度の向上において非常に効果的な手段です。定期的な配信により、視聴者の記憶に企業名やブランド名を定着させることができます。
また、配信内容がSNSでシェアされることで、視聴していない潜在顧客にもリーチを拡大できるでしょう。
配信を通じて企業の価値観や理念を伝えることで、単なる商品販売を超えたブランドストーリーの構築が可能になります。経営陣や開発担当者が直接出演することで、企業の人格化を図り、親しみやすいブランドイメージを醸成できます。

企業がライブ配信を導入することで、従来のマーケティング手法では実現できない多くの利点を得られます。リアルタイムでの双方向コミュニケーションにより、顧客との関係性を深めながら、効率的な情報発信が可能になるでしょう。
以下では、企業ライブ配信の具体的なメリットについて詳しく解説します。
ライブ配信では、商品の実際の使用感や魅力を生の映像で伝えることができます。静止画やテキストでは表現しきれない商品の質感、動作、サイズ感などを、配信者が実際に手に取って紹介することで、視聴者により具体的なイメージを提供できるでしょう。
特に、アパレル商品では着用感やコーディネート例を実演できますし、家電製品では操作方法や機能を詳細にデモンストレーションできます。
また、商品の製造過程や開発秘話なども交えることで、商品に対するストーリー性を演出し、感情的な訴求も可能になります。
企業ライブ配信は、従来のマーケティング手法と比較して圧倒的にコストパフォーマンスに優れています。テレビCMや新聞広告などの従来メディアでは多額の費用が必要ですが、ライブ配信なら基本的な機材とインターネット環境があれば始められるでしょう。
また、会場費や印刷費、配布物の準備費用なども不要で、人件費も最小限に抑えられます。
さらに、地理的制約がないため、全国や海外の視聴者にも同時にアプローチでき、リーチできる人数に対するコストは格段に低くなります。
ライブ配信を通じて企業の人間的な側面を見せることで、ブランドに対する親しみやすさを大幅に向上させられます。経営者や従業員が直接登場し、自然な表情や話し方で視聴者とコミュニケーションを取ることで、企業に対する堅いイメージを和らげ、より身近な存在として認識してもらえるでしょう。
このような親近感の醸成は、顧客ロイヤルティの向上に直結し、長期的な顧客関係の構築につながります。
ライブ配信の双方向性により、視聴者からの質問や疑問にリアルタイムで回答できることは、大きな競争優位性となります。従来の問い合わせ対応では、メールや電話での回答に時間がかかりましたが、ライブ配信なら即座に解決できるため、顧客満足度が大幅に向上するでしょう。
また、一つの質問への回答を他の視聴者も同時に聞くことで、効率的な情報提供が可能になります。

企業がライブ配信を導入する際には、多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。これらの課題を事前に把握し、適切な対策を講じることで、ライブ配信を成功に導くことが可能です。
ここでは、企業ライブ配信における主なデメリットについて詳しく解説していきます。
ライブ配信では、録画とは異なり撮り直しや編集ができないため、技術的なトラブルが発生した際の影響が深刻になりがちです。インターネット回線の不安定さによる映像の乱れや音声の途切れ、配信機材の故障、ソフトウェアの不具合など、様々な技術的問題が発生する可能性があります。
特に重要な発表会や大規模なイベントでこうしたトラブルが起きると、視聴者に悪印象を与えるだけでなく、企業の信頼性にも影響を及ぼしかねません。
高品質なライブ配信を実現するためには、相当な準備期間と費用が必要になります。配信機材の調達や設定、会場のネットワーク環境の整備、照明や音響設備の準備など、技術面での準備だけでも多大な労力を要します。
さらに、台本作成や出演者のリハーサル、視聴者への告知活動なども含めると、配信当日までに数週間から数か月の準備期間が必要となるケースも少なくありません。
コスト面では、専用の配信機材や高性能なカメラ、マイク、照明器具などの購入費用に加え、安定したインターネット回線の確保や配信プラットフォームの利用料金も発生します。
効果的なライブ配信を行うには、出演者に特殊なスキルが求められます。カメラを意識した話し方や表情の作り方、視聴者とのリアルタイムなコミュニケーション能力、予期しない状況への対応力など、通常のプレゼンテーションとは異なる技術が必要です。
また、配信中にコメントや質問に対応しながら進行する場合は、マルチタスク能力も重要になります。
配信に慣れていない社員が出演すると、緊張により本来の魅力が伝わらなかったり、機械的な印象を与えてしまう可能性があります。

企業がライブ配信を活用する方法は多岐にわたり、それぞれ異なる目的と効果を持っています。以下では、企業が実際に取り組んでいる主要なライブ配信の種類について詳しく解説します。
商品紹介・デモンストレーション配信は、企業ライブ配信の中でも最も効果的な手法の一つです。実際に商品を使用している様子をリアルタイムで見せることで、静止画や文章だけでは伝えきれない商品の魅力を視聴者に直接アピールできます。
特にアパレルブランドでは、スタッフが実際に洋服を着用して着心地や素材感を伝えたり、家電メーカーでは新製品の機能を実演したりすることで、購入を検討している顧客の不安を解消できます。
セミナー・ウェビナー形式のライブ配信は、企業の専門知識や業界情報を視聴者に提供する教育的な配信です。
従来の対面セミナーと比較して、会場費や交通費などのコストを大幅に削減できる上、地理的な制約なく多くの参加者を集められるメリットがあります。参加者は自宅やオフィスから気軽に参加でき、チャット機能を通じて質問することも可能です。
企業側にとっては、見込み顧客との接点を作り、専門性をアピールすることで信頼関係を構築できる重要な機会となります。
新商品発表イベントのライブ配信は、企業にとって重要なマーケティングイベントをより多くの人に届ける手段として活用されています。
従来のプレスリリースや記者会見だけでは限られた人数にしか情報を伝えられませんでしたが、ライブ配信により世界中の顧客や関係者に同時に情報を発信できます。
Apple社のような大手テクノロジー企業が行う製品発表会のように、高い注目度を集めるイベントとして演出することも可能です。リアルタイムでの視聴者の反応を確認しながら進行できるため、市場の反応を即座に把握することもできます。
イベント・展示会の中継配信は、物理的な会場に来場できない人々に対してもイベントの価値を提供する重要な手段です。
特にコロナ禍以降、ハイブリッド形式でのイベント開催が一般的になり、オンライン参加者への配慮が不可欠となっています。展示会では、各ブースの紹介や商品デモンストレーションをライブ配信することで、遠方の顧客や海外の関係者にもリーチできます。
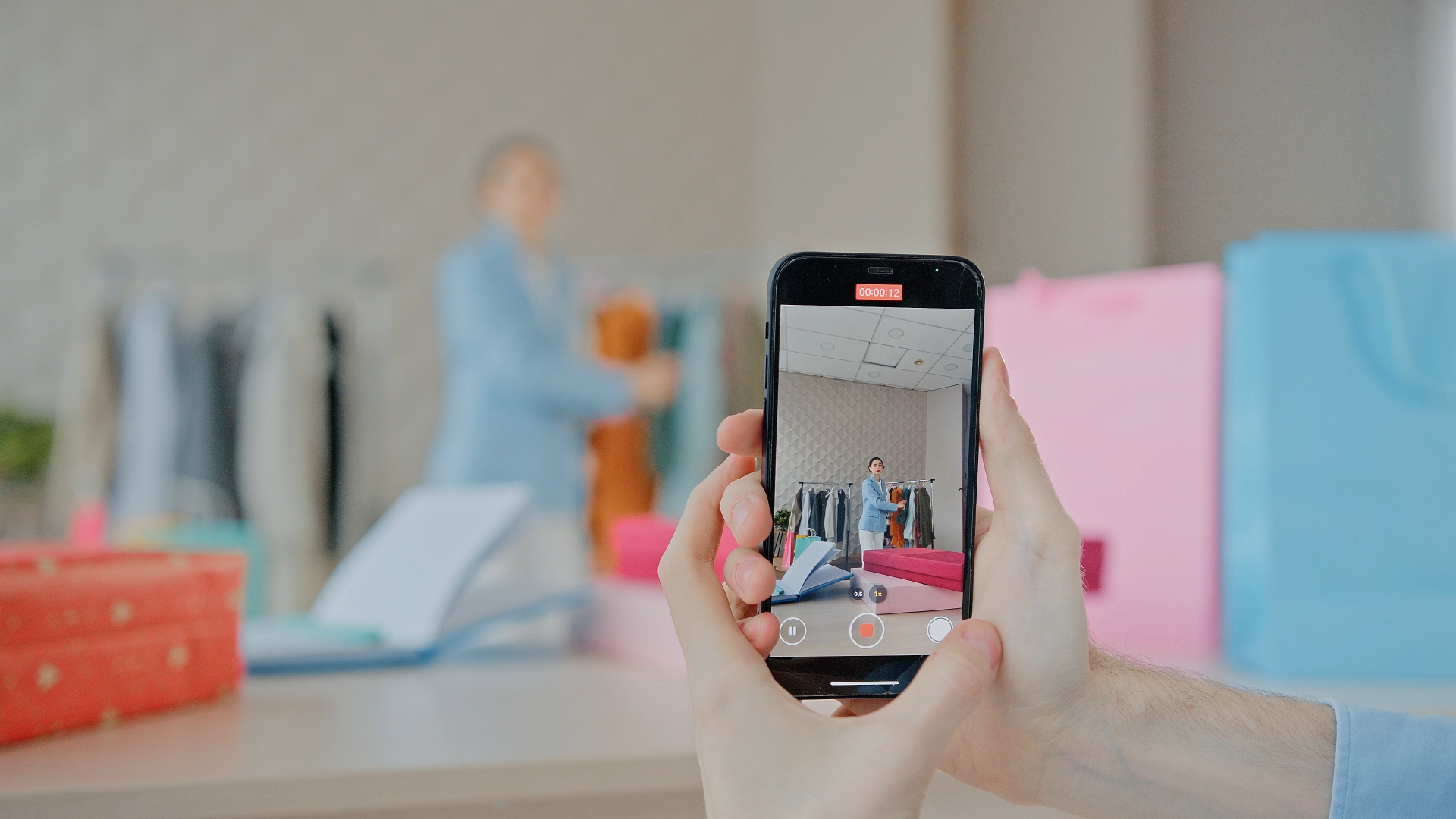
企業がライブ配信を成功させるためには、適切なプラットフォーム選択が重要になります。現在は多様な配信サービスが存在し、それぞれ異なる特徴や機能を持っているため、自社の目的や予算に合わせた選択が必要です。
これらの要素を詳しく比較検討することで、企業にとって最適なプラットフォームを見つけられるでしょう。
プラットフォーム選択において、配信機能の充実度は最も重要な判断基準の一つです。基本的な配信機能としては、高画質・高音質での配信が可能か、同時視聴可能人数の上限、配信の安定性などを確認しましょう。企業向けには、複数カメラの切り替え機能、画面共有機能、テロップやロゴの挿入機能なども重要になります。
また、配信形式の選択肢も重要な要素です。一方向配信だけでなく、双方向のコミュニケーションが可能かどうか、ウェビナー形式に対応しているかなどを確認する必要があります。
ライブ配信プラットフォームの料金体系は、無料プランから高額な企業向けプランまで幅広く存在します。
無料プランでは機能制限や広告表示、視聴者数制限などがある場合が多いため、企業利用では有料プランの検討が必要です。月額定額制、従量課金制、買い切り型など様々な料金形態があるため、自社の利用頻度や規模に応じて選択しましょう。
ライブ配信後の録画・アーカイブ機能は、企業利用において非常に重要な要素です。
配信を見逃した従業員や顧客が後から視聴できるだけでなく、研修資料や営業ツールとして二次活用も可能になります。自動録画機能の有無、録画データの保存期間、ダウンロード可能性、編集機能の充実度などを確認しましょう。
また、アーカイブの管理機能も重要なポイントです。タイトル設定、タグ付け、検索機能、フォルダ分け機能などがあると、大量のアーカイブを効率的に管理できます。
視聴者とのリアルタイムコミュニケーションを実現するチャット・コメント機能は、ライブ配信の魅力を高める重要な要素です。
基本的なテキストチャット機能に加えて、絵文字やスタンプ機能、質問機能、アンケート機能などがあると、より活発な双方向コミュニケーションが期待できます。
また、モデレーション機能により不適切なコメントを制御できることも重要です。企業向けの配信では、Q&A機能や挙手機能、ブレイクアウトルーム機能なども有用です。これらの機能により、セミナーや研修での質疑応答がスムーズに行えます。
企業がライブ配信を安心して活用するためには、充実したサポート体制が重要です。技術的なトラブルや操作方法に関する疑問に迅速に対応してもらえるかどうかは、配信の成功を左右する要因となります。
サポート方法としては、電話、メール、チャット、FAQ、マニュアルなどがあり、複数の方法でサポートを受けられることが理想的です。

企業のライブ配信では、技術的なトラブルや予期せぬ問題が発生する可能性があります。視聴者に良い印象を与え、配信を成功させるためには、事前の準備と適切な対処法を知っておくことが重要です。
ここでは、ライブ配信でよく発生するトラブルとその対処法について詳しく解説していきます。これらのポイントを押さえることで、安定した配信を実現できるでしょう。
ライブ配信の成功には、事前の機材テストが欠かせません。カメラ、マイク、配信ソフト、インターネット回線など、すべての機材が正常に動作するかを本番前に必ず確認しましょう。
特に音声は視聴者の満足度に大きく影響するため、マイクの音質やボリューム調整は念入りにチェックが必要です。配信当日と同じ環境でリハーサルを行い、実際の配信時間と同じ長さでテストすることをおすすめします。
これにより、長時間配信での機材の安定性も確認できます。
インターネット回線の不具合は、ライブ配信において最も致命的なトラブルの一つです。
メイン回線が途切れた場合に備えて、必ずバックアップ回線を用意しておきましょう。
モバイルWi-Fiルーターや4G/5G回線を活用したテザリング機能など、複数の接続手段を確保することが重要です。バックアップ回線は、メイン回線と異なるプロバイダーや通信方式を選ぶことで、同時に障害が発生するリスクを軽減できます。
スムーズなライブ配信を実現するには、配信スタッフ間での役割分担を明確にしておくことが不可欠です。
配信オペレーター、音響担当、進行管理者、視聴者対応担当など、それぞれの責任範囲を事前に決めておきましょう。トラブル発生時には、誰がどのような対応を取るかを明確にしておくことで、迅速な問題解決が可能になります。

ここまでご紹介したように、企業のライブ配信には多くのメリットがある一方で、トラブル対応や機材準備など専門的なノウハウも欠かせません。だからこそ、実績豊富なプロに任せることで安心して配信に臨むことができます。
Airzでは、セミナーやシンポジウム、学会、研修・式典、株主総会などあらゆるシーンに対応し、10名から3,000名規模まで柔軟にサポートします。ZoomやWebex、YouTube、Teamsといった配信ツールを含め幅広く対応し、回線や機材を最適化して高画質・高音質の配信を実現します。進行管理や会場選定、告知用サイト制作やメール配信、当日のオペレーションやアーカイブ納品まで一気通貫で支援できるのも特長です。
ベーシックプランは10万円から、オンライン完結型は5万円から利用可能で、打ち合わせは即日対応・お見積りも最短1営業日で提示できます。
初めての方も「どんな配信ができるか」から気軽にご相談いただけ、無料資料のダウンロードも可能です。企業ライブ配信を成功させたい方は、ぜひご相談ください。
本記事では、企業ライブ配信の基本からメリット・デメリット、配信の種類やプラットフォームの選び方、トラブル対策まで詳しく解説します。デジタルマーケティングを強化したい企業担当者必見です。
Table of Contents
企業ライブ配信とは
企業ライブ配信とは、企業が自社の商品やサービス、ブランド価値を視聴者にリアルタイムで発信するデジタルマーケティング手法のことです。従来のテレビCMや印刷広告とは異なり、インターネット上で生放送形式により情報を伝達します。
近年のデジタル化の進展と新型コロナウイルスの影響により、多くの企業が導入を加速させている注目の施策です。
リアルタイムで情報を発信する手法
企業ライブ配信の最大の特徴は、録画された動画ではなく生放送でコンテンツを配信することです。
この手法により、企業は最新の情報や緊急性の高いメッセージを即座に視聴者へ届けられます。新商品の発表会や重要な企業発表、株主総会などの場面で特に威力を発揮するでしょう。
リアルタイム配信では、事前に編集や修正を加えることができないため、より自然で親近感のある企業イメージを伝えることが可能です。
視聴者と双方向コミュニケーションが可能
従来の一方向的な広告媒体と大きく異なるのが、視聴者との双方向コミュニケーション機能です。コメント機能やチャット機能を活用することで、視聴者からの質問や意見をリアルタイムで受け取り、その場で回答することができます。
この仕組みにより、企業と顧客の距離が大幅に縮まるでしょう。視聴者からの生の声を直接聞くことで、商品開発のヒントや改善点を発見できる貴重な機会にもなります。
また、コメントで寄せられる疑問や不安に即座に対応することで、購買意欲の向上や顧客満足度の改善につながります。企業側も視聴者の反応を見ながら配信内容を調整できるため、より効果的なプレゼンテーションが実現可能です。
商品やサービスを生放送で紹介
ライブ配信では、商品やサービスの魅力を実演を交えながら詳細に紹介できます。
静止画や文章では伝えきれない使用感や機能性を、実際に使用している様子を映すことで視聴者に分かりやすく伝達可能です。
特に化粧品や調理器具、ファッションアイテムなどは、実際の使用シーンを見せることで購買意欲を大きく刺激します。配信者が商品を手に取り、質感や重量感、操作性などを詳しく説明することで、視聴者は店舗で実際に商品を手に取っているような体験を得られます。
ブランド認知度向上に効果的
企業ライブ配信は、ブランド認知度の向上において非常に効果的な手段です。定期的な配信により、視聴者の記憶に企業名やブランド名を定着させることができます。
また、配信内容がSNSでシェアされることで、視聴していない潜在顧客にもリーチを拡大できるでしょう。
配信を通じて企業の価値観や理念を伝えることで、単なる商品販売を超えたブランドストーリーの構築が可能になります。経営陣や開発担当者が直接出演することで、企業の人格化を図り、親しみやすいブランドイメージを醸成できます。
企業ライブ配信のメリット

企業がライブ配信を導入することで、従来のマーケティング手法では実現できない多くの利点を得られます。リアルタイムでの双方向コミュニケーションにより、顧客との関係性を深めながら、効率的な情報発信が可能になるでしょう。
以下では、企業ライブ配信の具体的なメリットについて詳しく解説します。
商品の魅力を直接伝えられる
ライブ配信では、商品の実際の使用感や魅力を生の映像で伝えることができます。静止画やテキストでは表現しきれない商品の質感、動作、サイズ感などを、配信者が実際に手に取って紹介することで、視聴者により具体的なイメージを提供できるでしょう。
特に、アパレル商品では着用感やコーディネート例を実演できますし、家電製品では操作方法や機能を詳細にデモンストレーションできます。
また、商品の製造過程や開発秘話なども交えることで、商品に対するストーリー性を演出し、感情的な訴求も可能になります。
低コストで多くの人にリーチ可能
企業ライブ配信は、従来のマーケティング手法と比較して圧倒的にコストパフォーマンスに優れています。テレビCMや新聞広告などの従来メディアでは多額の費用が必要ですが、ライブ配信なら基本的な機材とインターネット環境があれば始められるでしょう。
また、会場費や印刷費、配布物の準備費用なども不要で、人件費も最小限に抑えられます。
さらに、地理的制約がないため、全国や海外の視聴者にも同時にアプローチでき、リーチできる人数に対するコストは格段に低くなります。
ブランドの親しみやすさが向上
ライブ配信を通じて企業の人間的な側面を見せることで、ブランドに対する親しみやすさを大幅に向上させられます。経営者や従業員が直接登場し、自然な表情や話し方で視聴者とコミュニケーションを取ることで、企業に対する堅いイメージを和らげ、より身近な存在として認識してもらえるでしょう。
このような親近感の醸成は、顧客ロイヤルティの向上に直結し、長期的な顧客関係の構築につながります。
視聴者の質問に即座に回答できる
ライブ配信の双方向性により、視聴者からの質問や疑問にリアルタイムで回答できることは、大きな競争優位性となります。従来の問い合わせ対応では、メールや電話での回答に時間がかかりましたが、ライブ配信なら即座に解決できるため、顧客満足度が大幅に向上するでしょう。
また、一つの質問への回答を他の視聴者も同時に聞くことで、効率的な情報提供が可能になります。
企業ライブ配信のデメリット

企業がライブ配信を導入する際には、多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。これらの課題を事前に把握し、適切な対策を講じることで、ライブ配信を成功に導くことが可能です。
ここでは、企業ライブ配信における主なデメリットについて詳しく解説していきます。
技術的なトラブルが発生しやすい
ライブ配信では、録画とは異なり撮り直しや編集ができないため、技術的なトラブルが発生した際の影響が深刻になりがちです。インターネット回線の不安定さによる映像の乱れや音声の途切れ、配信機材の故障、ソフトウェアの不具合など、様々な技術的問題が発生する可能性があります。
特に重要な発表会や大規模なイベントでこうしたトラブルが起きると、視聴者に悪印象を与えるだけでなく、企業の信頼性にも影響を及ぼしかねません。
準備に時間とコストがかかる
高品質なライブ配信を実現するためには、相当な準備期間と費用が必要になります。配信機材の調達や設定、会場のネットワーク環境の整備、照明や音響設備の準備など、技術面での準備だけでも多大な労力を要します。
さらに、台本作成や出演者のリハーサル、視聴者への告知活動なども含めると、配信当日までに数週間から数か月の準備期間が必要となるケースも少なくありません。
コスト面では、専用の配信機材や高性能なカメラ、マイク、照明器具などの購入費用に加え、安定したインターネット回線の確保や配信プラットフォームの利用料金も発生します。
配信スキルが必要になる
効果的なライブ配信を行うには、出演者に特殊なスキルが求められます。カメラを意識した話し方や表情の作り方、視聴者とのリアルタイムなコミュニケーション能力、予期しない状況への対応力など、通常のプレゼンテーションとは異なる技術が必要です。
また、配信中にコメントや質問に対応しながら進行する場合は、マルチタスク能力も重要になります。
配信に慣れていない社員が出演すると、緊張により本来の魅力が伝わらなかったり、機械的な印象を与えてしまう可能性があります。
企業ライブ配信の種類

企業がライブ配信を活用する方法は多岐にわたり、それぞれ異なる目的と効果を持っています。以下では、企業が実際に取り組んでいる主要なライブ配信の種類について詳しく解説します。
商品紹介・デモンストレーション配信
商品紹介・デモンストレーション配信は、企業ライブ配信の中でも最も効果的な手法の一つです。実際に商品を使用している様子をリアルタイムで見せることで、静止画や文章だけでは伝えきれない商品の魅力を視聴者に直接アピールできます。
特にアパレルブランドでは、スタッフが実際に洋服を着用して着心地や素材感を伝えたり、家電メーカーでは新製品の機能を実演したりすることで、購入を検討している顧客の不安を解消できます。
セミナー・ウェビナー形式
セミナー・ウェビナー形式のライブ配信は、企業の専門知識や業界情報を視聴者に提供する教育的な配信です。
従来の対面セミナーと比較して、会場費や交通費などのコストを大幅に削減できる上、地理的な制約なく多くの参加者を集められるメリットがあります。参加者は自宅やオフィスから気軽に参加でき、チャット機能を通じて質問することも可能です。
企業側にとっては、見込み顧客との接点を作り、専門性をアピールすることで信頼関係を構築できる重要な機会となります。
新商品発表イベント配信
新商品発表イベントのライブ配信は、企業にとって重要なマーケティングイベントをより多くの人に届ける手段として活用されています。
従来のプレスリリースや記者会見だけでは限られた人数にしか情報を伝えられませんでしたが、ライブ配信により世界中の顧客や関係者に同時に情報を発信できます。
Apple社のような大手テクノロジー企業が行う製品発表会のように、高い注目度を集めるイベントとして演出することも可能です。リアルタイムでの視聴者の反応を確認しながら進行できるため、市場の反応を即座に把握することもできます。
イベント・展示会の中継配信
イベント・展示会の中継配信は、物理的な会場に来場できない人々に対してもイベントの価値を提供する重要な手段です。
特にコロナ禍以降、ハイブリッド形式でのイベント開催が一般的になり、オンライン参加者への配慮が不可欠となっています。展示会では、各ブースの紹介や商品デモンストレーションをライブ配信することで、遠方の顧客や海外の関係者にもリーチできます。
ライブ配信プラットフォームの選び方
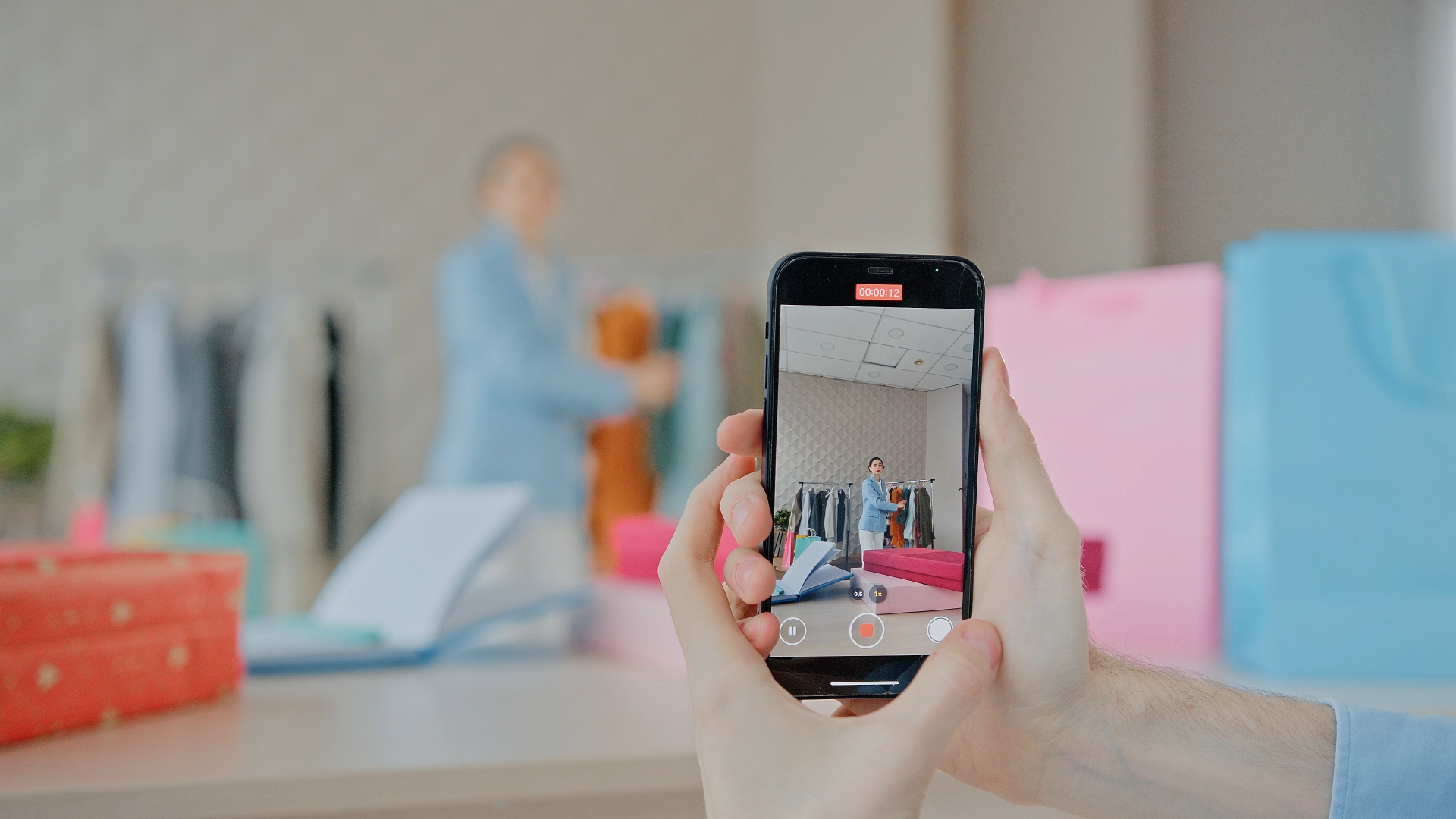
企業がライブ配信を成功させるためには、適切なプラットフォーム選択が重要になります。現在は多様な配信サービスが存在し、それぞれ異なる特徴や機能を持っているため、自社の目的や予算に合わせた選択が必要です。
これらの要素を詳しく比較検討することで、企業にとって最適なプラットフォームを見つけられるでしょう。
配信機能の充実度を比較
プラットフォーム選択において、配信機能の充実度は最も重要な判断基準の一つです。基本的な配信機能としては、高画質・高音質での配信が可能か、同時視聴可能人数の上限、配信の安定性などを確認しましょう。企業向けには、複数カメラの切り替え機能、画面共有機能、テロップやロゴの挿入機能なども重要になります。
また、配信形式の選択肢も重要な要素です。一方向配信だけでなく、双方向のコミュニケーションが可能かどうか、ウェビナー形式に対応しているかなどを確認する必要があります。
料金体系とコストパフォーマンス
ライブ配信プラットフォームの料金体系は、無料プランから高額な企業向けプランまで幅広く存在します。
無料プランでは機能制限や広告表示、視聴者数制限などがある場合が多いため、企業利用では有料プランの検討が必要です。月額定額制、従量課金制、買い切り型など様々な料金形態があるため、自社の利用頻度や規模に応じて選択しましょう。
録画・アーカイブ機能の有無
ライブ配信後の録画・アーカイブ機能は、企業利用において非常に重要な要素です。
配信を見逃した従業員や顧客が後から視聴できるだけでなく、研修資料や営業ツールとして二次活用も可能になります。自動録画機能の有無、録画データの保存期間、ダウンロード可能性、編集機能の充実度などを確認しましょう。
また、アーカイブの管理機能も重要なポイントです。タイトル設定、タグ付け、検索機能、フォルダ分け機能などがあると、大量のアーカイブを効率的に管理できます。
チャット・コメント機能の質
視聴者とのリアルタイムコミュニケーションを実現するチャット・コメント機能は、ライブ配信の魅力を高める重要な要素です。
基本的なテキストチャット機能に加えて、絵文字やスタンプ機能、質問機能、アンケート機能などがあると、より活発な双方向コミュニケーションが期待できます。
また、モデレーション機能により不適切なコメントを制御できることも重要です。企業向けの配信では、Q&A機能や挙手機能、ブレイクアウトルーム機能なども有用です。これらの機能により、セミナーや研修での質疑応答がスムーズに行えます。
サポート体制の充実度
企業がライブ配信を安心して活用するためには、充実したサポート体制が重要です。技術的なトラブルや操作方法に関する疑問に迅速に対応してもらえるかどうかは、配信の成功を左右する要因となります。
サポート方法としては、電話、メール、チャット、FAQ、マニュアルなどがあり、複数の方法でサポートを受けられることが理想的です。
ライブ配信のトラブル対処法

企業のライブ配信では、技術的なトラブルや予期せぬ問題が発生する可能性があります。視聴者に良い印象を与え、配信を成功させるためには、事前の準備と適切な対処法を知っておくことが重要です。
ここでは、ライブ配信でよく発生するトラブルとその対処法について詳しく解説していきます。これらのポイントを押さえることで、安定した配信を実現できるでしょう。
事前の機材テストを徹底する
ライブ配信の成功には、事前の機材テストが欠かせません。カメラ、マイク、配信ソフト、インターネット回線など、すべての機材が正常に動作するかを本番前に必ず確認しましょう。
特に音声は視聴者の満足度に大きく影響するため、マイクの音質やボリューム調整は念入りにチェックが必要です。配信当日と同じ環境でリハーサルを行い、実際の配信時間と同じ長さでテストすることをおすすめします。
これにより、長時間配信での機材の安定性も確認できます。
バックアップ回線を準備しておく
インターネット回線の不具合は、ライブ配信において最も致命的なトラブルの一つです。
メイン回線が途切れた場合に備えて、必ずバックアップ回線を用意しておきましょう。
モバイルWi-Fiルーターや4G/5G回線を活用したテザリング機能など、複数の接続手段を確保することが重要です。バックアップ回線は、メイン回線と異なるプロバイダーや通信方式を選ぶことで、同時に障害が発生するリスクを軽減できます。
配信スタッフの役割分担を明確化
スムーズなライブ配信を実現するには、配信スタッフ間での役割分担を明確にしておくことが不可欠です。
配信オペレーター、音響担当、進行管理者、視聴者対応担当など、それぞれの責任範囲を事前に決めておきましょう。トラブル発生時には、誰がどのような対応を取るかを明確にしておくことで、迅速な問題解決が可能になります。
企業のライブ配信はAirzにお任せください

ここまでご紹介したように、企業のライブ配信には多くのメリットがある一方で、トラブル対応や機材準備など専門的なノウハウも欠かせません。だからこそ、実績豊富なプロに任せることで安心して配信に臨むことができます。
Airzでは、セミナーやシンポジウム、学会、研修・式典、株主総会などあらゆるシーンに対応し、10名から3,000名規模まで柔軟にサポートします。ZoomやWebex、YouTube、Teamsといった配信ツールを含め幅広く対応し、回線や機材を最適化して高画質・高音質の配信を実現します。進行管理や会場選定、告知用サイト制作やメール配信、当日のオペレーションやアーカイブ納品まで一気通貫で支援できるのも特長です。
ベーシックプランは10万円から、オンライン完結型は5万円から利用可能で、打ち合わせは即日対応・お見積りも最短1営業日で提示できます。
初めての方も「どんな配信ができるか」から気軽にご相談いただけ、無料資料のダウンロードも可能です。企業ライブ配信を成功させたい方は、ぜひご相談ください。