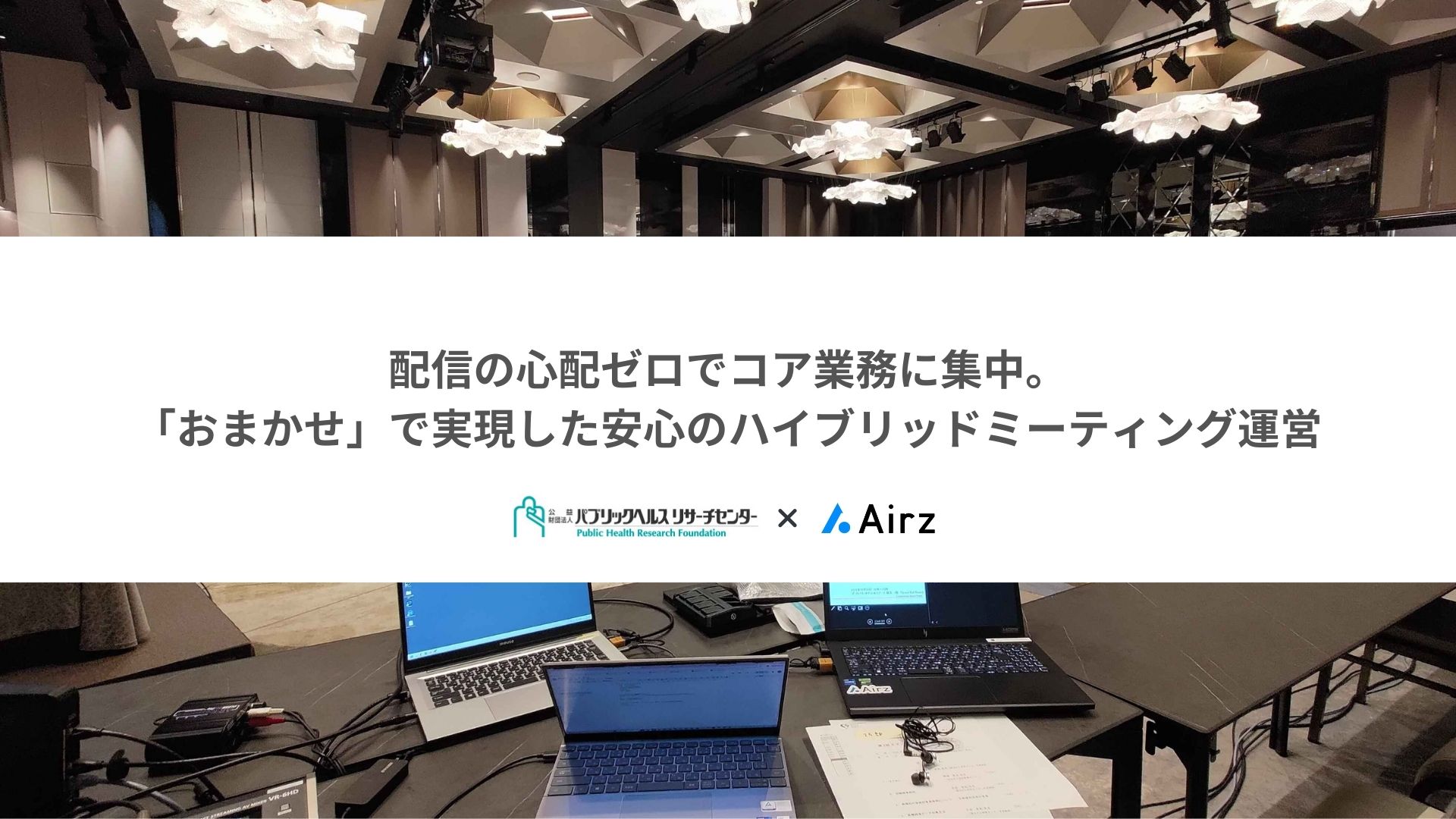【2025年最新】展示会ライブ配信とは?メリット・デメリットからサービス選びまで徹底解説
 更新日
更新日

展示会の現場に足を運ばなくても、最新情報や製品の魅力をリアルタイムで体験できる「展示会ライブ配信」が注目を集めています。オンラインでの参加は、地理的制約やコストの壁を取り払い、より多くの人々に情報発信できる新たな手法です。
本記事では、展示会ライブ配信のメリットやデメリット、トラブル対策、サービス会社選びのポイント、今後のトレンドまで分かりやすく解説します。

展示会ライブ配信とは、展示会の様子をリアルタイムでインターネット上に配信するサービスのことです。従来の展示会は会場に足を運ぶ必要がありましたが、ライブ配信により遠方からでも参加が可能になりました。
出展企業のブース紹介や製品デモンストレーション、セミナーなどの内容を、YouTubeやZoomなどの配信プラットフォームを通じて視聴者に届けることができます。
コロナ禍以降、バーチャル展示会やハイブリッド展示会の需要が急速に高まり、時間や場所の制約を受けない新しい展示会の形として注目されています。
展示会ライブ配信は、従来の物理的な展示会の制約を超え、多くの利点をもたらします。コロナ禍を機に急速に普及したこの手法は、現在では企業のマーケティング戦略において重要な位置を占めています。地理的制約の解消から、コスト削減、安全性の確保まで、様々な観点からメリットが存在します。
展示会ライブ配信最大の魅力は、場所を選ばずに参加できることです。
従来の展示会では会場までの移動が必要でしたが、オンライン配信により自宅やオフィスから気軽に参加できるようになりました。特に海外からの参加者にとって、ビザ取得や長時間の移動が不要となるため、参加のハードルが大幅に下がります。
また、地方に拠点を持つ企業や個人事業主も、首都圏で開催される展示会に容易にアクセスできます。これにより、従来は参加が困難だった潜在顧客との接点創出が可能となり、企業のビジネス機会が飛躍的に拡大します。
展示会参加にかかる経費を大幅に削減できることも、ライブ配信の重要なメリットです。
従来の展示会参加では、交通費、宿泊費、食事代などが必要でしたが、オンライン参加により これらの費用がほぼゼロになります。特に遠方からの参加者や海外からの参加者にとって、この経済的メリットは非常に大きいものです。
企業側においても、出張費の予算を他の重要な業務に振り分けることができ、より効率的な経営資源の活用が可能となります。
録画された内容は、社内での情報共有にも活用できます。参加できなかった同僚や上司に対して、重要なポイントを動画で共有することで、効率的な社内展開が可能になります。
また、チャットでの質問は文字として記録されるため、後から内容を見返すことができ、重要な情報を忘れる心配がありません。出展者側も、よくある質問をまとめて回答したり、個別の詳細な相談に対応したりと、柔軟な対応が可能になります。

展示会ライブ配信は多くのメリットがある一方で、従来の対面型展示会と比較していくつかの課題も存在します。
ここでは、展示会ライブ配信を導入する際に理解しておくべき主要なデメリットについて詳しく解説していきます。
例えば、精密機器や工作機械の場合、振動の少なさや操作時の感触といった重要な特徴を体感することができません。 このため、参加者は十分な情報を得られずに検討を保留してしまう可能性があります。
ライブ配信形式では、従来の展示会で可能だった自然な対面コミュニケーションの実現が困難になります。
リアルな展示会では、参加者の表情や身振り手振りから関心度を読み取り、その場に応じた柔軟な対応が可能でした。 オンライン環境では、チャット機能やビデオ通話を活用できるものの、複数の参加者との同時対応や、偶発的な出会いから生まれるビジネスチャンスが制限されてしまいます。
実際の展示会場では、多くの来場者で賑わう様子や、実演デモンストレーションの迫力、製品の実際のスケール感などが、参加者の購買意欲や関心を大きく高める要素となっています。 ライブ配信では、カメラの画角や音声品質の制約により、こうした臨場感のある体験を提供することが制限されます。
特に大型機械や建設機器のような製品では、その圧倒的な存在感やスケールを伝えることが困難になります。
出展者側の回線トラブルだけでなく、参加者側のネットワーク環境によっても配信品質は左右されます。モバイル回線を使用している参加者や、帯域制限のある環境からアクセスしている場合、満足な視聴体験を提供できないことがあります。
このような技術的な問題は、せっかくの商談機会を逸失させる原因となりかねません。

展示会ライブ配信は、リアルタイムで多くの視聴者に情報を届ける重要な手段ですが、技術的なトラブルが発生すると大きな損失につながる可能性があります。
ここでは、安定した配信を実現するための具体的なトラブル対策について詳しく解説します。
このような事態を避けるため、メイン回線とは別に複数の回線を用意することが重要です。携帯キャリアの異なるモバイルルーターを複数台準備し、さらに有線LANとの組み合わせを検討しましょう。
実際に多くの企業では、NTTドコモ、au、ソフトバンクの3キャリアのモバイルルーターを同時に持参し、回線状況に応じて瞬時に切り替えられる体制を整えています。
メインカメラと同等性能の予備カメラ、ワイヤレスマイクの予備バッテリーや受信機、さらに配信用PCのバックアップ機も準備しておきましょう。実際の配信現場では、機材トラブルが発生した際に5分以内に復旧できるよう、予備機材をすぐに使える状態でスタンバイさせています。
リハーサルでは、配信開始から終了まで全ての工程を実際に行い、音声レベル、映像品質、配信の安定性を確認しましょう。特に複数のカメラを切り替える場合や、プレゼンテーション資料を画面共有する際の操作手順を繰り返し練習することが重要です。
また、技術スタッフは展示会の内容についても事前に理解しておくことで、配信中の適切なカメラワークや音声調整が可能になり、より質の高い配信を実現できます。
録画は配信用PCとは別の機器で行うことが重要です。配信用PCがトラブルで停止しても、録画は継続される仕組みを構築しましょう。

展示会ライブ配信を成功させるには、信頼できるサービス会社の選定が重要です。配信の品質や安定性は、視聴者の満足度に直結し、企業のブランドイメージにも大きく影響します。適切な会社を選ぶことで、技術的なトラブルを回避し、効果的な情報発信が実現できるでしょう。
以下では、サービス会社選定時に重視すべき5つのポイントを詳しく解説します。
特に同業界や類似規模の展示会での配信経験があるかどうかは重要な判断材料となります。実績豊富な会社であれば、展示会特有の課題や要求を理解しており、適切な提案ができるからです。 成功事例を詳しく聞くことで、その会社の技術力やサービスレベルを把握できます。
費用対効果を正しく評価するためには、単純な価格比較だけでなく、提供されるサービス内容との兼ね合いを考慮する必要があります。例えば、低価格でもカメラ台数が少なく映像品質が劣る場合と、適正価格で高品質な配信が可能な場合では、後者の方が結果的に高い効果を得られることが多いです。
長期的な視点で見た時のコストパフォーマンスを重視し、最適なプランを選択しましょう。
例えば、複数ブースの同時配信や特定製品のクローズアップ撮影など、展示会特有の要求に対応可能かを確認しましょう。
技術面でのカスタマイズ対応も重要です。企業ロゴやテロップの挿入、背景デザインの変更、配信画面のレイアウト調整など、ブランディングに配慮した演出が可能かどうかを事前に確認してください。
特に大規模な展示会では、トラブルの影響が大きくなるため、複数の技術者による体制や、予備の配信システムの準備があると安心です。 過去のトラブル対応事例やその解決方法について具体的に聞くことで、その会社の対応力を判断できます。
特に同業界や類似規模の企業からの評価は参考になります。 顧客満足度の高い会社は、継続的な改善努力を行っており、最新の技術やトレンドにも敏感です。
配信の品質、スタッフの対応、料金の妥当性、トラブル時の対応など、具体的な体験談を聞くことで、より正確な判断ができるでしょう。

展示会ライブ配信は、デジタル技術の急速な発展により大きな変革期を迎えています。従来の2D配信から脱却し、より没入感のある体験を提供する技術が次々と登場しているのです。
参加者は仮想空間内を自由に歩き回り、興味のあるブースに近づいて詳細な製品情報を確認したり、他の参加者とリアルタイムでコミュニケーションを取ったりすることが可能です。
また、物理的な制約がないため、通常では不可能な演出や展示方法も実現できます。
この高画質配信により、製品の細部まで鮮明に映し出すことができ、参加者は実物を目の前で見ているような感覚で商品を確認できます。特に精密機器や高級品の展示において、その効果は絶大でしょう。
音声認識技術と機械翻訳技術の組み合わせにより、プレゼンターの発言がリアルタイムで多言語に翻訳され、字幕として表示されます。これにより、海外市場への展開を目指す企業にとって、より効果的な国際的なアプローチが可能になるでしょう。

「自社のイベントでも取り入れてみたい」「配信のやり方に不安がある」という方は、株式会社Airzのハイブリッド配信サービス「Airz Hybrid」を検討してみてはいかがでしょうか。セミナーやシンポジウム、研修・式典、株主総会まで幅広く対応し、Zoom・Webex・YouTube・Teamsといった主要ツールにも柔軟に対応可能です。
進行管理から会場・機材の手配、当日のオペレーションやアーカイブ動画の納品までトータルにサポートしてくれるため、初めての主催でも安心して進められます。
「自社でも取り入れてみたい」と感じた方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。ご相談・お見積りは無料、最短即日対応が可能です。
本記事では、展示会ライブ配信のメリットやデメリット、トラブル対策、サービス会社選びのポイント、今後のトレンドまで分かりやすく解説します。
Table of Contents
展示会ライブ配信とは

展示会ライブ配信とは、展示会の様子をリアルタイムでインターネット上に配信するサービスのことです。従来の展示会は会場に足を運ぶ必要がありましたが、ライブ配信により遠方からでも参加が可能になりました。
出展企業のブース紹介や製品デモンストレーション、セミナーなどの内容を、YouTubeやZoomなどの配信プラットフォームを通じて視聴者に届けることができます。
コロナ禍以降、バーチャル展示会やハイブリッド展示会の需要が急速に高まり、時間や場所の制約を受けない新しい展示会の形として注目されています。
展示会ライブ配信のメリット
展示会ライブ配信は、従来の物理的な展示会の制約を超え、多くの利点をもたらします。コロナ禍を機に急速に普及したこの手法は、現在では企業のマーケティング戦略において重要な位置を占めています。地理的制約の解消から、コスト削減、安全性の確保まで、様々な観点からメリットが存在します。
地理的制約なく世界中から参加可能
展示会ライブ配信最大の魅力は、場所を選ばずに参加できることです。
従来の展示会では会場までの移動が必要でしたが、オンライン配信により自宅やオフィスから気軽に参加できるようになりました。特に海外からの参加者にとって、ビザ取得や長時間の移動が不要となるため、参加のハードルが大幅に下がります。
また、地方に拠点を持つ企業や個人事業主も、首都圏で開催される展示会に容易にアクセスできます。これにより、従来は参加が困難だった潜在顧客との接点創出が可能となり、企業のビジネス機会が飛躍的に拡大します。
移動費用や宿泊費などのコストが削減
展示会参加にかかる経費を大幅に削減できることも、ライブ配信の重要なメリットです。
従来の展示会参加では、交通費、宿泊費、食事代などが必要でしたが、オンライン参加により これらの費用がほぼゼロになります。特に遠方からの参加者や海外からの参加者にとって、この経済的メリットは非常に大きいものです。
企業側においても、出張費の予算を他の重要な業務に振り分けることができ、より効率的な経営資源の活用が可能となります。
録画機能で後から何度でも視聴可能
多くの展示会ライブ配信では、アーカイブ機能が提供されており、配信終了後も繰り返し視聴できます。リアルタイムで参加できなかった場合や、重要な部分を再確認したい場合に非常に便利です。録画された内容は、社内での情報共有にも活用できます。参加できなかった同僚や上司に対して、重要なポイントを動画で共有することで、効率的な社内展開が可能になります。
チャット機能で気軽に質問や相談ができる
展示会ライブ配信では、リアルタイムチャット機能により、出展者と直接コミュニケーションを取ることができます。対面での質問に比べて心理的なハードルが低く、気軽に疑問点を投げかけられる環境が整っています。また、チャットでの質問は文字として記録されるため、後から内容を見返すことができ、重要な情報を忘れる心配がありません。出展者側も、よくある質問をまとめて回答したり、個別の詳細な相談に対応したりと、柔軟な対応が可能になります。
展示会ライブ配信のデメリット

展示会ライブ配信は多くのメリットがある一方で、従来の対面型展示会と比較していくつかの課題も存在します。
ここでは、展示会ライブ配信を導入する際に理解しておくべき主要なデメリットについて詳しく解説していきます。
実物を直接触って確認できない
展示会ライブ配信における最大のデメリットは、参加者が実際の製品やサービスを直接手に取って確認できない点です。特に製造業や技術系の展示会では、製品の質感、重量、操作感などが購買決定において重要な要素となります。 カメラを通した映像だけでは、素材の手触りや細かな仕上がり、実際のサイズ感を正確に伝えることが困難です。例えば、精密機器や工作機械の場合、振動の少なさや操作時の感触といった重要な特徴を体感することができません。 このため、参加者は十分な情報を得られずに検討を保留してしまう可能性があります。
対面での深いコミュニケーションが困難
ライブ配信形式では、従来の展示会で可能だった自然な対面コミュニケーションの実現が困難になります。
リアルな展示会では、参加者の表情や身振り手振りから関心度を読み取り、その場に応じた柔軟な対応が可能でした。 オンライン環境では、チャット機能やビデオ通話を活用できるものの、複数の参加者との同時対応や、偶発的な出会いから生まれるビジネスチャンスが制限されてしまいます。
画面越しでは臨場感が伝わりにくい
展示会特有の活気ある雰囲気や臨場感を、画面越しで完全に再現することは非常に困難です。実際の展示会場では、多くの来場者で賑わう様子や、実演デモンストレーションの迫力、製品の実際のスケール感などが、参加者の購買意欲や関心を大きく高める要素となっています。 ライブ配信では、カメラの画角や音声品質の制約により、こうした臨場感のある体験を提供することが制限されます。
特に大型機械や建設機器のような製品では、その圧倒的な存在感やスケールを伝えることが困難になります。
ネットワークの不安定さで音声が途切れる
ライブ配信では、インターネット回線の品質に大きく依存するため、ネットワークの不安定さが重大な問題となります。特に重要なプレゼンテーションや製品説明の最中に音声が途切れたり、映像が乱れたりすると、参加者の集中力が削がれ、内容が正確に伝わらない可能性があります。出展者側の回線トラブルだけでなく、参加者側のネットワーク環境によっても配信品質は左右されます。モバイル回線を使用している参加者や、帯域制限のある環境からアクセスしている場合、満足な視聴体験を提供できないことがあります。
このような技術的な問題は、せっかくの商談機会を逸失させる原因となりかねません。
展示会ライブ配信中のトラブル対策
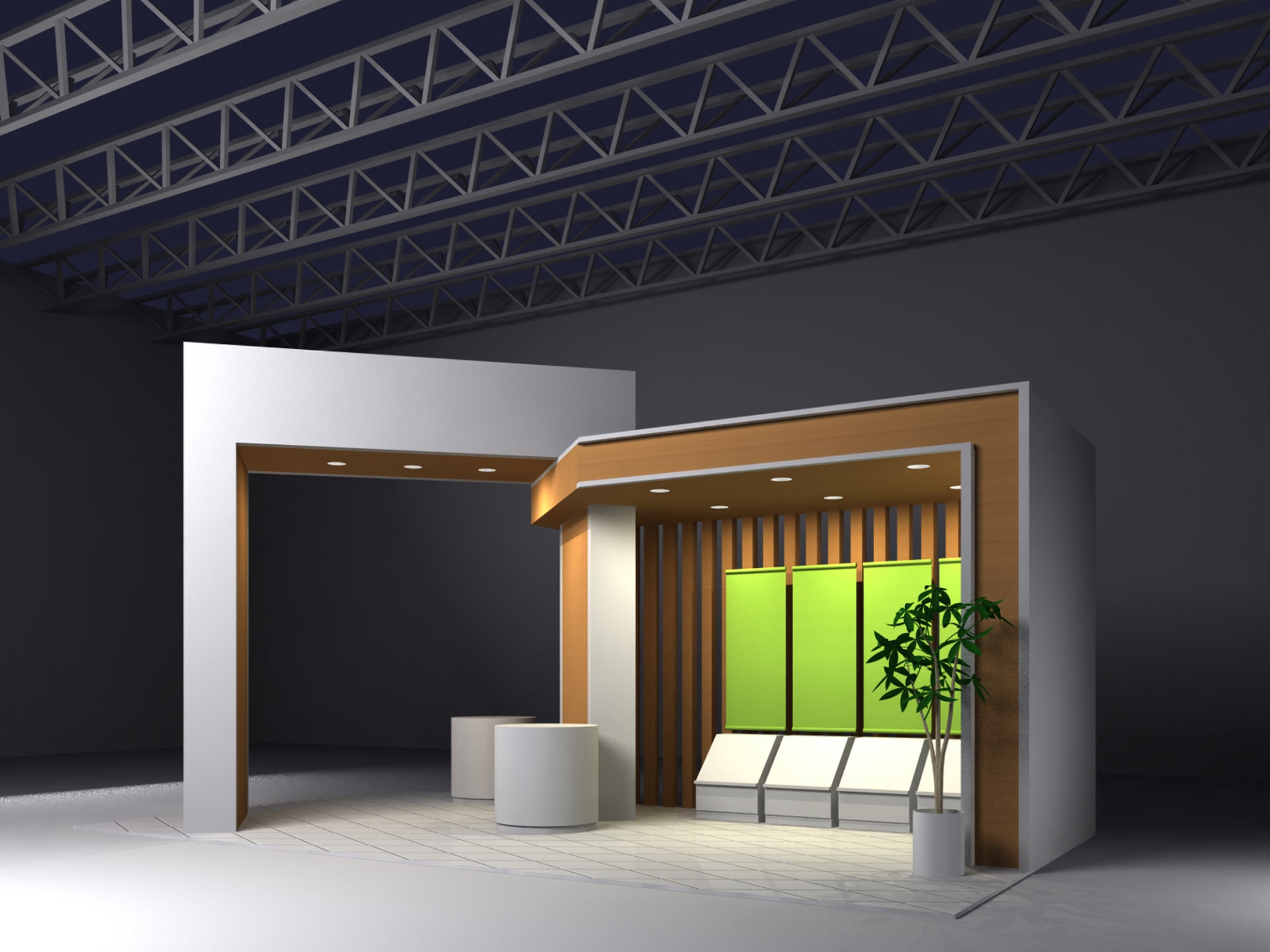
展示会ライブ配信は、リアルタイムで多くの視聴者に情報を届ける重要な手段ですが、技術的なトラブルが発生すると大きな損失につながる可能性があります。
ここでは、安定した配信を実現するための具体的なトラブル対策について詳しく解説します。
複数のインターネット回線を準備する
展示会会場でのインターネット回線は、予想以上に不安定になることが多々あります。会場の無線LANが混雑していたり、有線LANの速度が十分でない場合、配信が途切れてしまうリスクが高まるでしょう。このような事態を避けるため、メイン回線とは別に複数の回線を用意することが重要です。携帯キャリアの異なるモバイルルーターを複数台準備し、さらに有線LANとの組み合わせを検討しましょう。
実際に多くの企業では、NTTドコモ、au、ソフトバンクの3キャリアのモバイルルーターを同時に持参し、回線状況に応じて瞬時に切り替えられる体制を整えています。
機材の予備を必ず用意しておく
ライブ配信で使用するカメラ、マイク、配信用PCなどの機材は、突然故障する可能性があります。特に展示会会場のような環境では、電源トラブルや物理的な衝撃により機材が使用不能になることも珍しくありません。 予備機材の準備は、配信の継続性を保つために欠かせない要素です。メインカメラと同等性能の予備カメラ、ワイヤレスマイクの予備バッテリーや受信機、さらに配信用PCのバックアップ機も準備しておきましょう。実際の配信現場では、機材トラブルが発生した際に5分以内に復旧できるよう、予備機材をすぐに使える状態でスタンバイさせています。
事前のリハーサルで問題点を洗い出す
本番と同じ環境でのリハーサルを実施することで、潜在的な問題を事前に発見し、対策を講じることができます。展示会会場でのリハーサルが理想的ですが、難しい場合は類似環境での入念なテストが必要です。リハーサルでは、配信開始から終了まで全ての工程を実際に行い、音声レベル、映像品質、配信の安定性を確認しましょう。特に複数のカメラを切り替える場合や、プレゼンテーション資料を画面共有する際の操作手順を繰り返し練習することが重要です。
技術スタッフを現場に常駐させる
展示会ライブ配信では、技術的な知識を持つスタッフの現場常駐が不可欠です。配信機材の操作に慣れていない担当者だけでは、トラブル発生時に適切な対応ができない可能性が高くなります。技術スタッフには、配信システム全体の知識はもちろん、各種機材の操作方法、トラブルシューティングのスキルが求められるでしょう。また、技術スタッフは展示会の内容についても事前に理解しておくことで、配信中の適切なカメラワークや音声調整が可能になり、より質の高い配信を実現できます。
録画機能で後日配信できる仕組み
ライブ配信中にトラブルが発生し、一部の視聴者が見逃してしまった場合や、配信自体が中断してしまった場合に備えて、録画機能の活用は必須です。録画データがあれば、後日アーカイブ配信として視聴者に提供することができます。録画は配信用PCとは別の機器で行うことが重要です。配信用PCがトラブルで停止しても、録画は継続される仕組みを構築しましょう。
展示会ライブ配信サービス会社の選び方

展示会ライブ配信を成功させるには、信頼できるサービス会社の選定が重要です。配信の品質や安定性は、視聴者の満足度に直結し、企業のブランドイメージにも大きく影響します。適切な会社を選ぶことで、技術的なトラブルを回避し、効果的な情報発信が実現できるでしょう。
以下では、サービス会社選定時に重視すべき5つのポイントを詳しく解説します。
過去の展示会配信実績と成功事例
展示会ライブ配信サービス会社を選ぶ際は、過去の配信実績と成功事例の確認が不可欠です。特に同業界や類似規模の展示会での配信経験があるかどうかは重要な判断材料となります。実績豊富な会社であれば、展示会特有の課題や要求を理解しており、適切な提案ができるからです。 成功事例を詳しく聞くことで、その会社の技術力やサービスレベルを把握できます。
料金体系の透明性と費用対効果
料金体系が明確で透明性の高いサービス会社を選ぶことは、予算管理と費用対効果の最大化につながります。初期費用、配信時間による従量課金、機材レンタル費用、スタッフ派遣費用など、全ての項目が詳細に提示されているかを確認しましょう。費用対効果を正しく評価するためには、単純な価格比較だけでなく、提供されるサービス内容との兼ね合いを考慮する必要があります。例えば、低価格でもカメラ台数が少なく映像品質が劣る場合と、適正価格で高品質な配信が可能な場合では、後者の方が結果的に高い効果を得られることが多いです。
長期的な視点で見た時のコストパフォーマンスを重視し、最適なプランを選択しましょう。
カスタマイズ対応の柔軟性
展示会の規模や目的に応じて、配信内容や演出をカスタマイズできる柔軟性は重要な選定基準です。標準的なパッケージプランだけでなく、企業の個別ニーズに対応できるサービス会社を選ぶことで、より効果的な配信が実現できます。例えば、複数ブースの同時配信や特定製品のクローズアップ撮影など、展示会特有の要求に対応可能かを確認しましょう。
技術面でのカスタマイズ対応も重要です。企業ロゴやテロップの挿入、背景デザインの変更、配信画面のレイアウト調整など、ブランディングに配慮した演出が可能かどうかを事前に確認してください。
トラブル時の迅速な対応力
ライブ配信では技術的なトラブルが発生する可能性があるため、緊急時の対応力は極めて重要な評価項目です。配信中の音声や映像の不具合、ネットワーク接続の問題、機材の故障など、様々なトラブルに対して迅速かつ適切に対処できる体制が整っているかを確認しましょう。特に大規模な展示会では、トラブルの影響が大きくなるため、複数の技術者による体制や、予備の配信システムの準備があると安心です。 過去のトラブル対応事例やその解決方法について具体的に聞くことで、その会社の対応力を判断できます。
顧客満足度と口コミ評価
サービス会社の顧客満足度と口コミ評価は、実際のサービス品質を知るための貴重な情報源です。過去のクライアントからの評価や推薦状、オンラインでの口コミやレビューなどを総合的に確認し、客観的な評価を行いましょう。特に同業界や類似規模の企業からの評価は参考になります。 顧客満足度の高い会社は、継続的な改善努力を行っており、最新の技術やトレンドにも敏感です。
配信の品質、スタッフの対応、料金の妥当性、トラブル時の対応など、具体的な体験談を聞くことで、より正確な判断ができるでしょう。
展示会ライブ配信の今後のトレンド

展示会ライブ配信は、デジタル技術の急速な発展により大きな変革期を迎えています。従来の2D配信から脱却し、より没入感のある体験を提供する技術が次々と登場しているのです。
VR技術でより没入感のある体験提供
VR技術を活用した展示会ライブ配信は、参加者に革新的な体験をもたらしています。従来の画面越しの視聴とは異なり、VRヘッドセットを装着することで、まるで実際の展示会場にいるかのような臨場感を味わうことができるでしょう。参加者は仮想空間内を自由に歩き回り、興味のあるブースに近づいて詳細な製品情報を確認したり、他の参加者とリアルタイムでコミュニケーションを取ったりすることが可能です。
また、物理的な制約がないため、通常では不可能な演出や展示方法も実現できます。
5G通信による超高画質配信の実現
5G通信技術の普及により、展示会ライブ配信は画質面で飛躍的な向上を遂げています。従来の4G回線では困難だった4K・8K映像のリアルタイム配信が、遅延なくスムーズに行えるようになったのです。この高画質配信により、製品の細部まで鮮明に映し出すことができ、参加者は実物を目の前で見ているような感覚で商品を確認できます。特に精密機器や高級品の展示において、その効果は絶大でしょう。
リアルタイム翻訳機能の標準装備
AI技術の進歩により、リアルタイム翻訳機能が展示会ライブ配信の標準機能として普及し始めています。この技術により、言語の壁を越えて世界中の参加者が同じ展示会を楽しめるようになりました。音声認識技術と機械翻訳技術の組み合わせにより、プレゼンターの発言がリアルタイムで多言語に翻訳され、字幕として表示されます。これにより、海外市場への展開を目指す企業にとって、より効果的な国際的なアプローチが可能になるでしょう。
まとめ|展示会ライブ配信はAirzにお任せください

「自社のイベントでも取り入れてみたい」「配信のやり方に不安がある」という方は、株式会社Airzのハイブリッド配信サービス「Airz Hybrid」を検討してみてはいかがでしょうか。セミナーやシンポジウム、研修・式典、株主総会まで幅広く対応し、Zoom・Webex・YouTube・Teamsといった主要ツールにも柔軟に対応可能です。
進行管理から会場・機材の手配、当日のオペレーションやアーカイブ動画の納品までトータルにサポートしてくれるため、初めての主催でも安心して進められます。
「自社でも取り入れてみたい」と感じた方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。ご相談・お見積りは無料、最短即日対応が可能です。