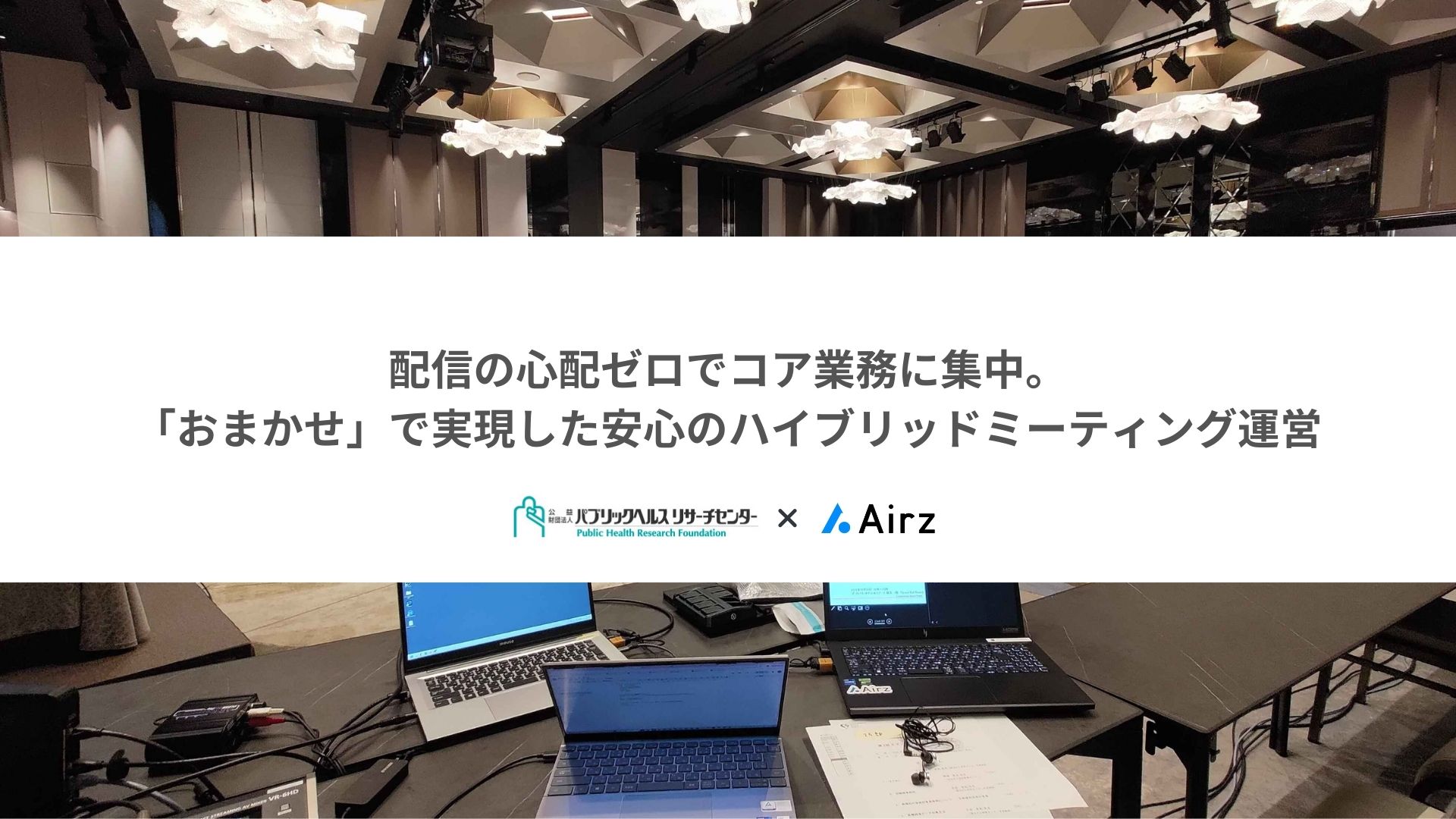オンライン研修とは?導入メリットから成功のコツまで完全ガイド!
 更新日
更新日

働き方の多様化が進む中、注目を集めているのが「オンライン研修」です。時間や場所を問わず受講できる利便性やコスト削減効果から、多くの企業で導入が進んでいます。
一方で、実技研修の難しさやネット環境への依存といった課題があるのも事実です。
この記事では、オンライン研修の特徴やメリット・デメリット、導入手順、成功のポイントまで詳しく解説します。オンライン研修の導入を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
 オンライン研修とは、インターネットを活用してWebブラウザ上で人材育成を行うことです。従来の集合型研修とは異なり、受講者が各自のパソコンやタブレットを使って、遠隔地からでも研修に参加できるのが特徴となります。
オンライン研修とは、インターネットを活用してWebブラウザ上で人材育成を行うことです。従来の集合型研修とは異なり、受講者が各自のパソコンやタブレットを使って、遠隔地からでも研修に参加できるのが特徴となります。
新型コロナウイルスの影響により急速に普及が進み、現在では多くの企業が導入を検討している教育システムです。
受講形式は、リアルタイムで講師と双方向のやり取りができるライブ配信型と、事前に録画された動画を視聴するオンデマンド型があります。
従来の集合研修では、受講者は指定された会場まで足を運ぶ必要がありましたが、オンライン研修ならインターネット環境があればどこからでも参加可能です。
また、在宅勤務中の社員や育児・介護で外出が困難な従業員も、自宅から気軽に研修を受けることができます。移動時間や交通費が不要になるため、企業にとってもコスト削減効果が期待できるでしょう。
さらに、録画型の研修であれば時間の制約も受けません。受講者は自分の都合に合わせて学習を進められるため、業務の繁忙期でも無理なく研修を完了できます。
この柔軟性こそが、現代の働き方改革に適した教育システムといえる理由です。
例えば、チャット機能を使った質疑応答、画面共有による資料の同時閲覧、ブレイクアウトルーム機能でのグループワークなど、デジタルならではの双方向性を実現できます。
また、受講状況の自動記録や理解度テストの即座採点、学習進捗の可視化など、管理者にとっても効率的な運営が可能です。

オンライン研修には大きく分けて「ライブ型」と「オンデマンド型」の2種類があります。それぞれの特徴を理解し、研修目的や受講者の状況に応じて使い分けることが重要です。
一方で、受講時間が固定されるため、勤務シフトやタイムゾーンが異なる受講者には参加が難しいケースもあります。そのため、録画配信を組み合わせるなどの工夫が有効です。
ただし、ライブ型のような双方向性が少なく、受講者の主体性が求められる点には注意が必要です。理解度確認テストやアンケートなどを組み合わせることで、効果を高められます。
このように、オンライン研修は「ライブ型」と「オンデマンド型」を組み合わせることで、双方向性と柔軟性を両立させることができます。
 オンライン研修には、従来の集合研修にはない多くのメリットがあります。特に働き方の多様化が進む現代において、企業の人材育成戦略を大きく変える可能性を秘めています。
オンライン研修には、従来の集合研修にはない多くのメリットがあります。特に働き方の多様化が進む現代において、企業の人材育成戦略を大きく変える可能性を秘めています。
以下では、オンライン研修の主要なメリットについて詳しく解説していきます。
従来の集合研修では、全員が同じ時間に同じ場所に集まる必要がありましたが、オンライン形式なら自宅やサテライトオフィス、出張先からでも参加可能です。特にeラーニング形式では、受講者が自分の業務スケジュールに合わせて最適なタイミングで学習を進められます。
この柔軟性により、シフト勤務者や育児・介護で時間制約のある社員も研修を受講しやすくなります。
また、海外拠点の社員や地方勤務者にとっても、移動時間を気にすることなく本社と同等の研修機会を得られるため、教育格差の解消にも大きく貢献します。
従来の集合研修では、研修会場のレンタル費用、参加者の交通費、宿泊費、講師の移動費など多額の経費が発生していました。しかし、オンライン形式では会場費が不要となり、参加者の移動コストも一切かかりません。
一度の受講では理解しきれなかった重要なポイントや、複雑な概念について、自分のペースで繰り返し学習できるのは大きなメリットです。
特に技術研修や専門知識を扱う内容では、この機能の価値は非常に高いと言えるでしょう。
さらに、同じ研修を複数回実施する際も、録画機能を活用すれば講師費用の重複も避けられます。
従来の集合研修では、各拠点から代表者を選出して本社に集める必要がありましたが、オンライン形式なら全社員が同時に同じ内容を受講できます。
これにより、情報伝達のタイムラグや内容の相違を防ぎ、組織全体で統一された知識やスキルの習得が実現できます。
従来の紙ベースの資料配布では、印刷コストや配送時間、保管場所の確保などが課題となっていました。
しかし、オンライン形式なら、PDFファイルや動画資料を瞬時に全受講者に配信でき、資料の更新があった場合もリアルタイムで最新版を共有できます。
従来の集合研修では、講師の移動費用や時間的制約により、招待できる講師が限定されがちでした。しかし、オンライン形式なら、東京の企業が大阪や福岡の専門家から直接指導を受けることも容易に実現できます。
この柔軟性により、企業は特定分野の第一人者や、実務経験豊富な専門家から質の高い研修を受ける機会を大幅に増やせます。
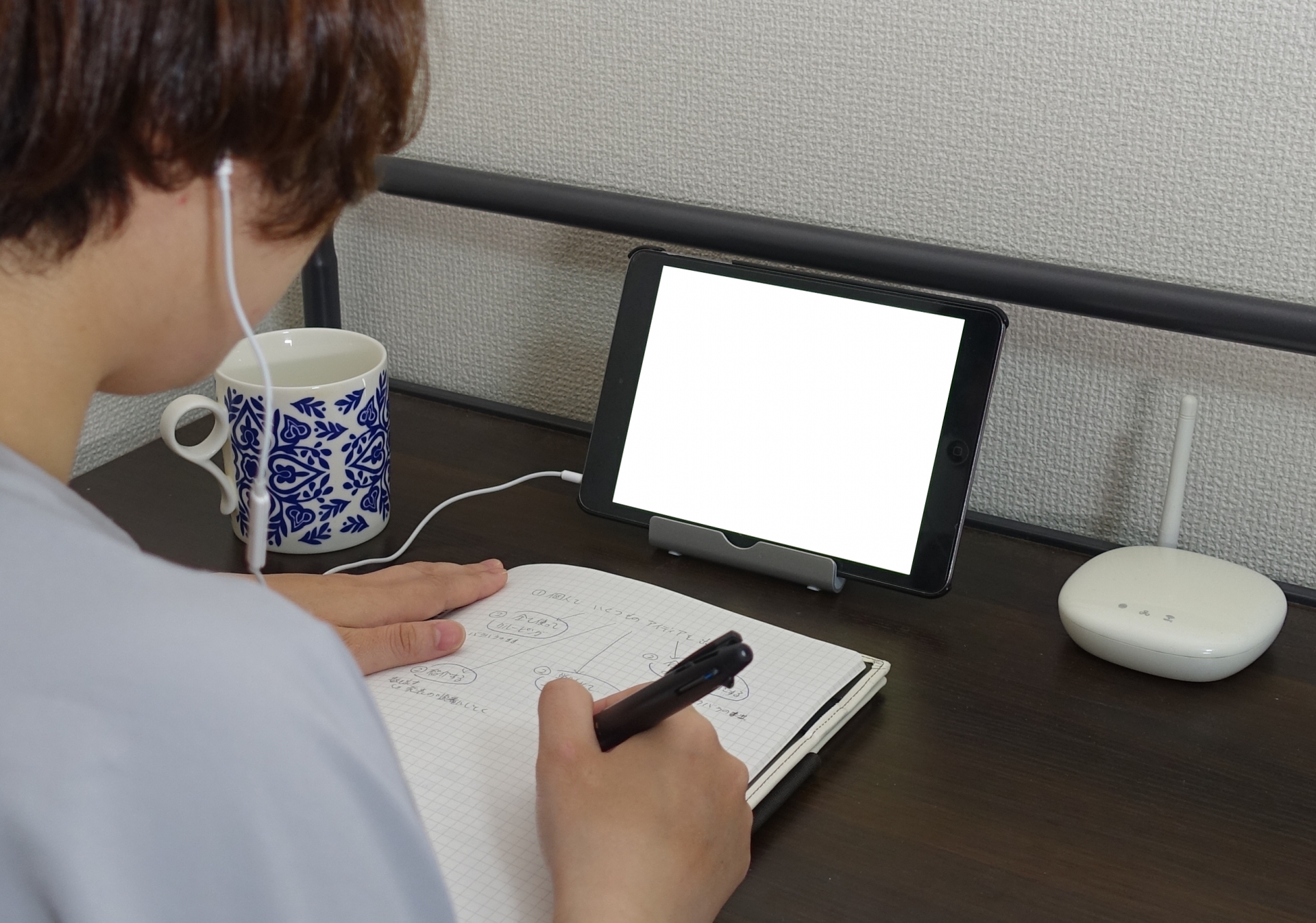 オンライン研修には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。これらの課題を事前に理解し、適切に対策することで、より効果的な研修運営が可能となります。
オンライン研修には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。これらの課題を事前に理解し、適切に対策することで、より効果的な研修運営が可能となります。
ここでは、オンライン研修の主要なデメリットについて詳しく解説します。
実際に手を動かして覚える技術や、身体的な動作を伴うスキルの習得においては、対面での指導が不可欠になります。
このような研修では、オンラインとオフラインを組み合わせたハイブリッド型の研修設計を検討する必要があるでしょう。
特に地方拠点や在宅勤務者の中には、十分なネット環境が整っていない場合があり、音声の途切れや画面の遅延、接続の切断などが発生することがあります。
企業側では事前の環境チェックや代替手段の準備、必要に応じてネット環境の整備支援を行うことが重要です。
講師は受講者の反応を正確に把握することが困難になり、適切なタイミングでの指導やフォローが難しくなることもあります。
この問題を軽減するためには、チャット機能の活用や定期的な確認タイムの設定、カメラの適切な使用などの工夫が必要です。
同じ空間を共有することで生まれる緊張感や集中力、参加者同士の連帯感などが薄れがちになります。
特にチームビルディングや組織文化の浸透を目的とした研修では、この臨場感の欠如が大きな問題となります。画面の向こう側にいる他の参加者との距離感や、研修会場特有の学習環境が失われることで、受講者のモチベーション維持が困難になる場合があります。
 オンライン研修を成功させるためには、計画的に導入手順を踏むことが重要です。ここでは、オンライン研修の導入を7つのステップに分けて詳しく解説します。
オンライン研修を成功させるためには、計画的に導入手順を踏むことが重要です。ここでは、オンライン研修の導入を7つのステップに分けて詳しく解説します。
新入社員のビジネスマナー習得、管理職のマネジメントスキル向上、全社的なコンプライアンス教育など、具体的な目標を設定することが必要です。
対象者の年齢層、ITリテラシーレベル、勤務形態、地理的分散状況なども詳細に把握する必要があります。例えば、地方拠点の営業担当者を対象とする場合、移動時間の削減効果や柔軟な受講スケジュールの重要性が高くなります。
安定した通信環境、使いやすいインターフェース、受講者管理機能、セキュリティ対策などを総合的に評価することが重要です。特に、受講者のITリテラシーレベルに合わせて選定することが、重要な要素となります。
また、既存システムとの連携可能性、コスト面、サポート体制なども考慮し、複数のプラットフォームを比較検討した上で最終決定を行いましょう。
中には、トライアル期間があるプラットフォームもあるので、事前に実際の操作感を確認すしておくと良いでしょう。
オンライン環境では受講者の集中力維持が課題となるため、30分から1時間程度のコンパクトな構成を心がけ、適度な休憩を挟むスケジュールを組みましょう。
コンテンツ制作では、一方的な講義形式では受講者の集中力が切れてしまう可能性があります。そのため、チャット機能を活用した質疑応答、グループワーク、クイズやアンケートなど、双方向のコミュニケーションを構成に取り入れると効果的です。
受講者の参加意識も高まり、理解度の向上を図ることができます。
事前にテスト接続を実施してもらい、音声や映像の品質、操作方法をチェックしておくと安心です。ITリテラシーが低い受講者に対しては、個別サポートや操作マニュアルの配布を行い、不安を解消すると良いでしょう。
また、研修当日のトラブルに備え、技術サポート窓口の設置や代替手段の準備も欠かせません。受講者が安心して研修に参加できる環境を整えることが大切です。
また、チャット機能での質問対応や、技術的なトラブルが発生した際の柔軟な対応力必要です。
ネットワーク接続の不安定、音声トラブル、操作ミスなど、実際に起こりうる問題への対処法を事前に検証しておくことで、本番での混乱を最小限に抑えられます。
運用開始後は、継続的な効果測定と改善を行います。受講率、完了率、理解度テストの結果、受講者満足度調査などのデータを定期的に収集・分析し、研修の品質向上に活用しましょう。
得られたデータをもとに、コンテンツの改善、運営方法の最適化、新たな研修プログラムの企画などを継続的に実施していくことで、より効果的なオンライン研修に仕上げていきましょう。 オンライン研修を成功させるためには、事前の準備から研修後のフォローアップまで、計画的かつ継続的な取り組みが不可欠です。
オンライン研修を成功させるためには、事前の準備から研修後のフォローアップまで、計画的かつ継続的な取り組みが不可欠です。
ここでは、オンライン研修の効果を最大化するための具体的な運営ポイントを詳しく解説していきます。
特に初めてオンライン研修を実施する場合は、本番前に必ずリハーサルを実施しましょう。
技術的な準備として、安定したインターネット環境の確保、適切なマイクやカメラの設定、資料の共有方法などを事前にチェックします。受講者には操作マニュアルを配布し、研修開始前にテクニカルトレーニングを実施することで、当日のトラブルを未然に防げます。
研修中は受講者の名前を呼びかけたり、具体的な質問を投げかけたりして、一人ひとりが参加している実感を持てるよう工夫しましょう。
グループワークを実施する際は、ブレイクアウトルーム機能を使って小グループに分け、活発な議論を促すとより効果的に研修することができます。
アンケート結果や受講データを分析することで、改善すべき点を明確にできます。 受講者の声を反映させることで、より効果的な研修プログラムにすることが可能です。
 オンライン研修は、時間や場所を問わず受講できる柔軟性やコスト削減効果から、多くの企業で導入が進んでいます。一方で、実技研修の難しさやネット環境への依存といった課題もあり、成功には計画的な準備と専門的なサポートが欠かせません。
オンライン研修は、時間や場所を問わず受講できる柔軟性やコスト削減効果から、多くの企業で導入が進んでいます。一方で、実技研修の難しさやネット環境への依存といった課題もあり、成功には計画的な準備と専門的なサポートが欠かせません。
Airzは、企業ごとのニーズに合わせたオンライン研修ソリューションを提供し、会場費や交通費などの負担を抑えながら、全国や海外拠点を含む全社員へ均一な研修機会を届けます。企画から運営、効果測定まで一貫して対応し、教育格差の解消とスキル向上をサポートします。
また、ハイブリッドイベント配信の分野で、国際機関や省庁、大手企業を含む1,000回以上の配信実績を持ち、ZoomやTeamsなど主要ツールにも幅広く対応可能です。セミナーや社内研修、学会、国際会議まで、多様なシーンで安心して任せられる体制を整えています。
オンライン研修の導入を検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。
一方で、実技研修の難しさやネット環境への依存といった課題があるのも事実です。
この記事では、オンライン研修の特徴やメリット・デメリット、導入手順、成功のポイントまで詳しく解説します。オンライン研修の導入を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
Table of Contents
オンライン研修とは
 オンライン研修とは、インターネットを活用してWebブラウザ上で人材育成を行うことです。従来の集合型研修とは異なり、受講者が各自のパソコンやタブレットを使って、遠隔地からでも研修に参加できるのが特徴となります。
オンライン研修とは、インターネットを活用してWebブラウザ上で人材育成を行うことです。従来の集合型研修とは異なり、受講者が各自のパソコンやタブレットを使って、遠隔地からでも研修に参加できるのが特徴となります。
新型コロナウイルスの影響により急速に普及が進み、現在では多くの企業が導入を検討している教育システムです。
受講形式は、リアルタイムで講師と双方向のやり取りができるライブ配信型と、事前に録画された動画を視聴するオンデマンド型があります。
場所を問わず受講できる教育システム
オンライン研修の最大の魅力は、地理的制約を受けずに研修を受講できることです。従来の集合研修では、受講者は指定された会場まで足を運ぶ必要がありましたが、オンライン研修ならインターネット環境があればどこからでも参加可能です。
また、在宅勤務中の社員や育児・介護で外出が困難な従業員も、自宅から気軽に研修を受けることができます。移動時間や交通費が不要になるため、企業にとってもコスト削減効果が期待できるでしょう。
さらに、録画型の研修であれば時間の制約も受けません。受講者は自分の都合に合わせて学習を進められるため、業務の繁忙期でも無理なく研修を完了できます。
この柔軟性こそが、現代の働き方改革に適した教育システムといえる理由です。
デジタル技術を使った人材育成手法
オンライン研修は、最新のデジタル技術を駆使した革新的な人材育成アプローチです。Web会議システムやクラウドベースの学習管理システム(LMS)を活用することで、従来の対面研修では実現できなかった機能を提供することができます。例えば、チャット機能を使った質疑応答、画面共有による資料の同時閲覧、ブレイクアウトルーム機能でのグループワークなど、デジタルならではの双方向性を実現できます。
また、受講状況の自動記録や理解度テストの即座採点、学習進捗の可視化など、管理者にとっても効率的な運営が可能です。
オンライン研修の種類

オンライン研修には大きく分けて「ライブ型」と「オンデマンド型」の2種類があります。それぞれの特徴を理解し、研修目的や受講者の状況に応じて使い分けることが重要です。
ライブ型
ライブ型は、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールを活用し、講師と受講者がリアルタイムでやり取りできる研修形式です。 質問や意見交換がその場で可能なため、臨場感や双方向性が高く、受講者の集中力を維持しやすいのが特徴です。一方で、受講時間が固定されるため、勤務シフトやタイムゾーンが異なる受講者には参加が難しいケースもあります。そのため、録画配信を組み合わせるなどの工夫が有効です。
オンデマンド型
オンデマンド型は、事前に収録された動画を受講者が好きな時間に視聴できる形式です。 繰り返し視聴できるため復習しやすく、業務の合間や繁忙期でも自分のペースで学習を進められます。ただし、ライブ型のような双方向性が少なく、受講者の主体性が求められる点には注意が必要です。理解度確認テストやアンケートなどを組み合わせることで、効果を高められます。
このように、オンライン研修は「ライブ型」と「オンデマンド型」を組み合わせることで、双方向性と柔軟性を両立させることができます。
オンライン研修のメリット
 オンライン研修には、従来の集合研修にはない多くのメリットがあります。特に働き方の多様化が進む現代において、企業の人材育成戦略を大きく変える可能性を秘めています。
オンライン研修には、従来の集合研修にはない多くのメリットがあります。特に働き方の多様化が進む現代において、企業の人材育成戦略を大きく変える可能性を秘めています。
以下では、オンライン研修の主要なメリットについて詳しく解説していきます。
時間と場所の制約がない
オンライン研修の最大の魅力は、受講者が時間や場所に縛られることなく学習できる点にあります。従来の集合研修では、全員が同じ時間に同じ場所に集まる必要がありましたが、オンライン形式なら自宅やサテライトオフィス、出張先からでも参加可能です。特にeラーニング形式では、受講者が自分の業務スケジュールに合わせて最適なタイミングで学習を進められます。
この柔軟性により、シフト勤務者や育児・介護で時間制約のある社員も研修を受講しやすくなります。
また、海外拠点の社員や地方勤務者にとっても、移動時間を気にすることなく本社と同等の研修機会を得られるため、教育格差の解消にも大きく貢献します。
交通費や会場費が削減できる
オンライン研修の導入により、企業は大幅なコスト削減を実現できます。従来の集合研修では、研修会場のレンタル費用、参加者の交通費、宿泊費、講師の移動費など多額の経費が発生していました。しかし、オンライン形式では会場費が不要となり、参加者の移動コストも一切かかりません。
録画機能で復習が可能
オンライン研修では録画機能を活用することで、受講者が何度でも研修内容を振り返ることができます。一度の受講では理解しきれなかった重要なポイントや、複雑な概念について、自分のペースで繰り返し学習できるのは大きなメリットです。
特に技術研修や専門知識を扱う内容では、この機能の価値は非常に高いと言えるでしょう。
さらに、同じ研修を複数回実施する際も、録画機能を活用すれば講師費用の重複も避けられます。
多拠点の社員を同時に研修できる
オンライン研修では、全国各地や海外に散らばる多拠点の社員を一度に研修することが可能です。従来の集合研修では、各拠点から代表者を選出して本社に集める必要がありましたが、オンライン形式なら全社員が同時に同じ内容を受講できます。
これにより、情報伝達のタイムラグや内容の相違を防ぎ、組織全体で統一された知識やスキルの習得が実現できます。
簡単に研修資料を共有できる
デジタル環境を活用するオンライン研修では、研修資料の共有が極めて簡単かつ効率的に行えます。従来の紙ベースの資料配布では、印刷コストや配送時間、保管場所の確保などが課題となっていました。
しかし、オンライン形式なら、PDFファイルや動画資料を瞬時に全受講者に配信でき、資料の更新があった場合もリアルタイムで最新版を共有できます。
全国から専門講師を招待できる
地理的制約を受けることなく、全国各地から優秀な専門講師を招待することができます。従来の集合研修では、講師の移動費用や時間的制約により、招待できる講師が限定されがちでした。しかし、オンライン形式なら、東京の企業が大阪や福岡の専門家から直接指導を受けることも容易に実現できます。
この柔軟性により、企業は特定分野の第一人者や、実務経験豊富な専門家から質の高い研修を受ける機会を大幅に増やせます。
オンライン研修のデメリット
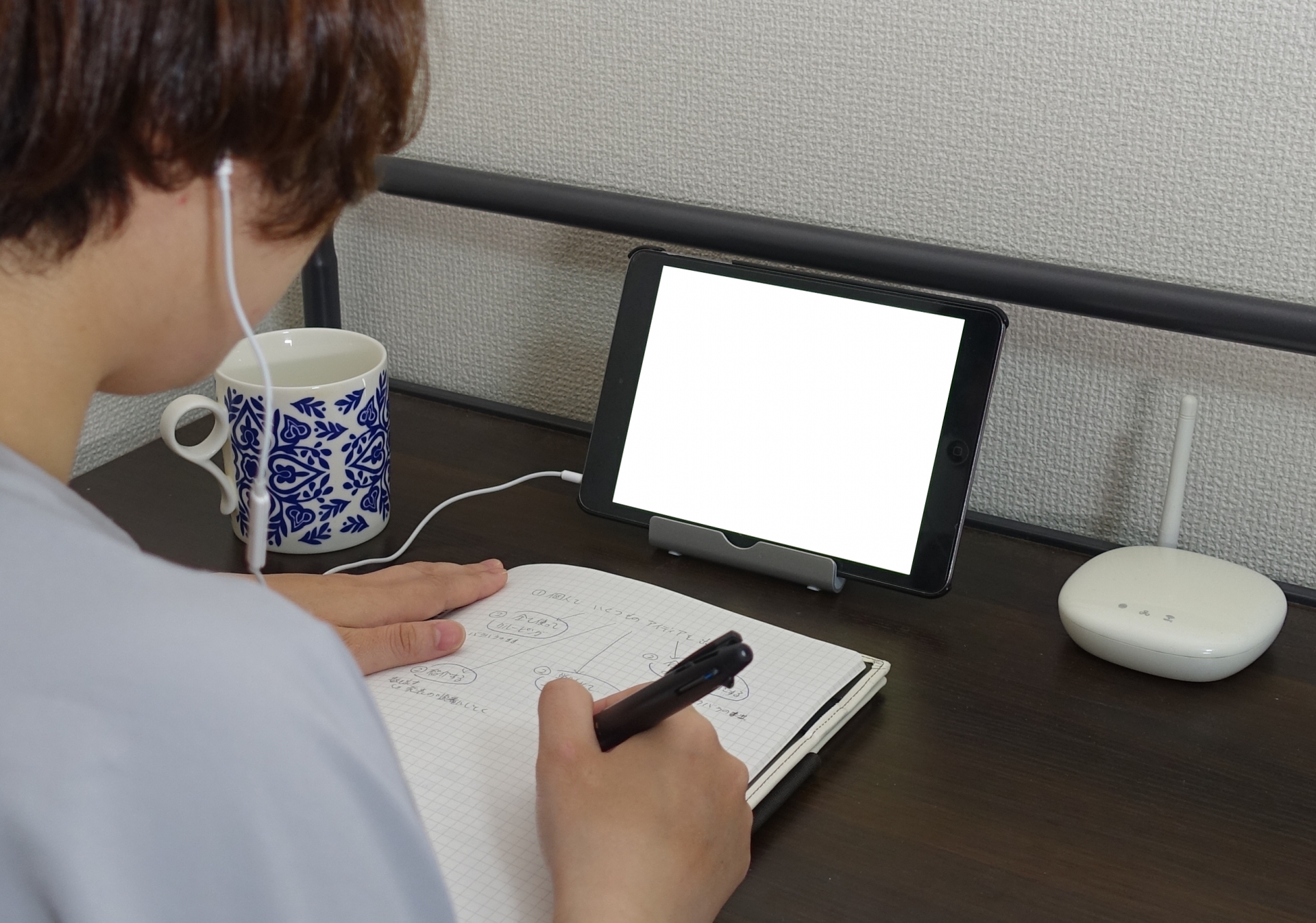 オンライン研修には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。これらの課題を事前に理解し、適切に対策することで、より効果的な研修運営が可能となります。
オンライン研修には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。これらの課題を事前に理解し、適切に対策することで、より効果的な研修運営が可能となります。
ここでは、オンライン研修の主要なデメリットについて詳しく解説します。
実技研修には不向き
実技や実習を伴う研修には、オンライン研修は適切ではありません。特に製造業における機械操作や医療分野での実習、接客サービスでの実践的なトレーニングなどは、画面越しでは十分な指導が行えないからです。実際に手を動かして覚える技術や、身体的な動作を伴うスキルの習得においては、対面での指導が不可欠になります。
このような研修では、オンラインとオフラインを組み合わせたハイブリッド型の研修設計を検討する必要があるでしょう。
ネット環境に左右される
オンライン研修は、安定したインターネット環境が欠かせません。通信速度が遅い、接続が不安定、データ通信量に制限があるといった環境では、研修の品質が著しく低下する可能性があります。特に地方拠点や在宅勤務者の中には、十分なネット環境が整っていない場合があり、音声の途切れや画面の遅延、接続の切断などが発生することがあります。
企業側では事前の環境チェックや代替手段の準備、必要に応じてネット環境の整備支援を行うことが重要です。
非言語コミュニケーションが取りにくい
画面越しでの研修では、対面研修で重要な役割を果たす非言語コミュニケーションが制限されます。表情の細かな変化、身振り手振り、姿勢、視線の動きなど、理解度や関心度を示す重要な情報が十分に伝わりません。講師は受講者の反応を正確に把握することが困難になり、適切なタイミングでの指導やフォローが難しくなることもあります。
この問題を軽減するためには、チャット機能の活用や定期的な確認タイムの設定、カメラの適切な使用などの工夫が必要です。
画面越しでは臨場感に欠ける
オンライン研修では、対面研修特有の臨場感や一体感を再現することが困難です。同じ空間を共有することで生まれる緊張感や集中力、参加者同士の連帯感などが薄れがちになります。
特にチームビルディングや組織文化の浸透を目的とした研修では、この臨場感の欠如が大きな問題となります。画面の向こう側にいる他の参加者との距離感や、研修会場特有の学習環境が失われることで、受講者のモチベーション維持が困難になる場合があります。
オンライン研修の導入手順
 オンライン研修を成功させるためには、計画的に導入手順を踏むことが重要です。ここでは、オンライン研修の導入を7つのステップに分けて詳しく解説します。
オンライン研修を成功させるためには、計画的に導入手順を踏むことが重要です。ここでは、オンライン研修の導入を7つのステップに分けて詳しく解説します。
研修目的と対象者を明確化する
オンライン研修導入の第一歩として、研修の目的と対象者を明確にしましょう。新入社員のビジネスマナー習得、管理職のマネジメントスキル向上、全社的なコンプライアンス教育など、具体的な目標を設定することが必要です。
対象者の年齢層、ITリテラシーレベル、勤務形態、地理的分散状況なども詳細に把握する必要があります。例えば、地方拠点の営業担当者を対象とする場合、移動時間の削減効果や柔軟な受講スケジュールの重要性が高くなります。
適切なプラットフォームを選定する
研修目的と対象者が明確になったら、次に最適なプラットフォームの選定が必要です。安定した通信環境、使いやすいインターフェース、受講者管理機能、セキュリティ対策などを総合的に評価することが重要です。特に、受講者のITリテラシーレベルに合わせて選定することが、重要な要素となります。
また、既存システムとの連携可能性、コスト面、サポート体制なども考慮し、複数のプラットフォームを比較検討した上で最終決定を行いましょう。
中には、トライアル期間があるプラットフォームもあるので、事前に実際の操作感を確認すしておくと良いでしょう。
研修コンテンツを企画・制作する
プラットフォーム選定後は、研修コンテンツの企画・制作に取り組みます。オンライン環境では受講者の集中力維持が課題となるため、30分から1時間程度のコンパクトな構成を心がけ、適度な休憩を挟むスケジュールを組みましょう。
コンテンツ制作では、一方的な講義形式では受講者の集中力が切れてしまう可能性があります。そのため、チャット機能を活用した質疑応答、グループワーク、クイズやアンケートなど、双方向のコミュニケーションを構成に取り入れると効果的です。
受講者の参加意識も高まり、理解度の向上を図ることができます。
受講環境の整備と確認を行う
研修を円滑に実施するため、受講者の環境整備と事前確認を行います。受講者には、安定したインターネット接続、パソコンまたはタブレット、ヘッドセットやマイク、可能であればWebカメラを準備してもらいましょう。事前にテスト接続を実施してもらい、音声や映像の品質、操作方法をチェックしておくと安心です。ITリテラシーが低い受講者に対しては、個別サポートや操作マニュアルの配布を行い、不安を解消すると良いでしょう。
また、研修当日のトラブルに備え、技術サポート窓口の設置や代替手段の準備も欠かせません。受講者が安心して研修に参加できる環境を整えることが大切です。
講師やファシリテーターを選任する
オンライン研修の成功には、適切な講師やファシリテーターの選任が不可欠です。オンライン環境では対面研修とは異なるスキルが求められるため、デジタルツールの操作に慣れており、画面越しでも受講者の関心を引きつけられる人材を選びましょう。 講師には、明瞭な話し方、適度なペース配分、視覚的な資料の効果的な活用などのスキルが求められます。また、チャット機能での質問対応や、技術的なトラブルが発生した際の柔軟な対応力必要です。
テスト運用で問題点を洗い出す
本番前に、テスト運用を実施して問題点を洗い出しましょう。テスト運用では、システムの動作確認、コンテンツの理解しやすさ、進行のスムーズさなどを総合的に検証しましょう。ネットワーク接続の不安定、音声トラブル、操作ミスなど、実際に起こりうる問題への対処法を事前に検証しておくことで、本番での混乱を最小限に抑えられます。
本格運用を開始し効果を測定する
テスト運用で問題へのやい処方を検証したら、いよいよ本格運用を開始します。初回実施時は特に慎重に進行し、受講者の反応や理解度を注意深く観察しながら研修を進めましょう。運用開始後は、継続的な効果測定と改善を行います。受講率、完了率、理解度テストの結果、受講者満足度調査などのデータを定期的に収集・分析し、研修の品質向上に活用しましょう。
得られたデータをもとに、コンテンツの改善、運営方法の最適化、新たな研修プログラムの企画などを継続的に実施していくことで、より効果的なオンライン研修に仕上げていきましょう。
オンライン研修を成功させる運営のコツ
 オンライン研修を成功させるためには、事前の準備から研修後のフォローアップまで、計画的かつ継続的な取り組みが不可欠です。
オンライン研修を成功させるためには、事前の準備から研修後のフォローアップまで、計画的かつ継続的な取り組みが不可欠です。
ここでは、オンライン研修の効果を最大化するための具体的な運営ポイントを詳しく解説していきます。
事前準備とリハーサルを徹底する
オンライン研修の成功は事前準備にかかっているといっても過言ではありません。まず、使用するWeb会議システムやeラーニングプラットフォームの動作確認を行い、講師と受講者の双方が操作に慣れておく必要があります。特に初めてオンライン研修を実施する場合は、本番前に必ずリハーサルを実施しましょう。
技術的な準備として、安定したインターネット環境の確保、適切なマイクやカメラの設定、資料の共有方法などを事前にチェックします。受講者には操作マニュアルを配布し、研修開始前にテクニカルトレーニングを実施することで、当日のトラブルを未然に防げます。
受講者とのコミュニケーションを密にする
オンライン研修では対面研修に比べて受講者の反応が見えにくいため、積極的なコミュニケーションが不可欠です。チャット機能を活用して質問を受け付けたり、定期的に受講者の理解度を確認したりすることで、双方向のやりとりを促進できます。研修中は受講者の名前を呼びかけたり、具体的な質問を投げかけたりして、一人ひとりが参加している実感を持てるよう工夫しましょう。
グループワークを実施する際は、ブレイクアウトルーム機能を使って小グループに分け、活発な議論を促すとより効果的に研修することができます。
技術サポート体制を用意しておく
オンライン研修では技術的なトラブルが発生する可能性があるため、専任のサポートスタッフを用意しておくと良いでしょう。進行補助役(オペレーター)を設けることで、Web会議システムの操作や機材トラブルに迅速に対応できます。 サポート体制には、事前の動作確認支援、研修中のトラブル対応、受講者への操作案内などが含まれます。継続的な改善サイクルを回す
オンライン研修の品質向上には、継続的な改善が不可欠です。各回の研修後には必ず受講者からのフィードバックを収集し、内容や進行方法の見直しを行いましょう。アンケート結果や受講データを分析することで、改善すべき点を明確にできます。 受講者の声を反映させることで、より効果的な研修プログラムにすることが可能です。
オンライン研修はAirzにお任せください
 オンライン研修は、時間や場所を問わず受講できる柔軟性やコスト削減効果から、多くの企業で導入が進んでいます。一方で、実技研修の難しさやネット環境への依存といった課題もあり、成功には計画的な準備と専門的なサポートが欠かせません。
オンライン研修は、時間や場所を問わず受講できる柔軟性やコスト削減効果から、多くの企業で導入が進んでいます。一方で、実技研修の難しさやネット環境への依存といった課題もあり、成功には計画的な準備と専門的なサポートが欠かせません。
Airzは、企業ごとのニーズに合わせたオンライン研修ソリューションを提供し、会場費や交通費などの負担を抑えながら、全国や海外拠点を含む全社員へ均一な研修機会を届けます。企画から運営、効果測定まで一貫して対応し、教育格差の解消とスキル向上をサポートします。
また、ハイブリッドイベント配信の分野で、国際機関や省庁、大手企業を含む1,000回以上の配信実績を持ち、ZoomやTeamsなど主要ツールにも幅広く対応可能です。セミナーや社内研修、学会、国際会議まで、多様なシーンで安心して任せられる体制を整えています。
オンライン研修の導入を検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。