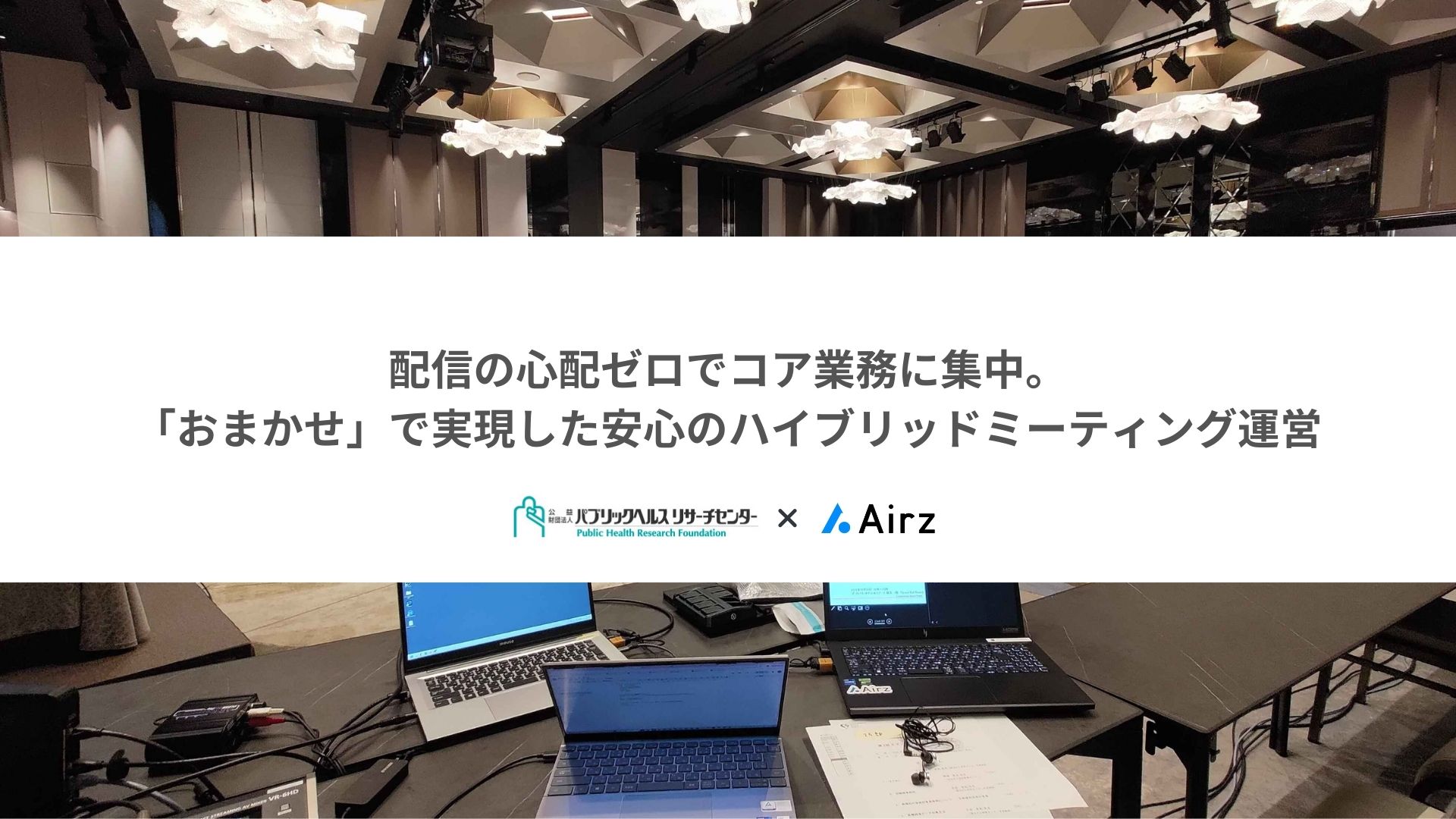オンデマンド配信プラットフォームの選び方とは?失敗しない比較ポイントを専門家が解説!
 更新日
更新日

オンデマンド配信は、好きな時間に好きな場所で動画視聴ができるサービスで、教育やビジネス、エンターテインメントなどの分野で注目されています。
本記事では、オンデマンド配信の基本、ライブ配信との違い、メリット・デメリット、最適なプラットフォームの選び方、トラブル対策について詳しく解説します。
オンデマンド配信の導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
 オンデマンド配信とは、あらかじめ制作した動画をサーバーにアップロードしておき、視聴者が好きなタイミングで視聴できる動画配信方式のことです。
オンデマンド配信とは、あらかじめ制作した動画をサーバーにアップロードしておき、視聴者が好きなタイミングで視聴できる動画配信方式のことです。
ライブ配信とは異なり、リアルタイムでの配信ではなく、事前に録画・編集された動画コンテンツを提供します。
「オンデマンド(On Demand)」は「要求に応じて」という意味で、視聴者の都合に合わせていつでもどこでも動画を再生できるという特徴があります。YouTubeやNetflix、Amazonプライムビデオなどが代表的なサービスとして挙げられるでしょう。
企業では研修動画や商品紹介、セミナーのアーカイブ配信などに活用され、視聴者にとっては時間や場所の制約を受けずに学習や情報収集ができる便利なツールとなっています。
 オンデマンド配信とライブ配信の最大の違いは、動画の配信タイミングにあります。
オンデマンド配信とライブ配信の最大の違いは、動画の配信タイミングにあります。
オンデマンド配信は、事前に制作・編集された動画をサーバーにアップロードし、視聴者が好きな時間に視聴できる配信方式です。一方、ライブ配信はリアルタイムで撮影・配信を行い、視聴者と同じ時間軸で動画が進行します。
オンデマンド配信では視聴者が再生・停止・早送りなどを自由に操作でき、何度でも繰り返し視聴が可能です。対してライブ配信は一度きりの体験となり、視聴者とリアルタイムでコミュニケーションがとれるのが特徴となります。
 オンデマンド配信は、事前に制作した動画コンテンツを視聴者がいつでも自由に視聴できる配信方式です。この配信方法には多くのメリットがあり、企業研修や教育分野、マーケティング活動において広く活用されています。
オンデマンド配信は、事前に制作した動画コンテンツを視聴者がいつでも自由に視聴できる配信方式です。この配信方法には多くのメリットがあり、企業研修や教育分野、マーケティング活動において広く活用されています。
ここからは、具体的にどのようなメリットがあるのかを詳しく見ていきましょう。
理解が困難な箇所では一時停止して考える時間を取ったり、既に理解している部分は早送りしたりと、個々の学習スタイルに応じた調整が可能になります。特に企業研修や教育コンテンツにおいて、この特性は非常に重要です。
従来の集合研修では全員が同じペースで進む必要がありましたが、オンデマンド配信なら受講者一人ひとりが最適な速度で学習できます。また、集中力が続かない場合は適度に休憩を挟みながら視聴を継続でき、学習効果の向上が期待できるでしょう。
研修や教育分野では、この反復学習効果が特に重要視されています。
複雑な業務プロセスや技術的な内容は、一回の説明だけでは完全に習得することが困難です。しかし、オンデマンド配信なら必要に応じて該当部分を何度も確認でき、確実な知識定着を図れます。
また、時間が経過してから復習したい場合も、いつでもアクセスして記憶を呼び起こすことが可能です。このように学習の質を高められる点が、教育効果を重視する組織にとって大きなメリットとなっています。
特にリモートワークが普及した現在、時間や場所を選ばず柔軟に視聴可能できるという点は 、企業にとって非常に価値があります。全国各地に散らばる社員や、異なるタイムゾーンで働くメンバーに対しても、統一された研修コンテンツを提供できるからです。
また、育児や介護などの事情で決まった時間に参加できない人々も、自分の都合に合わせて学習を進められます。
さらに、質の高いコンテンツを一度制作すれば、多くの視聴者に対して同じクオリティの情報を提供できます。講師の体調や気分に左右されることなく、常に安定した品質を保てる点も魅力です。
編集により、情報の整理や構成の最適化も可能になります。論理的な流れに沿って内容を再構成し、視聴者の理解を促進する工夫を凝らせるでしょう。
また、音声の調整や画質の向上、字幕の追加なども行えるため、アクセシビリティの向上にも貢献します。さらに、チャプター機能を活用すれば、視聴者が必要な情報に素早くアクセスできる環境も整備できます。
このように技術的な品質向上により、視聴者の満足度を高められる点が大きな魅力です。
企業にとっては、新入社員研修や基本的な業務マニュアルとして継続的に使用できる点が大きなメリットです。
また、コンテンツライブラリとして蓄積していけば、組織の知識資産として機能し、ナレッジマネジメントの向上にも寄与します。
 オンデマンド配信は便利な配信方式ですが、いくつかのデメリットも存在します。特にリアルタイム性や視聴者とのコミュニケーション、制作面での課題が挙げられるでしょう。
オンデマンド配信は便利な配信方式ですが、いくつかのデメリットも存在します。特にリアルタイム性や視聴者とのコミュニケーション、制作面での課題が挙げられるでしょう。
これらの課題を理解しておくことで、より効果的な配信戦略を立てることができます。
ライブ配信であれば、コメント機能を使って視聴者の疑問にその場で答えられますが、事前収録された動画では双方向のやり取りが困難です。この制約により、視聴者が抱いた疑問や関心事を即座に解決できず、満足度の低下につながる可能性があります。
特に教育コンテンツや商品説明動画では、視聴者の理解度を確認しながら進行できないため、一方的な情報伝達になりがちです。
対策として、コメント欄やお問い合わせフォームを設置し、後日回答する仕組みを構築する企業も増えています。また、よくある質問を想定したFAQ動画を別途制作することで、ある程度の課題解決は可能でしょう。
視聴者は「今この瞬間に配信者と同じ時間を共有している」という特別感を得られないため、エンゲージメントが低下する傾向があります。特にイベントやセミナーのような場合、参加者同士の交流やリアクションが重要な要素となりますが、オンデマンド配信ではこうした体験を提供できません。視聴者は孤独感を感じやすく、途中で離脱してしまう可能性も高くなります。
この課題に対しては、動画内で視聴者に問いかけるような演出を取り入れたり、コミュニティ機能を併用したりすることで、ある程度の参加感を創出できます。また、定期的にライブ配信と組み合わせることで、両方の良さを活用する戦略も効果的です。
例えば、株価情報や天気予報、ニュース解説などの分野では、数時間の遅れが致命的になる場合もあるでしょう。また、新商品の発表や法改正などの重要な変更点についても、タイムリーに伝えることが困難です。
この問題を解決するには、定期的な動画の更新スケジュールを設定したり、緊急性の高い情報については別途ライブ配信で補完したりする必要があります。また、動画制作フローを効率化し、制作期間を短縮する取り組みも重要になってきます。
特に企業が本格的なマーケティング動画を制作する場合、プロの制作会社に依頼することも多く、1本あたり数十万円から数百万円の費用がかかることも珍しくありません。また、内製する場合でも、撮影機材の準備や編集ソフトの習得、人件費などを考慮すると、決して安価ではありません。
しかし、一度制作した動画は長期間にわたって活用できるため、費用対効果を長期的な視点で評価することが重要です。また、制作工程の標準化や効率化を図ることで、コストを抑制しながら品質を維持することも可能になります。
 近年、教育研修やウェビナー、株主総会といったさまざまなビジネスシーンでオンデマンド配信の導入が進んでいます。ここでは、オンデマンド配信を活用して成果を上げている3社の事例を紹介します。
近年、教育研修やウェビナー、株主総会といったさまざまなビジネスシーンでオンデマンド配信の導入が進んでいます。ここでは、オンデマンド配信を活用して成果を上げている3社の事例を紹介します。
約3分のアニメーション動画をJ-Stream Equipmediaを通じて配信し、字幕切り替えで7言語に対応しました。これにより、パートや外国人スタッフを含む誰もが「いつでも・誰でも・同じ質」で学べる体制を実現しています。
動画内容は手洗い・身だしなみ・体調管理・洗剤の安全な扱いなど60本以上で、食品衛生や労災対策を網羅しました。オンデマンド配信の強みを活かし、教育の属人化を解消しつつ、短期間で人員が入れ替わる現場でも安定した教育を提供可能にしたといいます。
三井住友ファイナンス&リース株式会社(SMFL)は、非対面営業活動の一環として2021年よりウェビナーを実施しています。SDGs経営をテーマに顧客企業が登壇するディスカッションウェビナーをオンデマンド配信形式で開催しました。
オンデマンド配信は、顧客が都合の良い時間に視聴でき、登壇者にとっても撮り直しが可能で負担が少ない点が好評です。スタジオ収録・編集をJストリームが担当し、30〜40分の集中しやすい動画に仕上げ、テロップや資料挿入で飽きさせない工夫も実施しました。
結果、申込約800件に対して再生数780回、アンケート回答400件と高いエンゲージメントを獲得し、新たな顧客接点の創出や認知向上にもつながりました。
当初は外注先からの動画データ納品に時間がかかり、公開の遅れや内容確認不足といった課題が発生しました。そこで翌年は、総会終了後すぐに動画データを受け取れる体制を整備しました。
会場下見や撮影テスト、編集調整まで手厚いサポートを受けられ、IRサイトへの早期公開が実現したといいます。高画質・高音質で納得の仕上がりとなり、総会本来の業務に集中できた点も大きな効果でした。
 オンデマンド配信プラットフォームを選ぶ際は、自社のニーズと予算に最適なサービスを見極めることが重要です。視聴者数や配信する動画の種類、求める機能によって適切なプラットフォームは大きく異なります。
オンデマンド配信プラットフォームを選ぶ際は、自社のニーズと予算に最適なサービスを見極めることが重要です。視聴者数や配信する動画の種類、求める機能によって適切なプラットフォームは大きく異なります。
以下では、プラットフォーム選定時に重視すべき6つのポイントを詳しく解説していきます。
同時接続数の上限や月間視聴時間の制限を事前に把握しておかないと、いざという時に配信が止まってしまう可能性があります。小規模な社内研修であれば数十人程度の同時接続で十分ですが、大規模なウェビナーや商品発表会では数千人規模の対応が必要になるでしょう。
また、視聴者が集中する時間帯での負荷テストの実績があるかも重要な判断材料となります。さらに、将来的な事業拡大を見据えて拡張性も考慮しましょう。
初期は小規模でスタートしても、後からプランをアップグレードできるサービスを選んでおけば、成長に合わせて柔軟に対応できます。
配信速度については、CDN(コンテンツ配信ネットワーク)の充実度が大きく影響します。国内外に配信拠点を持つプラットフォームであれば、どの地域からアクセスしても快適な視聴体験を提供できるでしょう。
初期費用だけでなく、ランニングコストも含めた総合的な費用対効果を検討しましょう。安価なプランでも機能制限が厳しく、結果的に追加オプション料金がかさむケースもあります。
また、契約期間の縛りや解約条件も事前に確認が必要です。事業の変化に応じて柔軟にプラン変更できるサービスを選んでおけば、無駄なコストを抑制できるでしょう。
特に企業研修や商品紹介動画では、視聴完了率や特定チャプターでの滞在時間など、詳細な分析データが今後のコンテンツ改善に活用できます。リアルタイムでのデータ確認機能があれば、配信中の問題にも迅速に対応可能です。
データのエクスポート機能やAPI連携の対応状況も確認しておくと、他のマーケティングツールとの連携がスムーズになり、より包括的な分析が行えるでしょう。
専用アプリの提供があるかも重要なポイントです。アプリ版では、オフライン視聴機能やプッシュ通知機能など、ブラウザ版にはない便利な機能が利用できる場合があります。
さらに、視聴途中でデバイスを切り替えても続きから再生できる機能があると、ユーザビリティが大幅に向上します。通勤中にスマートフォンで視聴を始め、自宅でPCから続きを見るといった使い方にも対応できるでしょう。
技術的な問題だけでなく、配信設定や動画のアップロード方法など、運用面でのサポートも充実しているかを確認しておきましょう。初回導入時の設定支援や定期的な運用コンサルティングを提供するサービスもあります。
また、プラットフォームのアップデート頻度やセキュリティ対策の実施状況も重要な判断材料です。常に最新の技術動向に対応し、安全な配信環境を維持できるプロバイダーを選ぶことで、長期的な安心感を得られるでしょう。
関連記事:動画配信システムのおすすめ9選!選び方のポイントも解説 オンデマンド配信を成功させるには、安定した配信環境と高品質な映像、そしてスムーズな運営を支えてくれるパートナーが欠かせません。数ある配信支援サービスの中でも、信頼できる選択肢の一つがAirzです。
オンデマンド配信を成功させるには、安定した配信環境と高品質な映像、そしてスムーズな運営を支えてくれるパートナーが欠かせません。数ある配信支援サービスの中でも、信頼できる選択肢の一つがAirzです。
Airzは、企業のオンデマンド配信ニーズに特化した包括的なサポートで、これまで国際機関や省庁、上場企業を含む1,000回以上の配信を支援してきました。
セミナーや研修、学会、決算説明会、国際会議など多様なシーンで培ったノウハウを活かし、配信ツール選定から会場下見、当日の運営、アーカイブ納品まで一貫して対応します。
また、高性能なカメラやミキサー、スイッチャーなどの機材を自社で保有し、ハイブリッドイベントにも柔軟に対応。チャプター機能や倍速再生、字幕表示など視聴体験を高める機能に加え、詳細な視聴ログの取得・分析で配信効果も可視化できます。
さらに、予備機材や回線手配など、トラブルを防ぐための備えも万全です。オンデマンド配信を検討している方は、まずはAirzに相談してみてください。
本記事では、オンデマンド配信の基本、ライブ配信との違い、メリット・デメリット、最適なプラットフォームの選び方、トラブル対策について詳しく解説します。
オンデマンド配信の導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
Table of Contents
オンデマンド配信とは
 オンデマンド配信とは、あらかじめ制作した動画をサーバーにアップロードしておき、視聴者が好きなタイミングで視聴できる動画配信方式のことです。
オンデマンド配信とは、あらかじめ制作した動画をサーバーにアップロードしておき、視聴者が好きなタイミングで視聴できる動画配信方式のことです。
ライブ配信とは異なり、リアルタイムでの配信ではなく、事前に録画・編集された動画コンテンツを提供します。
「オンデマンド(On Demand)」は「要求に応じて」という意味で、視聴者の都合に合わせていつでもどこでも動画を再生できるという特徴があります。YouTubeやNetflix、Amazonプライムビデオなどが代表的なサービスとして挙げられるでしょう。
企業では研修動画や商品紹介、セミナーのアーカイブ配信などに活用され、視聴者にとっては時間や場所の制約を受けずに学習や情報収集ができる便利なツールとなっています。
オンデマンド配信とライブ配信の違い
 オンデマンド配信とライブ配信の最大の違いは、動画の配信タイミングにあります。
オンデマンド配信とライブ配信の最大の違いは、動画の配信タイミングにあります。
オンデマンド配信は、事前に制作・編集された動画をサーバーにアップロードし、視聴者が好きな時間に視聴できる配信方式です。一方、ライブ配信はリアルタイムで撮影・配信を行い、視聴者と同じ時間軸で動画が進行します。
オンデマンド配信では視聴者が再生・停止・早送りなどを自由に操作でき、何度でも繰り返し視聴が可能です。対してライブ配信は一度きりの体験となり、視聴者とリアルタイムでコミュニケーションがとれるのが特徴となります。
オンデマンド配信のメリット
 オンデマンド配信は、事前に制作した動画コンテンツを視聴者がいつでも自由に視聴できる配信方式です。この配信方法には多くのメリットがあり、企業研修や教育分野、マーケティング活動において広く活用されています。
オンデマンド配信は、事前に制作した動画コンテンツを視聴者がいつでも自由に視聴できる配信方式です。この配信方法には多くのメリットがあり、企業研修や教育分野、マーケティング活動において広く活用されています。
ここからは、具体的にどのようなメリットがあるのかを詳しく見ていきましょう。
視聴者が自分のペースで学習できる
オンデマンド配信最大の魅力は、視聴者が自分の都合に合わせて学習を進められることです。理解が困難な箇所では一時停止して考える時間を取ったり、既に理解している部分は早送りしたりと、個々の学習スタイルに応じた調整が可能になります。特に企業研修や教育コンテンツにおいて、この特性は非常に重要です。
従来の集合研修では全員が同じペースで進む必要がありましたが、オンデマンド配信なら受講者一人ひとりが最適な速度で学習できます。また、集中力が続かない場合は適度に休憩を挟みながら視聴を継続でき、学習効果の向上が期待できるでしょう。
繰り返し視聴により理解度が向上する
オンデマンド配信では、同じコンテンツを何度でも繰り返し視聴できるため、理解度の大幅な向上が見込めます。一度の視聴では理解しきれなかった内容も、複数回視聴することで段階的に理解を深められるからです。研修や教育分野では、この反復学習効果が特に重要視されています。
複雑な業務プロセスや技術的な内容は、一回の説明だけでは完全に習得することが困難です。しかし、オンデマンド配信なら必要に応じて該当部分を何度も確認でき、確実な知識定着を図れます。
また、時間が経過してから復習したい場合も、いつでもアクセスして記憶を呼び起こすことが可能です。このように学習の質を高められる点が、教育効果を重視する組織にとって大きなメリットとなっています。
時間や場所を選ばず柔軟に視聴可能
オンデマンド配信は、視聴者の時間的・地理的制約を大幅に軽減します。インターネット環境があれば、自宅でも移動中でも、好きな時間に好きな場所でコンテンツを視聴できるためです。特にリモートワークが普及した現在、時間や場所を選ばず柔軟に視聴可能できるという点は 、企業にとって非常に価値があります。全国各地に散らばる社員や、異なるタイムゾーンで働くメンバーに対しても、統一された研修コンテンツを提供できるからです。
また、育児や介護などの事情で決まった時間に参加できない人々も、自分の都合に合わせて学習を進められます。
配信者の負担が軽減され効率的
従来のライブ形式では、同じ内容でも毎回講師が時間を割く必要がありました。しかしオンデマンド配信なら、一度コンテンツを制作すれば何度でも繰り返し活用できるため、講師や研修担当者の時間的負担が大幅に軽減されます。さらに、質の高いコンテンツを一度制作すれば、多くの視聴者に対して同じクオリティの情報を提供できます。講師の体調や気分に左右されることなく、常に安定した品質を保てる点も魅力です。
高品質な編集済みコンテンツを提供できる
オンデマンド配信ではライブ配信とは異なり、撮影後に不要な部分をカットしたり、重要なポイントにテロップを追加したりと、視聴しやすい形に調整できます。編集により、情報の整理や構成の最適化も可能になります。論理的な流れに沿って内容を再構成し、視聴者の理解を促進する工夫を凝らせるでしょう。
また、音声の調整や画質の向上、字幕の追加なども行えるため、アクセシビリティの向上にも貢献します。さらに、チャプター機能を活用すれば、視聴者が必要な情報に素早くアクセスできる環境も整備できます。
このように技術的な品質向上により、視聴者の満足度を高められる点が大きな魅力です。
長期的な資産として活用できる
オンデマンド配信コンテンツは、制作後も長期間にわたって価値を提供し続ける貴重な資産となります。特に基礎的な知識や変わらない原理原則を扱ったコンテンツは、長期間の活用が期待できるでしょう。企業にとっては、新入社員研修や基本的な業務マニュアルとして継続的に使用できる点が大きなメリットです。
また、コンテンツライブラリとして蓄積していけば、組織の知識資産として機能し、ナレッジマネジメントの向上にも寄与します。
オンデマンド配信のデメリット
 オンデマンド配信は便利な配信方式ですが、いくつかのデメリットも存在します。特にリアルタイム性や視聴者とのコミュニケーション、制作面での課題が挙げられるでしょう。
オンデマンド配信は便利な配信方式ですが、いくつかのデメリットも存在します。特にリアルタイム性や視聴者とのコミュニケーション、制作面での課題が挙げられるでしょう。
これらの課題を理解しておくことで、より効果的な配信戦略を立てることができます。
リアルタイムな質疑応答ができない
オンデマンド配信では、視聴者からの質問に対してリアルタイムで回答することができません。ライブ配信であれば、コメント機能を使って視聴者の疑問にその場で答えられますが、事前収録された動画では双方向のやり取りが困難です。この制約により、視聴者が抱いた疑問や関心事を即座に解決できず、満足度の低下につながる可能性があります。
特に教育コンテンツや商品説明動画では、視聴者の理解度を確認しながら進行できないため、一方的な情報伝達になりがちです。
対策として、コメント欄やお問い合わせフォームを設置し、後日回答する仕組みを構築する企業も増えています。また、よくある質問を想定したFAQ動画を別途制作することで、ある程度の課題解決は可能でしょう。
視聴者との一体感や臨場感に欠ける
録画された動画では、ライブ配信特有の一体感や臨場感を演出することが困難です。視聴者は「今この瞬間に配信者と同じ時間を共有している」という特別感を得られないため、エンゲージメントが低下する傾向があります。特にイベントやセミナーのような場合、参加者同士の交流やリアクションが重要な要素となりますが、オンデマンド配信ではこうした体験を提供できません。視聴者は孤独感を感じやすく、途中で離脱してしまう可能性も高くなります。
この課題に対しては、動画内で視聴者に問いかけるような演出を取り入れたり、コミュニティ機能を併用したりすることで、ある程度の参加感を創出できます。また、定期的にライブ配信と組み合わせることで、両方の良さを活用する戦略も効果的です。
最新情報の反映に時間がかかる
オンデマンド配信では、動画制作から公開まで一定の時間が必要なため、最新の情報やトレンドを即座に反映することができません。特に変化の激しい業界や時事性の高いコンテンツでは、情報の鮮度が重要な要素となるため、大きなデメリットとなり得ます。例えば、株価情報や天気予報、ニュース解説などの分野では、数時間の遅れが致命的になる場合もあるでしょう。また、新商品の発表や法改正などの重要な変更点についても、タイムリーに伝えることが困難です。
この問題を解決するには、定期的な動画の更新スケジュールを設定したり、緊急性の高い情報については別途ライブ配信で補完したりする必要があります。また、動画制作フローを効率化し、制作期間を短縮する取り組みも重要になってきます。
制作に時間とコストがかかる
質の高いオンデマンド配信を制作するには、企画から撮影、編集まで多くの工程が必要で、相応の時間とコストが発生します。ライブ配信であれば最低限の機材で始められますが、録画動画では編集作業や品質管理により多くのリソースを割く必要があるでしょう。特に企業が本格的なマーケティング動画を制作する場合、プロの制作会社に依頼することも多く、1本あたり数十万円から数百万円の費用がかかることも珍しくありません。また、内製する場合でも、撮影機材の準備や編集ソフトの習得、人件費などを考慮すると、決して安価ではありません。
しかし、一度制作した動画は長期間にわたって活用できるため、費用対効果を長期的な視点で評価することが重要です。また、制作工程の標準化や効率化を図ることで、コストを抑制しながら品質を維持することも可能になります。
オンデマンド配信の活用事例
 近年、教育研修やウェビナー、株主総会といったさまざまなビジネスシーンでオンデマンド配信の導入が進んでいます。ここでは、オンデマンド配信を活用して成果を上げている3社の事例を紹介します。
近年、教育研修やウェビナー、株主総会といったさまざまなビジネスシーンでオンデマンド配信の導入が進んでいます。ここでは、オンデマンド配信を活用して成果を上げている3社の事例を紹介します。
オンデマンド配信により教育の属人化を解消|サラヤ株式会社
サラヤ株式会社は、現場での衛生教育を効率化するため、オンデマンド配信による教育動画サービスを導入しました。約3分のアニメーション動画をJ-Stream Equipmediaを通じて配信し、字幕切り替えで7言語に対応しました。これにより、パートや外国人スタッフを含む誰もが「いつでも・誰でも・同じ質」で学べる体制を実現しています。
動画内容は手洗い・身だしなみ・体調管理・洗剤の安全な扱いなど60本以上で、食品衛生や労災対策を網羅しました。オンデマンド配信の強みを活かし、教育の属人化を解消しつつ、短期間で人員が入れ替わる現場でも安定した教育を提供可能にしたといいます。
オンデマンド配信で新たな顧客接点と認知拡大に貢献|三井住友ファイナンス&リース株式会社
三井住友ファイナンス&リース株式会社(SMFL)は、非対面営業活動の一環として2021年よりウェビナーを実施しています。SDGs経営をテーマに顧客企業が登壇するディスカッションウェビナーをオンデマンド配信形式で開催しました。
オンデマンド配信は、顧客が都合の良い時間に視聴でき、登壇者にとっても撮り直しが可能で負担が少ない点が好評です。スタジオ収録・編集をJストリームが担当し、30〜40分の集中しやすい動画に仕上げ、テロップや資料挿入で飽きさせない工夫も実施しました。
結果、申込約800件に対して再生数780回、アンケート回答400件と高いエンゲージメントを獲得し、新たな顧客接点の創出や認知向上にもつながりました。
株主総会のオンデマンド配信をスピーディに実現|日総工産株式会社
日総工産株式会社は、株主との接点拡大を目的に2022年から株主総会のオンデマンド配信を導入しています。来場が難しい株主にも総会内容を届け、自社理解を深めてもらう狙いでした。当初は外注先からの動画データ納品に時間がかかり、公開の遅れや内容確認不足といった課題が発生しました。そこで翌年は、総会終了後すぐに動画データを受け取れる体制を整備しました。
会場下見や撮影テスト、編集調整まで手厚いサポートを受けられ、IRサイトへの早期公開が実現したといいます。高画質・高音質で納得の仕上がりとなり、総会本来の業務に集中できた点も大きな効果でした。
オンデマンド配信プラットフォームの選び方
 オンデマンド配信プラットフォームを選ぶ際は、自社のニーズと予算に最適なサービスを見極めることが重要です。視聴者数や配信する動画の種類、求める機能によって適切なプラットフォームは大きく異なります。
オンデマンド配信プラットフォームを選ぶ際は、自社のニーズと予算に最適なサービスを見極めることが重要です。視聴者数や配信する動画の種類、求める機能によって適切なプラットフォームは大きく異なります。
以下では、プラットフォーム選定時に重視すべき6つのポイントを詳しく解説していきます。
想定視聴者数に対応できる容量を確認
プラットフォーム選びで最初に確認すべきは、想定する視聴者数に対応できる配信容量です。同時接続数の上限や月間視聴時間の制限を事前に把握しておかないと、いざという時に配信が止まってしまう可能性があります。小規模な社内研修であれば数十人程度の同時接続で十分ですが、大規模なウェビナーや商品発表会では数千人規模の対応が必要になるでしょう。
また、視聴者が集中する時間帯での負荷テストの実績があるかも重要な判断材料となります。さらに、将来的な事業拡大を見据えて拡張性も考慮しましょう。
初期は小規模でスタートしても、後からプランをアップグレードできるサービスを選んでおけば、成長に合わせて柔軟に対応できます。
動画品質と配信速度の安定性を評価
視聴者満足度を左右する動画品質と配信速度の安定性は、プラットフォーム選定の重要な要素です。4K対応やフルHD画質での配信が可能かどうか、また視聴環境に応じた自動画質調整機能があるかを確認しましょう。配信速度については、CDN(コンテンツ配信ネットワーク)の充実度が大きく影響します。国内外に配信拠点を持つプラットフォームであれば、どの地域からアクセスしても快適な視聴体験を提供できるでしょう。
料金体系とコストパフォーマンスを比較
オンデマンド配信プラットフォームの料金体系は多様で、月額固定制、従量課金制、視聴時間課金制など様々な形態があります。自社の配信頻度や視聴者数の変動パターンを分析し、最もコストパフォーマンスの良いプランを選択することが重要です。初期費用だけでなく、ランニングコストも含めた総合的な費用対効果を検討しましょう。安価なプランでも機能制限が厳しく、結果的に追加オプション料金がかさむケースもあります。
また、契約期間の縛りや解約条件も事前に確認が必要です。事業の変化に応じて柔軟にプラン変更できるサービスを選んでおけば、無駄なコストを抑制できるでしょう。
分析機能と視聴データの詳細度
効果的なオンデマンド配信を実現するには、詳細な視聴データの分析が欠かせません。視聴者数や視聴時間だけでなく、どの部分で離脱が多いか、どのデバイスからのアクセスが多いかなど、具体的なデータを取得できるプラットフォームを選びましょう。特に企業研修や商品紹介動画では、視聴完了率や特定チャプターでの滞在時間など、詳細な分析データが今後のコンテンツ改善に活用できます。リアルタイムでのデータ確認機能があれば、配信中の問題にも迅速に対応可能です。
データのエクスポート機能やAPI連携の対応状況も確認しておくと、他のマーケティングツールとの連携がスムーズになり、より包括的な分析が行えるでしょう。
モバイル対応とマルチデバイス再生
現代の視聴者はスマートフォンやタブレットでの動画視聴が当たり前になっているため、モバイル対応の充実度は必須の確認項目です。レスポンシブデザインに対応し、どのデバイスからでも快適に視聴できるプラットフォームを選択しましょう。専用アプリの提供があるかも重要なポイントです。アプリ版では、オフライン視聴機能やプッシュ通知機能など、ブラウザ版にはない便利な機能が利用できる場合があります。
さらに、視聴途中でデバイスを切り替えても続きから再生できる機能があると、ユーザビリティが大幅に向上します。通勤中にスマートフォンで視聴を始め、自宅でPCから続きを見るといった使い方にも対応できるでしょう。
サポート体制と技術的対応力
オンデマンド配信では技術的なトラブルが発生した際の迅速な対応が重要になります。そのため、プラットフォーム提供会社のサポート体制を詳しく確認しましょう。24時間365日のサポートがあるか、日本語での対応が可能かなど、自社の運用体制に合ったサポートレベルを選択することが大切です。技術的な問題だけでなく、配信設定や動画のアップロード方法など、運用面でのサポートも充実しているかを確認しておきましょう。初回導入時の設定支援や定期的な運用コンサルティングを提供するサービスもあります。
また、プラットフォームのアップデート頻度やセキュリティ対策の実施状況も重要な判断材料です。常に最新の技術動向に対応し、安全な配信環境を維持できるプロバイダーを選ぶことで、長期的な安心感を得られるでしょう。
関連記事:動画配信システムのおすすめ9選!選び方のポイントも解説
オンデマンド配信にはAirzがおすすめ
 オンデマンド配信を成功させるには、安定した配信環境と高品質な映像、そしてスムーズな運営を支えてくれるパートナーが欠かせません。数ある配信支援サービスの中でも、信頼できる選択肢の一つがAirzです。
オンデマンド配信を成功させるには、安定した配信環境と高品質な映像、そしてスムーズな運営を支えてくれるパートナーが欠かせません。数ある配信支援サービスの中でも、信頼できる選択肢の一つがAirzです。
Airzは、企業のオンデマンド配信ニーズに特化した包括的なサポートで、これまで国際機関や省庁、上場企業を含む1,000回以上の配信を支援してきました。
セミナーや研修、学会、決算説明会、国際会議など多様なシーンで培ったノウハウを活かし、配信ツール選定から会場下見、当日の運営、アーカイブ納品まで一貫して対応します。
また、高性能なカメラやミキサー、スイッチャーなどの機材を自社で保有し、ハイブリッドイベントにも柔軟に対応。チャプター機能や倍速再生、字幕表示など視聴体験を高める機能に加え、詳細な視聴ログの取得・分析で配信効果も可視化できます。
さらに、予備機材や回線手配など、トラブルを防ぐための備えも万全です。オンデマンド配信を検討している方は、まずはAirzに相談してみてください。