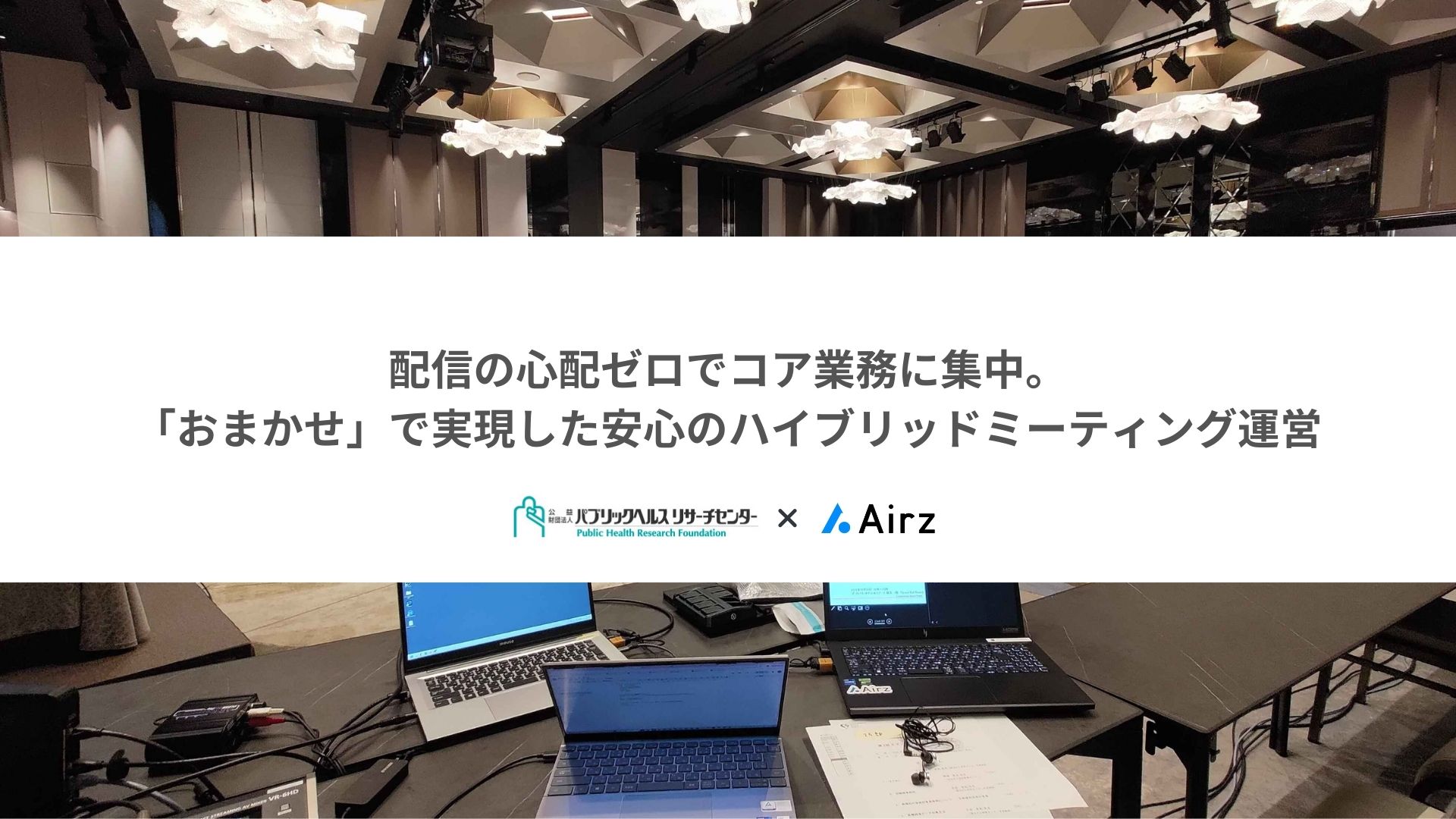【教育現場向け】ハイフレックス授業の始め方と注意点|ハイブリッド授業・ブレンド型との違いも解説!
 更新日
更新日

ハイフレックス授業は、対面とオンラインを同時に実施し、学習者が自由に参加方法を選べる新しい授業形式として注目されています。
本記事では、ハイフレックス授業の特徴や、従来のハイブリッド授業・ブレンド型授業との違い、導入手順やトラブル対応策までを詳しく解説します。
柔軟な学びの環境を実現したい教育機関や担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
 ハイフレックス授業とは、Hybrid-Flexibleの略称で、同じ授業内容を対面とオンラインで同時に実施し、学習者が自由に参加方法を選択できる新しい授業形式です。新型コロナウイルス感染症の拡大をきっかけに急速に普及しました。
ハイフレックス授業とは、Hybrid-Flexibleの略称で、同じ授業内容を対面とオンラインで同時に実施し、学習者が自由に参加方法を選択できる新しい授業形式です。新型コロナウイルス感染症の拡大をきっかけに急速に普及しました。
教員は教室で授業を行いながら、ZoomなどのWeb会議システムを使って遠隔地の学生にもリアルタイムで配信します。
従来のハイブリッド授業とは異なり、学習者一人ひとりが毎回の授業で参加スタイルを自由に決められる点が最大の特徴といえるでしょう。
教員は教室のスクリーンにオンライン参加者の画面を映し出すことで、双方の学生が互いの存在を認識できるよう工夫することができます。この形式により、感染症対策や交通事情、体調不良などの理由で教室に来られない学生も、授業に参加し続けることが可能になりました。
また、遠方に住む学生や社会人学習者にとっても、通学時間を削減しながら質の高い教育を受けられるメリットがあります。
今日は教室で対面参加、明日はオンライン参加といったように、その時の状況や都合に応じて柔軟に決められます。従来の固定的な授業形式とは大きく異なり、学習者のライフスタイルや学習環境に合わせた個別対応が可能になっています。この自由度の高さにより、学習継続率の向上が期待されています。
体調不良や家庭の事情で教室に来られない日でも、オンラインで参加することで学習機会を失わずに済みます。また、集中しやすい環境を自分で選択できるため、学習効果の向上も報告されています。
教員は教室の学生からの質問を受けると同時に、オンライン参加者からのチャットや音声による質問にも対応できます。
また、グループワークや討論の際には、対面とオンラインの学生を混合したチームを編成することも可能です。
 ハイフレックス授業とハイブリッド授業は、どちらも対面とオンラインを組み合わせた授業形態ですが、学習者の選択権や実施方法に大きな違いがあります。ここでは、両者の具体的な違いについて詳しく解説します。
ハイフレックス授業とハイブリッド授業は、どちらも対面とオンラインを組み合わせた授業形態ですが、学習者の選択権や実施方法に大きな違いがあります。ここでは、両者の具体的な違いについて詳しく解説します。
例えば、体調不良や交通事情で教室に来られない日はオンラインで参加し、グループワークがある日は対面で参加するといった柔軟な選択が可能になります。
一方、従来のハイブリッド授業では、学期開始時や単元ごとに参加形式が固定されることが多く、学習者の日々の状況変化に対応しきれない場合がありました。ハイフレックス授業はこうした課題を解決する革新的な授業形態といえるでしょう。
この方式では、対面授業とオンライン授業が別々に設計されることもあり、必ずしも同じ内容や体験を提供するとは限りません。また、一度決められた参加形式を途中で変更することは困難で、学習者の状況変化に柔軟に対応できないという課題があります。
さらに、対面とオンラインで異なる教材や課題が用意される場合もあり、学習者間で学習内容に差が生じる可能性もあります。これに対してハイフレックス授業は、全ての学習者が同等の学習機会を得られるよう設計されており、より公平で柔軟な学習環境を実現しているのです。
 ハイフレックス授業とブレンド型授業は、その運用方法に大きな違いがあります。ここでは、両者の具体的な違いについて詳しく解説していきます。
ハイフレックス授業とブレンド型授業は、その運用方法に大きな違いがあります。ここでは、両者の具体的な違いについて詳しく解説していきます。
教員は決められた時間に教室で授業を行い、その様子をリアルタイムでオンライン受講者にも配信する仕組みです。学習者は授業開始時刻までに参加方法を選択し、指定された時間に受講する必要があります。
対照的にブレンド型授業は、対面授業の時間は固定されているものの、オンライン学習部分については録画視聴や課題提出など、学習者のペースに合わせて進められる場合が多くなっています。
教員は教室にいる学生とオンライン参加の学生に対して、同じタイミングで同じ内容を提供し、質疑応答や議論も同時進行で行われます。そのため、全受講者が同じペースで学習を進めることになり、コンテンツの配信タイミングに差は生まれません。
一方、ブレンド型授業では対面授業とオンライン学習のコンテンツが段階的に配信されることが一般的です。例えば、対面授業で基礎概念を学んだ後、関連する動画教材や追加資料がオンラインで提供される流れになります。
対面参加者は授業前後の雑談や対面でのグループワークを通じて自然なコミュニケーションが取りやすい一方、オンライン参加者はチャット機能や画面越しでのやり取りが中心となる傾向があります。そのため、教員は双方の参加者が等しく交流できるよう、場づくりや進行方法に配慮する必要があります。
ブレンド型授業では、対面授業の機会に全員が同じ空間で学ぶため、直接的な交流が促進されます。また、オンライン学習期間中にも掲示板やグループチャットなどのツールを活用し、意見交換を継続することで学習コミュニティの維持が可能です。
ただし、対面期間とオンライン期間の温度差をなくすためには、オンライン時にも積極的な交流の仕組みを設けることが求められます。
 ハイフレックス授業の導入には、技術環境の整備から学習者サポート、効果検証まで段階的なアプローチが必要です。ここでは、各段階で押さえるべきポイントを詳しく解説していきます。
ハイフレックス授業の導入には、技術環境の整備から学習者サポート、効果検証まで段階的なアプローチが必要です。ここでは、各段階で押さえるべきポイントを詳しく解説していきます。
まず、高速で安定したインターネット回線の確保が必要になります。対面とオンラインの学習者が同時に参加するため、映像や音声の遅延が発生しないよう、十分な帯域幅を確保しましょう。
次に、教室内のネットワーク環境を整備します。Wi-Fi環境の強化や有線LANの配線など、複数のデバイスが同時接続されても問題ない環境を構築することが重要です。
さらに、クラウドサービスの活用も欠かせません。録画データの保存やファイル共有のためのストレージ容量を十分に確保し、学習管理システム(LMS)との連携も考慮した環境整備を行いましょう。
まず、ハイフレックス授業の仕組みやメリット、参加方法について詳細なガイダンスを実施しましょう。対面とオンラインの選択方法や切り替えルールを明確に伝えることが大切です。
技術面でのサポートも欠かせません。学習者が使用するデバイスの推奨スペックや必要なソフトウェアのインストール方法、接続テストの手順を分かりやすく説明すると良いでしょう。特にオンライン参加者には、カメラやマイクの設定方法、トラブル時の対処法も事前に共有しておきましょう。
グループワークやディスカッションでは、対面とオンラインの参加者が平等に参加できる仕組みを設計することが重要です。それに伴い、教材の準備も見直しが必要になります。
画面共有しやすいデジタル教材の作成や、オンライン参加者にも見やすい資料のレイアウト調整も必要です。
音声については、教員の声を明瞭に拾うワイヤレスマイクや、教室全体の音を収音できる集音マイクが必要です。
ビデオ会議システムの選定も重要なポイントです。ZoomやMicrosoft Teams、Google Meetなど、機関の要件に合ったプラットフォームを選択し、録画機能や画面共有機能の使いやすさも考慮しましょう。
その他、プロジェクターやモニター、タブレットスタンドなどの周辺機器も授業の質を向上させる重要な要素となります。予算と効果のバランスを考慮しながら、段階的に機材を充実させていくと良いでしょう。
小規模なグループで試験的にハイフレックス授業を実施し、技術的な問題や運用上の課題を特定しましょう。ここでは、音声や映像の品質、接続の安定性、操作性などを詳細にチェックします。
また、対面とオンライン参加者の理解度や満足度を比較分析し、学習成果に差が生じていないかも確認しましょう。
学習者、教員、技術サポートスタッフそれぞれの視点から意見を聞き取り反映させていくことで、より質の高い授業内容になります。
収集したフィードバックを基に、優先度を付けて改善していくことがおすすめです。技術的な問題については即座に対応し、運用面の課題については段階的な改善を進めると良いでしょう。
 ハイフレックス授業では、対面とオンラインを同時に行うため、技術的なトラブルが発生する可能性があります。音声が聞こえない、映像が途切れる、接続が不安定になるなどの問題は授業の質に直結します。
ハイフレックス授業では、対面とオンラインを同時に行うため、技術的なトラブルが発生する可能性があります。音声が聞こえない、映像が途切れる、接続が不安定になるなどの問題は授業の質に直結します。
ここでは、具体的なトラブル対応策について詳しく解説していきます。
例えば、Zoomをメインで使用する場合でも、Microsoft TeamsやGoogle Meetといった代替プラットフォームを用意しておけば、接続トラブルが発生した際にすぐ切り替えられます。
インターネット回線についても、有線LANを基本としながら、モバイルWi-Fiやスマートフォンのテザリングを予備として備えておくと安心です。これにより、万が一回線障害が起きても授業を中断せずに続けられます。
さらに、音声配信用のマイクはワイヤレスのみではなく、有線マイクも併用するなど、冗長性を持たせることが望ましいでしょう。
事前にすべての機器の動作確認を行い、切り替えの手順を教員自身が習熟しておくことで、トラブル発生時の対応を大幅に短縮できます。
 ハイフレックス授業を効果的に行うには、対面とオンラインの双方で学習体験に差が出ないよう、安定した通信環境と高品質な音声・映像配信が欠かせません。
ハイフレックス授業を効果的に行うには、対面とオンラインの双方で学習体験に差が出ないよう、安定した通信環境と高品質な音声・映像配信が欠かせません。
特に音声は授業の理解度や参加感に直結するため、講師だけでなく学生の発言も明瞭に届けられる仕組みが必要です。しかし従来のマイクでは、教室後方の声を拾いにくい、対面参加者とオンライン参加者で音声品質に差が出るといった課題がありました。
こうした課題を解決し、すべての参加者が快適に学べる環境を整えるために活用できるのが、株式会社Airzの配信ソリューションです。
Airzのシステムは、360度全方向から高精度で音声を収集し、ノイズキャンセリング機能によって雑音を除去。講師や学生の声をクリアに届けます。さらにZoomやTeamsなど複数の配信ツールに対応し、リアルとオンラインを組み合わせた授業をスムーズに運営できます。
また、専門スタッフが教育機関ごとのニーズに合わせて最適な環境を提案し、導入から運用まで一貫してサポートしてくれる点も大きな魅力です。
ハイフレックス授業の導入を検討している方は、ぜひ一度ご相談ください。
本記事では、ハイフレックス授業の特徴や、従来のハイブリッド授業・ブレンド型授業との違い、導入手順やトラブル対応策までを詳しく解説します。
柔軟な学びの環境を実現したい教育機関や担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
Table of Contents
ハイフレックス授業とは
 ハイフレックス授業とは、Hybrid-Flexibleの略称で、同じ授業内容を対面とオンラインで同時に実施し、学習者が自由に参加方法を選択できる新しい授業形式です。新型コロナウイルス感染症の拡大をきっかけに急速に普及しました。
ハイフレックス授業とは、Hybrid-Flexibleの略称で、同じ授業内容を対面とオンラインで同時に実施し、学習者が自由に参加方法を選択できる新しい授業形式です。新型コロナウイルス感染症の拡大をきっかけに急速に普及しました。
教員は教室で授業を行いながら、ZoomなどのWeb会議システムを使って遠隔地の学生にもリアルタイムで配信します。
従来のハイブリッド授業とは異なり、学習者一人ひとりが毎回の授業で参加スタイルを自由に決められる点が最大の特徴といえるでしょう。
対面とオンラインを同時に実施する授業形式
ハイフレックス授業では、教員が教室で行う対面授業と、Web会議システムを通じたオンライン授業を同時進行で実施します。教室にいる学生と自宅などからオンライン参加する学生が、同じ時間に同じ内容の授業を受講できる仕組みです。教員は教室のスクリーンにオンライン参加者の画面を映し出すことで、双方の学生が互いの存在を認識できるよう工夫することができます。この形式により、感染症対策や交通事情、体調不良などの理由で教室に来られない学生も、授業に参加し続けることが可能になりました。
また、遠方に住む学生や社会人学習者にとっても、通学時間を削減しながら質の高い教育を受けられるメリットがあります。
学習者が参加方法を自由に選択できる
ハイフレックス授業の最大の特徴は、学習者が授業ごとに参加方法を自由に選択できることです。今日は教室で対面参加、明日はオンライン参加といったように、その時の状況や都合に応じて柔軟に決められます。従来の固定的な授業形式とは大きく異なり、学習者のライフスタイルや学習環境に合わせた個別対応が可能になっています。この自由度の高さにより、学習継続率の向上が期待されています。
体調不良や家庭の事情で教室に来られない日でも、オンラインで参加することで学習機会を失わずに済みます。また、集中しやすい環境を自分で選択できるため、学習効果の向上も報告されています。
リアルタイムで双方向のやり取りが可能
ハイフレックス授業では、対面参加者とオンライン参加者の間でリアルタイムの双方向コミュニケーションが取れます。教員は教室の学生からの質問を受けると同時に、オンライン参加者からのチャットや音声による質問にも対応できます。
また、グループワークや討論の際には、対面とオンラインの学生を混合したチームを編成することも可能です。
ハイフレックス授業とハイブリッド授業の違い
 ハイフレックス授業とハイブリッド授業は、どちらも対面とオンラインを組み合わせた授業形態ですが、学習者の選択権や実施方法に大きな違いがあります。ここでは、両者の具体的な違いについて詳しく解説します。
ハイフレックス授業とハイブリッド授業は、どちらも対面とオンラインを組み合わせた授業形態ですが、学習者の選択権や実施方法に大きな違いがあります。ここでは、両者の具体的な違いについて詳しく解説します。
参加方法の選択権が学習者にある
ハイフレックス授業の最大の特徴は、学習者一人ひとりが授業への参加方法を自由に選択できる点にあります。同じ授業内容を対面とオンラインで同時に提供し、学習者は自身の状況や都合に応じて、その都度最適な受講スタイルを決められるのです。例えば、体調不良や交通事情で教室に来られない日はオンラインで参加し、グループワークがある日は対面で参加するといった柔軟な選択が可能になります。
一方、従来のハイブリッド授業では、学期開始時や単元ごとに参加形式が固定されることが多く、学習者の日々の状況変化に対応しきれない場合がありました。ハイフレックス授業はこうした課題を解決する革新的な授業形態といえるでしょう。
ハイブリッドは事前に参加形式が決定されている
従来のハイブリッド授業では、学習者の参加形式が事前に決められているのが一般的です。例えば、クラスを対面参加グループとオンライン参加グループに分けて、それぞれ異なる日程や時間帯で授業を実施するケースが多く見られます。この方式では、対面授業とオンライン授業が別々に設計されることもあり、必ずしも同じ内容や体験を提供するとは限りません。また、一度決められた参加形式を途中で変更することは困難で、学習者の状況変化に柔軟に対応できないという課題があります。
さらに、対面とオンラインで異なる教材や課題が用意される場合もあり、学習者間で学習内容に差が生じる可能性もあります。これに対してハイフレックス授業は、全ての学習者が同等の学習機会を得られるよう設計されており、より公平で柔軟な学習環境を実現しているのです。
ハイフレックス授業とブレンド型授業の違い
 ハイフレックス授業とブレンド型授業は、その運用方法に大きな違いがあります。ここでは、両者の具体的な違いについて詳しく解説していきます。
ハイフレックス授業とブレンド型授業は、その運用方法に大きな違いがあります。ここでは、両者の具体的な違いについて詳しく解説していきます。
授業時間の固定性が違う
ハイフレックス授業では、全ての授業が同じ時間に対面とオンラインで同時開催されるため、授業時間は完全に固定されています。教員は決められた時間に教室で授業を行い、その様子をリアルタイムでオンライン受講者にも配信する仕組みです。学習者は授業開始時刻までに参加方法を選択し、指定された時間に受講する必要があります。
対照的にブレンド型授業は、対面授業の時間は固定されているものの、オンライン学習部分については録画視聴や課題提出など、学習者のペースに合わせて進められる場合が多くなっています。
コンテンツ配信のタイミングが違う
ハイフレックス授業では、授業内容が対面受講者とオンライン受講者に同時配信されることが基本となります。教員は教室にいる学生とオンライン参加の学生に対して、同じタイミングで同じ内容を提供し、質疑応答や議論も同時進行で行われます。そのため、全受講者が同じペースで学習を進めることになり、コンテンツの配信タイミングに差は生まれません。
一方、ブレンド型授業では対面授業とオンライン学習のコンテンツが段階的に配信されることが一般的です。例えば、対面授業で基礎概念を学んだ後、関連する動画教材や追加資料がオンラインで提供される流れになります。
学習者同士の交流機会に差がある
ハイフレックス授業では、対面参加者とオンライン参加者の間で交流形態に違いが生じやすくなります。対面参加者は授業前後の雑談や対面でのグループワークを通じて自然なコミュニケーションが取りやすい一方、オンライン参加者はチャット機能や画面越しでのやり取りが中心となる傾向があります。そのため、教員は双方の参加者が等しく交流できるよう、場づくりや進行方法に配慮する必要があります。
ブレンド型授業では、対面授業の機会に全員が同じ空間で学ぶため、直接的な交流が促進されます。また、オンライン学習期間中にも掲示板やグループチャットなどのツールを活用し、意見交換を継続することで学習コミュニティの維持が可能です。
ただし、対面期間とオンライン期間の温度差をなくすためには、オンライン時にも積極的な交流の仕組みを設けることが求められます。
ハイフレックス授業の導入手順
 ハイフレックス授業の導入には、技術環境の整備から学習者サポート、効果検証まで段階的なアプローチが必要です。ここでは、各段階で押さえるべきポイントを詳しく解説していきます。
ハイフレックス授業の導入には、技術環境の整備から学習者サポート、効果検証まで段階的なアプローチが必要です。ここでは、各段階で押さえるべきポイントを詳しく解説していきます。
技術環境とインフラの整備から開始
ハイフレックス授業導入の第一歩は、安定した技術環境とインフラの構築です。まず、高速で安定したインターネット回線の確保が必要になります。対面とオンラインの学習者が同時に参加するため、映像や音声の遅延が発生しないよう、十分な帯域幅を確保しましょう。
次に、教室内のネットワーク環境を整備します。Wi-Fi環境の強化や有線LANの配線など、複数のデバイスが同時接続されても問題ない環境を構築することが重要です。
さらに、クラウドサービスの活用も欠かせません。録画データの保存やファイル共有のためのストレージ容量を十分に確保し、学習管理システム(LMS)との連携も考慮した環境整備を行いましょう。
学習者への事前説明と準備支援
学習者が安心してハイフレックス授業に参加できるよう、事前説明と準備支援を徹底することが重要です。まず、ハイフレックス授業の仕組みやメリット、参加方法について詳細なガイダンスを実施しましょう。対面とオンラインの選択方法や切り替えルールを明確に伝えることが大切です。
技術面でのサポートも欠かせません。学習者が使用するデバイスの推奨スペックや必要なソフトウェアのインストール方法、接続テストの手順を分かりやすく説明すると良いでしょう。特にオンライン参加者には、カメラやマイクの設定方法、トラブル時の対処法も事前に共有しておきましょう。
授業設計とカリキュラムの見直し
ハイフレックス授業では、従来の対面授業とは異なる授業設計が必要です。対面とオンラインの両方の学習者が効果的に学習できるよう、双方向的な要素を取り入れた授業構成を検討しましょう。グループワークやディスカッションでは、対面とオンラインの参加者が平等に参加できる仕組みを設計することが重要です。それに伴い、教材の準備も見直しが必要になります。
画面共有しやすいデジタル教材の作成や、オンライン参加者にも見やすい資料のレイアウト調整も必要です。
必要な機材とソフトウェアの導入
ハイフレックス授業の品質を左右する機材とソフトウェアの選定は慎重に行う必要があります。まず、高画質な映像配信のためのWebカメラや、教室全体を映せる広角カメラの導入を検討しましょう。音声については、教員の声を明瞭に拾うワイヤレスマイクや、教室全体の音を収音できる集音マイクが必要です。
ビデオ会議システムの選定も重要なポイントです。ZoomやMicrosoft Teams、Google Meetなど、機関の要件に合ったプラットフォームを選択し、録画機能や画面共有機能の使いやすさも考慮しましょう。
その他、プロジェクターやモニター、タブレットスタンドなどの周辺機器も授業の質を向上させる重要な要素となります。予算と効果のバランスを考慮しながら、段階的に機材を充実させていくと良いでしょう。
パイロット授業での効果検証
本格導入前のパイロット授業は、問題点の洗い出しと改善策の検討に欠かせないプロセスです。小規模なグループで試験的にハイフレックス授業を実施し、技術的な問題や運用上の課題を特定しましょう。ここでは、音声や映像の品質、接続の安定性、操作性などを詳細にチェックします。
また、対面とオンライン参加者の理解度や満足度を比較分析し、学習成果に差が生じていないかも確認しましょう。
フィードバック収集と改善実施
パイロット授業の実施後は、参加者からの詳細なフィードバックを収集し、継続的に改善を行いましょう。学習者、教員、技術サポートスタッフそれぞれの視点から意見を聞き取り反映させていくことで、より質の高い授業内容になります。
収集したフィードバックを基に、優先度を付けて改善していくことがおすすめです。技術的な問題については即座に対応し、運用面の課題については段階的な改善を進めると良いでしょう。
ハイフレックス授業のトラブル対応策
 ハイフレックス授業では、対面とオンラインを同時に行うため、技術的なトラブルが発生する可能性があります。音声が聞こえない、映像が途切れる、接続が不安定になるなどの問題は授業の質に直結します。
ハイフレックス授業では、対面とオンラインを同時に行うため、技術的なトラブルが発生する可能性があります。音声が聞こえない、映像が途切れる、接続が不安定になるなどの問題は授業の質に直結します。
ここでは、具体的なトラブル対応策について詳しく解説していきます。
複数の通信手段を事前に準備する
ハイフレックス授業を安定して行うためには、メインの通信手段に加え、複数のバックアップを準備しておくことが大切です。例えば、Zoomをメインで使用する場合でも、Microsoft TeamsやGoogle Meetといった代替プラットフォームを用意しておけば、接続トラブルが発生した際にすぐ切り替えられます。
インターネット回線についても、有線LANを基本としながら、モバイルWi-Fiやスマートフォンのテザリングを予備として備えておくと安心です。これにより、万が一回線障害が起きても授業を中断せずに続けられます。
さらに、音声配信用のマイクはワイヤレスのみではなく、有線マイクも併用するなど、冗長性を持たせることが望ましいでしょう。
事前にすべての機器の動作確認を行い、切り替えの手順を教員自身が習熟しておくことで、トラブル発生時の対応を大幅に短縮できます。
録画機能で授業内容を保存する
ハイフレックス授業では、録画機能がトラブル対応の要となります。授業中に技術的な問題が起き、一部の学生が内容を聞き逃しても、録画があれば後から学習を補うことができます。 録画は授業開始前に必ず設定を確認し、自動録画機能を活用することで、録り忘れなどのミスを防ぎましょう。録画データは複数の場所に保存しておくと、一方のストレージに不具合があっても授業記録を失わずに済みます。サポートスタッフの配置と連携
授業を円滑に進めるためには、教員に加えてサポートスタッフを配置するのが効果的です。 授業中に技術トラブルが発生した場合、教員は授業進行に集中し、サポートスタッフが解決を担当することで中断時間を最小限にできます。 そのためスタッフには、機器の基本操作やよくあるトラブル対応を事前に習得してもらうことが欠かせません。学習者向けヘルプデスクの設置
学生の技術的な課題に対応するには、専用のヘルプデスクを設置することが有効です。 オンライン授業では接続不良や操作ミスが起こりやすく、対応が遅れると授業進行や学習機会に影響します。専用窓口を設ければ、ヘルプデスクが個別に対応する間も授業を中断せず進められます。 また、電話・メール・チャットなど複数の連絡手段を用意すれば、学生は自分に合った方法でスムーズに相談できるでしょう。ハイフレックス授業にはAirzがおすすめ
 ハイフレックス授業を効果的に行うには、対面とオンラインの双方で学習体験に差が出ないよう、安定した通信環境と高品質な音声・映像配信が欠かせません。
ハイフレックス授業を効果的に行うには、対面とオンラインの双方で学習体験に差が出ないよう、安定した通信環境と高品質な音声・映像配信が欠かせません。
特に音声は授業の理解度や参加感に直結するため、講師だけでなく学生の発言も明瞭に届けられる仕組みが必要です。しかし従来のマイクでは、教室後方の声を拾いにくい、対面参加者とオンライン参加者で音声品質に差が出るといった課題がありました。
こうした課題を解決し、すべての参加者が快適に学べる環境を整えるために活用できるのが、株式会社Airzの配信ソリューションです。
Airzのシステムは、360度全方向から高精度で音声を収集し、ノイズキャンセリング機能によって雑音を除去。講師や学生の声をクリアに届けます。さらにZoomやTeamsなど複数の配信ツールに対応し、リアルとオンラインを組み合わせた授業をスムーズに運営できます。
また、専門スタッフが教育機関ごとのニーズに合わせて最適な環境を提案し、導入から運用まで一貫してサポートしてくれる点も大きな魅力です。
ハイフレックス授業の導入を検討している方は、ぜひ一度ご相談ください。