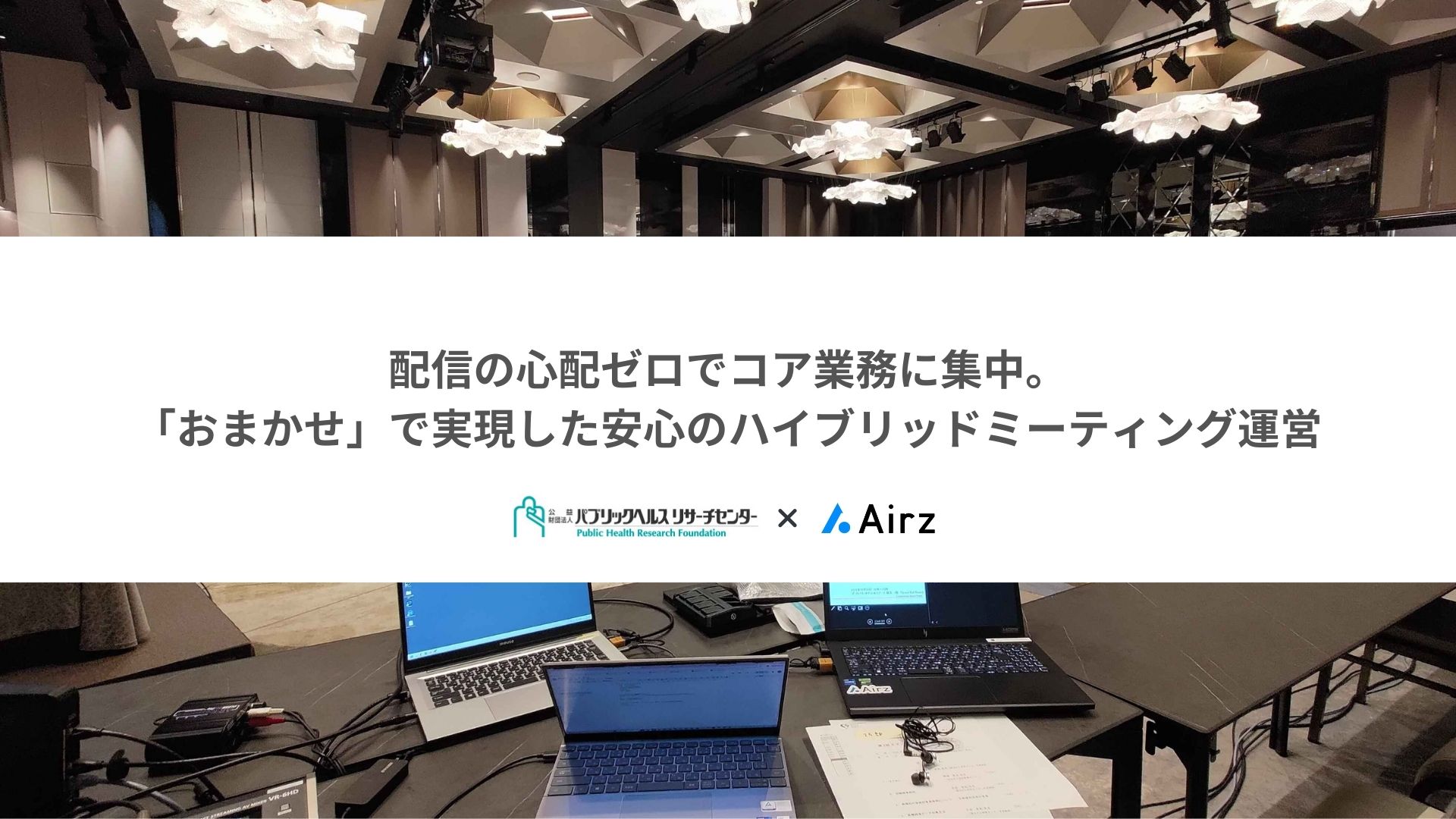失敗しないオンライン記者会見|安定・高品質な配信のポイント
 更新日
更新日

オンライン記者会見は、遠隔地から参加できる利便性やコスト削減など、多くのメリットがあります。しかし、技術トラブルや通信環境などのデメリットも存在するため、事前準備やトラブル対策が重要です。
本記事では、オンライン記者会見の特徴、メリット・デメリット、基本的な流れ、万全な開催のためのポイントについて詳しく解説します。初めてオンライン記者会見を検討している方も、ぜひ参考にしてください。
 オンライン記者会見とは、ZoomやYouTubeなどのデジタルプラットフォームを活用して、インターネット経由で実施する記者会見のことです。新型コロナウイルス感染拡大の影響で急速に普及し、現在では対面式の記者会見と並ぶ重要な情報発信手段として定着しています。
オンライン記者会見とは、ZoomやYouTubeなどのデジタルプラットフォームを活用して、インターネット経由で実施する記者会見のことです。新型コロナウイルス感染拡大の影響で急速に普及し、現在では対面式の記者会見と並ぶ重要な情報発信手段として定着しています。
企業の新製品発表や決算説明会、政府機関の政策発表など、様々な場面で活用されており、参加者は自宅やオフィスから手軽に参加できるのが特徴です。
従来の会場型記者会見と比較して、時間や場所の制約が大幅に軽減されるため、より多くのメディア関係者の参加を促すことが可能になりました。

オンライン記者会見には、従来の対面式記者会見と比較して多くのメリットがあります。ここでは、オンライン記者会見が企業の広報活動にもたらす具体的な利点について、詳しく解説していきます。
オンライン記者会見の最大のメリットが、従来の対面式記者会見で必要だった会場費や設営費用を大幅に削減できることです。
従来の記者会見では、ホテルや会議室を借りる必要があります。その場合、東京都内では、規模にもよりますが数十万円から数百万円の会場費が発生していました。これに加えて、音響設備やプロジェクター、照明機器のレンタル費用、さらにはバックパネルや受付デスクなどの設営費用も必要になります。
しかし、オンライン記者会見では、これらの物理的な設備投資が一切不要になります。自社のオフィス会議室や専用スタジオから配信すれば、会場費はゼロです。必要なのは配信機材とインターネット環境のみで、初期投資を回収すれば継続的なコストは大幅に抑えられます。
地理的制約の解消は、オンライン記者会見が提供する革新的なメリットの一つです。
従来の対面式記者会見では、東京で開催される場合、地方のメディア関係者は交通費や宿泊費を負担して参加する必要がありました。
オンライン形式であれば、北海道から沖縄まで、全国どこからでも同じ条件で参加できます。地方紙や地域メディアの記者も気軽に参加でき、より幅広い媒体での露出機会を獲得できるでしょう。
オンライン記者会見では、リアルタイム配信と同時に録画も自動的に行われるため、後日のアーカイブ配信が可能になります。これは対面式記者会見では実現困難だった大きなメリットです。
当日参加できなかった記者や、途中で通信トラブルが発生した参加者も、後から完全な内容を視聴できます。録画データは編集も可能で、重要なポイントにテロップを追加したり、質疑応答部分のみを抜粋したりといった活用もできるでしょう。
YouTubeやVimeoなどの動画プラットフォームにアップロードすれば、メディア関係者以外の一般視聴者にも情報を届けられます。
従来の記者会見では、会場の予約から設営、リハーサルまで数週間から1ヶ月程度の準備期間が必要でした。しかし、オンライン記者会見なら最短1週間程度で開催可能です。会場探しや設営業者との調整が不要になり、配信機材の準備と参加者への案内送付が主な準備作業となります。
緊急性の高い発表や、競合他社の動向に素早く対応したい場合には、この時間短縮効果は非常に重要です。例えば、新型コロナウイルス関連の緊急発表や、株価に影響する重要な業績修正発表などでは、迅速な情報開示が求められます。
オンライン形式なら、発表内容が固まり次第すぐに記者会見を設定できるため、タイムリーな情報発信が実現できるでしょう。
台風や大雪などの悪天候、電車の運行停止や交通渋滞といった外的要因により、従来の記者会見は中止や延期を余儀なくされることがありました。特に重要な発表タイミングが決まっている場合、このような不測の事態は企業にとって大きな損失となります。
オンライン記者会見なら、参加者も主催者も自宅やオフィスから参加できるため、天候や交通事情の影響を受けません。台風が接近していても、地震による交通麻痺が発生していても、インターネット環境さえ確保できれば予定通り開催できます。
グローバル展開を進める企業にとって、海外メディアへの情報発信は重要な課題です。従来の対面式記者会見では、海外の記者が日本まで来日する必要があり、時差や移動コスト、ビザ取得などの制約により参加が困難でした。
オンライン記者会見なら、時差の調整は必要ですが、世界中どこからでも参加可能になります。アメリカ、ヨーロッパ、アジア各国のメディア関係者が同時に参加でき、グローバルな情報発信が実現できるでしょう。
同時通訳機能を活用すれば、日本語での発表内容をリアルタイムで英語や中国語に翻訳して配信することも可能です。これにより、海外展開する新商品の発表や、国際的な提携発表などで、現地メディアに直接アプローチできます。

オンライン記者会見は利便性が高い反面、いくつかのデメリットも存在します。以下では、オンライン記者会見における主なデメリットについて詳しく解説していきます。
技術的なトラブルが発生する可能性
オンライン記者会見では、配信機材の故障やシステムエラーなど、様々な技術的トラブルが起こる可能性があります。
例えば、配信用PCの突然のフリーズ、スイッチャーの不具合、録画機器の停止などが挙げられます。これらのトラブルは、本番中に突然発生することが多いのが特徴です。特に複数のカメラや音響機器を使用する場合、機材間の連携不具合も起こりやすくなります。
また、配信プラットフォーム自体のサーバーダウンや、使用している配信ソフトウェアのバグなども想定されるトラブルです。こうした技術的問題が発生すると、記者会見が中断されたり、参加者が離脱してしまったりする恐れがあります。
そのため、事前の機材チェックやバックアップシステムの準備が不可欠となります。
オンライン記者会見の品質は、主催者側と参加者側双方のインターネット通信環境に大きく依存します。
会場のネットワーク回線が不安定だと、配信が途切れたり画質が劣化したりする問題が発生します。特に上り回線の速度が不十分な場合、高画質での配信が困難になり、視聴者にとって見づらい映像となってしまいます。
参加者側でも、自宅やオフィスのWi-Fi環境によって視聴品質が左右されます。通信速度が遅い環境では、音声の遅延や映像のカクつきが生じ、記者会見の内容を正確に把握できない可能性があります。
また、モバイル回線を使用している参加者の場合、データ通信量の制限により途中で接続が切れるリスクもあります。これらの通信環境の問題は、記者会見の効果を大幅に低下させる要因となります。
オンライン記者会見では、従来の対面式記者会見で可能だった直接的なコミュニケーションが制限されます。会場での偶発的な情報交換や、記者同士の雑談から得られる業界情報などが期待できません。また、登壇者の表情や身振り手振りなどの非言語コミュニケーションが伝わりにくく、発言の真意を読み取ることが困難になる場合があります。
質疑応答の際も、画面越しでは挙手のタイミングが分かりにくく、複数の記者が同時に発言してしまう混乱が生じることがあります。さらに、新製品発表会などでは実物に触れることができないため、記者が製品の質感や使用感を直接確認できないというデメリットもあります。
このような対面コミュニケーションの欠如は、記者の理解度や満足度に影響を与える可能性があります。
オンライン記者会見では、音声や映像の品質が様々な要因により不安定になることがあります。
音声については、マイクの設定不良やエコー、ハウリングなどの問題が発生し、登壇者の発言が聞き取りにくくなる場合があります。特に複数人が登壇する場合、マイクの切り替えタイミングや音量調整が適切に行われないと、音声品質が著しく低下します。
映像面では、照明不足による暗い画像や、カメラの解像度設定ミスによる低画質配信などが問題となります。
また、配信中の帯域不足により、映像が圧縮されて画質が劣化したり、フレームレートが低下してカクカクした動きになったりすることもあります。
オンライン記者会見を実施するためには、従来の記者会見にはない多くの機材と配信システムの準備が必要となります。
カメラ、マイク、照明機器、配信用PC、スイッチャー、ミキサーなど、専門的な機材を揃える必要があり、初期投資が高額になる可能性があります。また、これらの機材を適切に操作できる技術スタッフの確保も重要な課題です。
配信プラットフォームの選定や設定も複雑で、参加者の規模や用途に応じて最適なシステムを選択する必要があります。ZoomやYouTube Live、専用の配信プラットフォームなど、それぞれに特徴があり、事前の検証と設定が不可欠です。

オンライン記者会見は、従来の対面式会見とは異なる独自の流れで進行されます。事前準備から閉会後のフォローまで、各段階で適切な対応が求められます。
会見を成功させるためには、段階的なプロセスを理解し、それぞれのステップで必要な作業を確実に実行しましょう。
オンライン記者会見を成功させるためには、事前準備を徹底して行う必要があります。
まず配信環境の整備が最優先となり、安定したインターネット回線の確保、複数台のカメラ設置、音響機材の調整が必要です。会場のレイアウト設計では、登壇者の配置と照明の調整により、画面越しでも見やすい環境を作り上げましょう。
配信プラットフォームの選定も重要な要素で、ZoomやYouTube Live、Microsoft Teamsなど、参加予定メディアが使い慣れたツールの使用がおすすめです。
機材面では、配信用PC、スイッチャー、ミキサーなどの専門機器を準備し、万が一の機材トラブルに備えてバックアップ機器も用意しておく必要があります。
さらに、会場の通信環境テストを複数回実施し、映像・音声の品質確認を徹底的に行います。プロのカメラマンやエンジニアとの事前打ち合わせにより、当日の役割分担を明確化し、スムーズな運営体制を構築することが成功への鍵となります。
参加者への案内は、オンライン記者会見の参加率を左右する重要な要素です。
招待状には会見の目的、開催日時、参加方法を明記し、従来の対面式会見と同様の情報に加えて、接続用URLやパスワード、推奨環境などの技術的な詳細を含める必要があります。送付タイミングは開催の1週間前を目安とし、リマインドメールを開催前日と当日朝に配信することが効果的です。
参加方法は、セキュリティを考慮してた限定公開URLの発行や、参加者専用のプレスルームを開設がおすすめです。また、参加者が事前に接続テストを行えるよう、テスト用のURLを別途提供することで当日のトラブルを未然に防げます。
オンライン配信では技術的なトラブルが会見の品質を大きく左右するため、開始前のテストは必須作業となります。
会見開始の10分前から音楽を流すことで、参加者が音声レベルを確認できる環境を提供し、同時に映像の鮮明さや画角の適切性もチェックします。登壇者のマイクテストでは、声の大きさや音質を入念に確認し、ハウリングや雑音の有無を検証しましょう。
カメラワークのテストでは、複数台のカメラ切り替えがスムーズに行われるか、登壇者の表情が適切に映し出されるかを確認します。プレゼンテーション資料の投影テストも欠かせません。文字の読みやすさや画面共有の動作確認を必ず行いましょう。
また、参加者側の環境確認も重要です。音声が適切に届いているか、映像が途切れていないかをチャット機能などで確認すると安心です。
オンライン環境でのプレゼンテーションは、対面式とは異なる配慮が必要となります。画面越しの視聴者に対しては、より明確で聞き取りやすい話し方を心がけ、適度な間を取りながら進行しましょう。
資料の提示では、文字サイズを大きめに設定し、重要なポイントにはハイライトやアニメーションを効果的に活用するのがポイントです。また、カメラワークの工夫により、登壇者の表情と資料を交互に映し出すことで、視聴者の集中力を維持できます。
複数の登壇者がいる場合は、発言者に合わせてカメラを切り替え、誰が話しているかを明確に示すことが必要になります。
オンライン記者会見における質疑応答は、対面式と比較して特別な配慮が求められる重要なセッションです。参加者からの質問受付方法として、挙手機能とチャット機能の併用が効果的です。司会者が適切に質問者を指名し、発言順序を明確に管理すると良いでしょう。
音声の遅延やタイムラグを考慮し、質問者には名前と所属を最初に述べてもらうことで、他の参加者にも分かりやすく、スムーズに進みやすくなります。
チャット形式での質問では、司会者や運営スタッフが内容を整理し、登壇者に分かりやすく伝えましょう。返答を準備している間の「つなぎ」として、企業紹介動画や製品デモンストレーションを活用することで、参加者の関心や集中力を維持できます。
オンライン記者会見の締めくくりでは、参加者への感謝の気持ちを込めた閉会挨拶が重要な役割を果たします。司会者は会見の要点を簡潔にまとめ、発表内容の重要なポイントを再度強調することで、参加者の理解を深めることができます。
今後のスケジュールや追加情報の予定についても案内することで、会見後の関係構築にもつながります。広報担当者のメールアドレスや電話番号を画面上に表示して、連絡先として提示しておくと、後日の問い合わせに対応できるのでおすすめです。
また、追加取材の受付についても言及し、個別インタビューの可能性や条件について説明することで、メディア関係者のニーズに応えられるでしょう。
会見終了後の録画データ処理は、オンライン記者会見の価値を最大化する重要な工程です。収録した映像の編集は、音声レベルの調整、不要な部分のカット、テロップの追加などを行い、視聴しやすい形に仕上げます。
特に質疑応答部分では、質問者の音声が聞き取りにくい場合があるため、字幕やテロップで補完することがポイントです。
編集済み動画の配信準備では、複数の形式でエンコーディングを行い、様々なデバイスや通信環境に対応できるようにしましょう。YouTubeやVimeoなどの動画プラットフォームへのアップロードに加え、自社サイトでの限定公開も検討し、セキュリティを保ちながら必要な関係者がアクセスできる環境を構築することがおすすめです。
 オンライン記者会見は、配信環境の整備から機材運用、当日の進行管理まで、多くの準備と専門知識が求められます。そこで頼りになるのが、国際機関や省庁、上場企業を含む1,000件以上のイベント配信を支援してきたAirzです。
オンライン記者会見は、配信環境の整備から機材運用、当日の進行管理まで、多くの準備と専門知識が求められます。そこで頼りになるのが、国際機関や省庁、上場企業を含む1,000件以上のイベント配信を支援してきたAirzです。
Airzは、会場とオンラインの両方に最適化した映像・音響環境を構築し、ZoomやYouTubeなど配信ツールの選定・設定から、機材の持ち込み・設置、当日のディレクション、アーカイブ動画の編集・納品まで一貫して対応します。記者会見のように失敗が許されない場面でも、事前リハーサルや通信テストを徹底し、機材トラブルや回線不安定のリスクを最小限に抑えます。
さらに、多カメラ構成やワイプ表示、テロップ・パターン合成などの演出にも柔軟に対応できるため、視聴者にとって見やすく、情報が正確に伝わる映像制作が可能です。同時通訳や字幕挿入にも対応しており、海外メディア向けの発信にも強みを発揮します。
「トラブルゼロ・高品質の配信」を目指すAirzなら、初めてのオンライン記者会見でも安心して任せられます。目的や規模に合わせた最適なプランの提案も受けられるので、お気軽にご相談ください。
本記事では、オンライン記者会見の特徴、メリット・デメリット、基本的な流れ、万全な開催のためのポイントについて詳しく解説します。初めてオンライン記者会見を検討している方も、ぜひ参考にしてください。
Table of Contents
オンライン記者会見とは
 オンライン記者会見とは、ZoomやYouTubeなどのデジタルプラットフォームを活用して、インターネット経由で実施する記者会見のことです。新型コロナウイルス感染拡大の影響で急速に普及し、現在では対面式の記者会見と並ぶ重要な情報発信手段として定着しています。
オンライン記者会見とは、ZoomやYouTubeなどのデジタルプラットフォームを活用して、インターネット経由で実施する記者会見のことです。新型コロナウイルス感染拡大の影響で急速に普及し、現在では対面式の記者会見と並ぶ重要な情報発信手段として定着しています。
企業の新製品発表や決算説明会、政府機関の政策発表など、様々な場面で活用されており、参加者は自宅やオフィスから手軽に参加できるのが特徴です。
従来の会場型記者会見と比較して、時間や場所の制約が大幅に軽減されるため、より多くのメディア関係者の参加を促すことが可能になりました。
オンライン記者会見のメリット

オンライン記者会見には、従来の対面式記者会見と比較して多くのメリットがあります。ここでは、オンライン記者会見が企業の広報活動にもたらす具体的な利点について、詳しく解説していきます。
会場費や設営費用を大幅に削減できる
オンライン記者会見の最大のメリットが、従来の対面式記者会見で必要だった会場費や設営費用を大幅に削減できることです。
従来の記者会見では、ホテルや会議室を借りる必要があります。その場合、東京都内では、規模にもよりますが数十万円から数百万円の会場費が発生していました。これに加えて、音響設備やプロジェクター、照明機器のレンタル費用、さらにはバックパネルや受付デスクなどの設営費用も必要になります。
しかし、オンライン記者会見では、これらの物理的な設備投資が一切不要になります。自社のオフィス会議室や専用スタジオから配信すれば、会場費はゼロです。必要なのは配信機材とインターネット環境のみで、初期投資を回収すれば継続的なコストは大幅に抑えられます。
全国どこからでも参加可能になる
地理的制約の解消は、オンライン記者会見が提供する革新的なメリットの一つです。
従来の対面式記者会見では、東京で開催される場合、地方のメディア関係者は交通費や宿泊費を負担して参加する必要がありました。
オンライン形式であれば、北海道から沖縄まで、全国どこからでも同じ条件で参加できます。地方紙や地域メディアの記者も気軽に参加でき、より幅広い媒体での露出機会を獲得できるでしょう。
録画配信で後から視聴できる
オンライン記者会見では、リアルタイム配信と同時に録画も自動的に行われるため、後日のアーカイブ配信が可能になります。これは対面式記者会見では実現困難だった大きなメリットです。
当日参加できなかった記者や、途中で通信トラブルが発生した参加者も、後から完全な内容を視聴できます。録画データは編集も可能で、重要なポイントにテロップを追加したり、質疑応答部分のみを抜粋したりといった活用もできるでしょう。
YouTubeやVimeoなどの動画プラットフォームにアップロードすれば、メディア関係者以外の一般視聴者にも情報を届けられます。
準備時間を短縮できる
従来の記者会見では、会場の予約から設営、リハーサルまで数週間から1ヶ月程度の準備期間が必要でした。しかし、オンライン記者会見なら最短1週間程度で開催可能です。会場探しや設営業者との調整が不要になり、配信機材の準備と参加者への案内送付が主な準備作業となります。
緊急性の高い発表や、競合他社の動向に素早く対応したい場合には、この時間短縮効果は非常に重要です。例えば、新型コロナウイルス関連の緊急発表や、株価に影響する重要な業績修正発表などでは、迅速な情報開示が求められます。
オンライン形式なら、発表内容が固まり次第すぐに記者会見を設定できるため、タイムリーな情報発信が実現できるでしょう。
天候や交通事情に左右されない
台風や大雪などの悪天候、電車の運行停止や交通渋滞といった外的要因により、従来の記者会見は中止や延期を余儀なくされることがありました。特に重要な発表タイミングが決まっている場合、このような不測の事態は企業にとって大きな損失となります。
オンライン記者会見なら、参加者も主催者も自宅やオフィスから参加できるため、天候や交通事情の影響を受けません。台風が接近していても、地震による交通麻痺が発生していても、インターネット環境さえ確保できれば予定通り開催できます。
海外メディアも参加しやすい
グローバル展開を進める企業にとって、海外メディアへの情報発信は重要な課題です。従来の対面式記者会見では、海外の記者が日本まで来日する必要があり、時差や移動コスト、ビザ取得などの制約により参加が困難でした。
オンライン記者会見なら、時差の調整は必要ですが、世界中どこからでも参加可能になります。アメリカ、ヨーロッパ、アジア各国のメディア関係者が同時に参加でき、グローバルな情報発信が実現できるでしょう。
同時通訳機能を活用すれば、日本語での発表内容をリアルタイムで英語や中国語に翻訳して配信することも可能です。これにより、海外展開する新商品の発表や、国際的な提携発表などで、現地メディアに直接アプローチできます。
オンライン記者会見のデメリット

オンライン記者会見は利便性が高い反面、いくつかのデメリットも存在します。以下では、オンライン記者会見における主なデメリットについて詳しく解説していきます。
技術的なトラブルが発生する可能性
オンライン記者会見では、配信機材の故障やシステムエラーなど、様々な技術的トラブルが起こる可能性があります。
例えば、配信用PCの突然のフリーズ、スイッチャーの不具合、録画機器の停止などが挙げられます。これらのトラブルは、本番中に突然発生することが多いのが特徴です。特に複数のカメラや音響機器を使用する場合、機材間の連携不具合も起こりやすくなります。
また、配信プラットフォーム自体のサーバーダウンや、使用している配信ソフトウェアのバグなども想定されるトラブルです。こうした技術的問題が発生すると、記者会見が中断されたり、参加者が離脱してしまったりする恐れがあります。
そのため、事前の機材チェックやバックアップシステムの準備が不可欠となります。
通信環境に左右される
オンライン記者会見の品質は、主催者側と参加者側双方のインターネット通信環境に大きく依存します。
会場のネットワーク回線が不安定だと、配信が途切れたり画質が劣化したりする問題が発生します。特に上り回線の速度が不十分な場合、高画質での配信が困難になり、視聴者にとって見づらい映像となってしまいます。
参加者側でも、自宅やオフィスのWi-Fi環境によって視聴品質が左右されます。通信速度が遅い環境では、音声の遅延や映像のカクつきが生じ、記者会見の内容を正確に把握できない可能性があります。
また、モバイル回線を使用している参加者の場合、データ通信量の制限により途中で接続が切れるリスクもあります。これらの通信環境の問題は、記者会見の効果を大幅に低下させる要因となります。
対面でのコミュニケーションが取れない
オンライン記者会見では、従来の対面式記者会見で可能だった直接的なコミュニケーションが制限されます。会場での偶発的な情報交換や、記者同士の雑談から得られる業界情報などが期待できません。また、登壇者の表情や身振り手振りなどの非言語コミュニケーションが伝わりにくく、発言の真意を読み取ることが困難になる場合があります。
質疑応答の際も、画面越しでは挙手のタイミングが分かりにくく、複数の記者が同時に発言してしまう混乱が生じることがあります。さらに、新製品発表会などでは実物に触れることができないため、記者が製品の質感や使用感を直接確認できないというデメリットもあります。
このような対面コミュニケーションの欠如は、記者の理解度や満足度に影響を与える可能性があります。
音声や映像の品質が不安定になる
オンライン記者会見では、音声や映像の品質が様々な要因により不安定になることがあります。
音声については、マイクの設定不良やエコー、ハウリングなどの問題が発生し、登壇者の発言が聞き取りにくくなる場合があります。特に複数人が登壇する場合、マイクの切り替えタイミングや音量調整が適切に行われないと、音声品質が著しく低下します。
映像面では、照明不足による暗い画像や、カメラの解像度設定ミスによる低画質配信などが問題となります。
また、配信中の帯域不足により、映像が圧縮されて画質が劣化したり、フレームレートが低下してカクカクした動きになったりすることもあります。
機材や配信システムの準備が必要
オンライン記者会見を実施するためには、従来の記者会見にはない多くの機材と配信システムの準備が必要となります。
カメラ、マイク、照明機器、配信用PC、スイッチャー、ミキサーなど、専門的な機材を揃える必要があり、初期投資が高額になる可能性があります。また、これらの機材を適切に操作できる技術スタッフの確保も重要な課題です。
配信プラットフォームの選定や設定も複雑で、参加者の規模や用途に応じて最適なシステムを選択する必要があります。ZoomやYouTube Live、専用の配信プラットフォームなど、それぞれに特徴があり、事前の検証と設定が不可欠です。
オンライン記者会見の基本的な流れ

オンライン記者会見は、従来の対面式会見とは異なる独自の流れで進行されます。事前準備から閉会後のフォローまで、各段階で適切な対応が求められます。
会見を成功させるためには、段階的なプロセスを理解し、それぞれのステップで必要な作業を確実に実行しましょう。
事前準備と機材セットアップを行う
オンライン記者会見を成功させるためには、事前準備を徹底して行う必要があります。
まず配信環境の整備が最優先となり、安定したインターネット回線の確保、複数台のカメラ設置、音響機材の調整が必要です。会場のレイアウト設計では、登壇者の配置と照明の調整により、画面越しでも見やすい環境を作り上げましょう。
配信プラットフォームの選定も重要な要素で、ZoomやYouTube Live、Microsoft Teamsなど、参加予定メディアが使い慣れたツールの使用がおすすめです。
機材面では、配信用PC、スイッチャー、ミキサーなどの専門機器を準備し、万が一の機材トラブルに備えてバックアップ機器も用意しておく必要があります。
さらに、会場の通信環境テストを複数回実施し、映像・音声の品質確認を徹底的に行います。プロのカメラマンやエンジニアとの事前打ち合わせにより、当日の役割分担を明確化し、スムーズな運営体制を構築することが成功への鍵となります。
参加者への招待状と参加情報を送付
参加者への案内は、オンライン記者会見の参加率を左右する重要な要素です。
招待状には会見の目的、開催日時、参加方法を明記し、従来の対面式会見と同様の情報に加えて、接続用URLやパスワード、推奨環境などの技術的な詳細を含める必要があります。送付タイミングは開催の1週間前を目安とし、リマインドメールを開催前日と当日朝に配信することが効果的です。
参加方法は、セキュリティを考慮してた限定公開URLの発行や、参加者専用のプレスルームを開設がおすすめです。また、参加者が事前に接続テストを行えるよう、テスト用のURLを別途提供することで当日のトラブルを未然に防げます。
開始前の音声・映像テストを実施
オンライン配信では技術的なトラブルが会見の品質を大きく左右するため、開始前のテストは必須作業となります。
会見開始の10分前から音楽を流すことで、参加者が音声レベルを確認できる環境を提供し、同時に映像の鮮明さや画角の適切性もチェックします。登壇者のマイクテストでは、声の大きさや音質を入念に確認し、ハウリングや雑音の有無を検証しましょう。
カメラワークのテストでは、複数台のカメラ切り替えがスムーズに行われるか、登壇者の表情が適切に映し出されるかを確認します。プレゼンテーション資料の投影テストも欠かせません。文字の読みやすさや画面共有の動作確認を必ず行いましょう。
また、参加者側の環境確認も重要です。音声が適切に届いているか、映像が途切れていないかをチャット機能などで確認すると安心です。
発表者によるプレゼンテーション
オンライン環境でのプレゼンテーションは、対面式とは異なる配慮が必要となります。画面越しの視聴者に対しては、より明確で聞き取りやすい話し方を心がけ、適度な間を取りながら進行しましょう。
資料の提示では、文字サイズを大きめに設定し、重要なポイントにはハイライトやアニメーションを効果的に活用するのがポイントです。また、カメラワークの工夫により、登壇者の表情と資料を交互に映し出すことで、視聴者の集中力を維持できます。
複数の登壇者がいる場合は、発言者に合わせてカメラを切り替え、誰が話しているかを明確に示すことが必要になります。
質疑応答セッションを実施
オンライン記者会見における質疑応答は、対面式と比較して特別な配慮が求められる重要なセッションです。参加者からの質問受付方法として、挙手機能とチャット機能の併用が効果的です。司会者が適切に質問者を指名し、発言順序を明確に管理すると良いでしょう。
音声の遅延やタイムラグを考慮し、質問者には名前と所属を最初に述べてもらうことで、他の参加者にも分かりやすく、スムーズに進みやすくなります。
チャット形式での質問では、司会者や運営スタッフが内容を整理し、登壇者に分かりやすく伝えましょう。返答を準備している間の「つなぎ」として、企業紹介動画や製品デモンストレーションを活用することで、参加者の関心や集中力を維持できます。
閉会挨拶と今後の予定案内
オンライン記者会見の締めくくりでは、参加者への感謝の気持ちを込めた閉会挨拶が重要な役割を果たします。司会者は会見の要点を簡潔にまとめ、発表内容の重要なポイントを再度強調することで、参加者の理解を深めることができます。
今後のスケジュールや追加情報の予定についても案内することで、会見後の関係構築にもつながります。広報担当者のメールアドレスや電話番号を画面上に表示して、連絡先として提示しておくと、後日の問い合わせに対応できるのでおすすめです。
また、追加取材の受付についても言及し、個別インタビューの可能性や条件について説明することで、メディア関係者のニーズに応えられるでしょう。
録画データの編集と配信準備
会見終了後の録画データ処理は、オンライン記者会見の価値を最大化する重要な工程です。収録した映像の編集は、音声レベルの調整、不要な部分のカット、テロップの追加などを行い、視聴しやすい形に仕上げます。
特に質疑応答部分では、質問者の音声が聞き取りにくい場合があるため、字幕やテロップで補完することがポイントです。
編集済み動画の配信準備では、複数の形式でエンコーディングを行い、様々なデバイスや通信環境に対応できるようにしましょう。YouTubeやVimeoなどの動画プラットフォームへのアップロードに加え、自社サイトでの限定公開も検討し、セキュリティを保ちながら必要な関係者がアクセスできる環境を構築することがおすすめです。
オンライン記者会見はAirzにお任せください
 オンライン記者会見は、配信環境の整備から機材運用、当日の進行管理まで、多くの準備と専門知識が求められます。そこで頼りになるのが、国際機関や省庁、上場企業を含む1,000件以上のイベント配信を支援してきたAirzです。
オンライン記者会見は、配信環境の整備から機材運用、当日の進行管理まで、多くの準備と専門知識が求められます。そこで頼りになるのが、国際機関や省庁、上場企業を含む1,000件以上のイベント配信を支援してきたAirzです。
Airzは、会場とオンラインの両方に最適化した映像・音響環境を構築し、ZoomやYouTubeなど配信ツールの選定・設定から、機材の持ち込み・設置、当日のディレクション、アーカイブ動画の編集・納品まで一貫して対応します。記者会見のように失敗が許されない場面でも、事前リハーサルや通信テストを徹底し、機材トラブルや回線不安定のリスクを最小限に抑えます。
さらに、多カメラ構成やワイプ表示、テロップ・パターン合成などの演出にも柔軟に対応できるため、視聴者にとって見やすく、情報が正確に伝わる映像制作が可能です。同時通訳や字幕挿入にも対応しており、海外メディア向けの発信にも強みを発揮します。
「トラブルゼロ・高品質の配信」を目指すAirzなら、初めてのオンライン記者会見でも安心して任せられます。目的や規模に合わせた最適なプランの提案も受けられるので、お気軽にご相談ください。