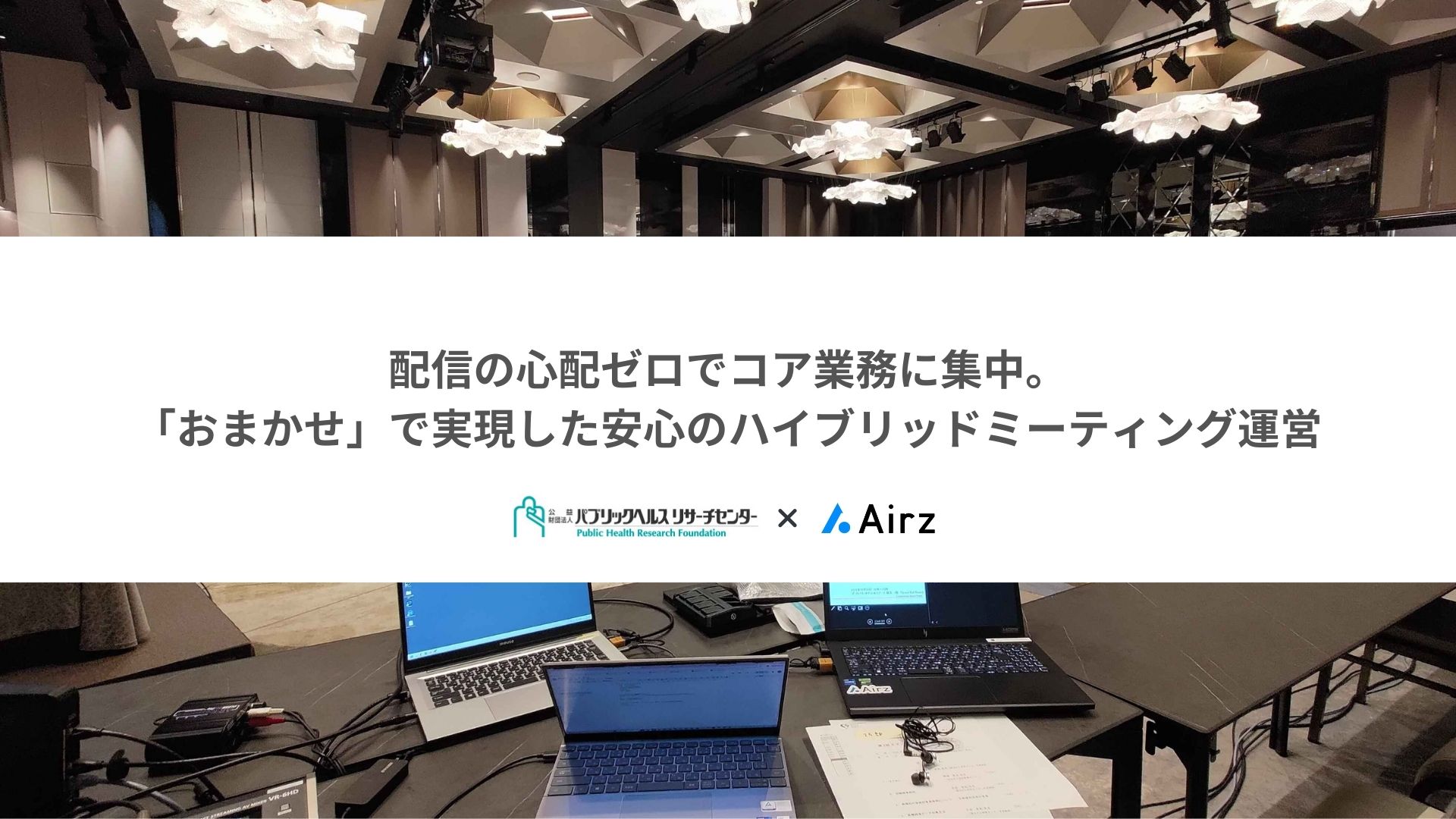バーチャル株主総会とは?種類から開催手順まで完全解説!
 更新日
更新日

バーチャル株主総会は、インターネットを活用して遠隔地からでも参加できる新しい株主総会の形です。近年、感染症対策やコスト削減の観点から多くの企業が導入を進めています。
本記事では、バーチャル株主総会の基本や種類、メリット・デメリット、具体的な開催手順までをわかりやすく解説します。バーチャル株主総会を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
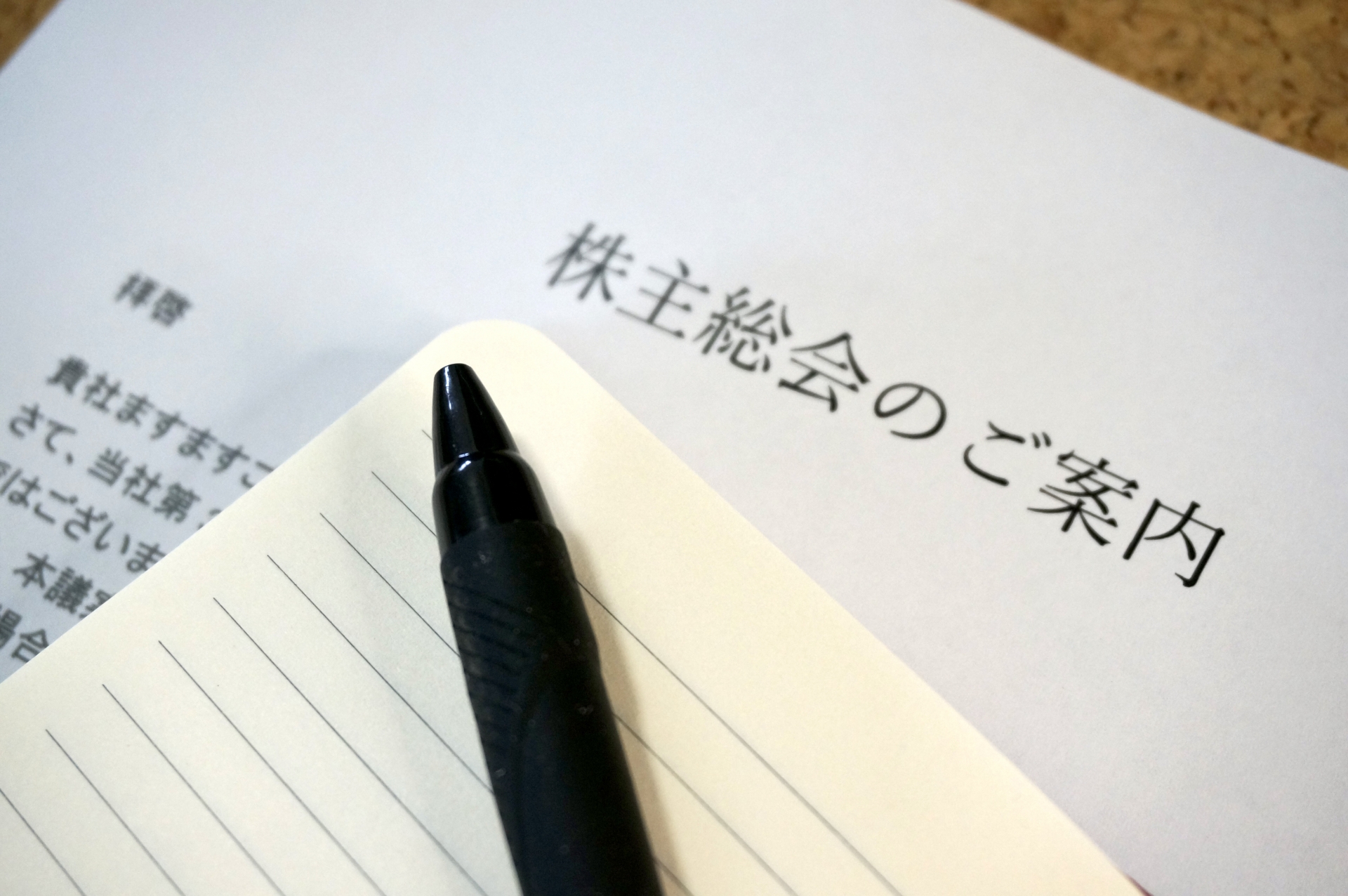 バーチャル株主総会とは、インターネットを利用して株主がオンライン上で参加・出席できる株主総会のことです。従来の株主総会は、会場に株主が集まる形式でしたが、バーチャル株主総会では自宅や職場など遠隔地からでも参加が可能になります。
バーチャル株主総会とは、インターネットを利用して株主がオンライン上で参加・出席できる株主総会のことです。従来の株主総会は、会場に株主が集まる形式でしたが、バーチャル株主総会では自宅や職場など遠隔地からでも参加が可能になります。
近年、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、多くの企業がバーチャル株主総の導入を検討しており、株主の利便性向上や感染症対策として注目されています。
 バーチャル株主総会は、開催方式によっていくつかの種類に分類されます。主要な分類として、実際の会場とオンライン参加を組み合わせた「ハイブリッド型」と、完全にオンラインで実施する「バーチャルオンリー型」があります。
バーチャル株主総会は、開催方式によっていくつかの種類に分類されます。主要な分類として、実際の会場とオンライン参加を組み合わせた「ハイブリッド型」と、完全にオンラインで実施する「バーチャルオンリー型」があります。
さらに配信方法や参加者の権限によって細かく分けられ、それぞれ異なる特徴とメリットを持っています。
2024年3月31日時点で64社・延べ108回、同年11月30日時点では71社・延べ138回の開催が確認されています。
(参照:第4回スタートアップ・DX・GXワーキンググループ資料 バーチャルオンリー総会の現状と課題について)
その性質上、開催地や移動の制約を受けずに全国や海外の株主が容易に参加できるほか、会場費などの運営コストを削減でき、感染症や災害時にも開催が可能です。
従来は、会社法298条の規定により完全バーチャル型での開催が難しいとされてきました。しかし、2021年6月の産業競争力強化法改正で「場所の定めのない株主総会」が制度化され、特定の要件を満たす上場企業に限り開催が可能となりました。
ただし、経済産業大臣と法務大臣の事前確認と定款変更が必要であり、会社法の原則どおり株主からの質問や動議を受け付ける必要があります。制度の詳細は経済産業省の制度説明ページを参照してください。
経済産業省のガイドラインでは、特定の形式を推奨しているわけではなく、各社の業態や株主構成に応じて検討すべき「追加的な選択肢」と位置づけられています。
オンライン参加には、議決権行使の有無によって「参加型」と「出席型」があります。参加型は総会の様子を視聴できるものの法的な出席とはならず、議決権も行使できません。一方、出席型は会場参加と同等に質問や議決権行使が可能で、法律上の「出席」として扱われます。
日本では書面投票や電子投票制度が整備され、多くの会社が総会前に議決権行使結果を把握していますが、オンライン出席はこうした制度の趣旨と整合を図りつつ参加機会を広げる手段として活用されます。
この形式は導入コストが比較的低く、技術的なハードルも下がるため、初めてバーチャル株主総会を実施する企業に適しています。株主にとっては、遠方からでも総会の雰囲気を感じられ、経営陣の報告や質疑応答を聞くことができるメリットがあります。
ただし、株主との直接的な対話機会が制限されるため、エンゲージメント向上の観点では課題もあります。事前に株主からの質問を受け付けて総会で回答するなど、補完的な仕組みを用意することが重要です。
株主はオンライン上で質問を投稿したり、チャット機能を使って意見を述べたりすることができます。ハイブリッド出席型やバーチャルオンリー型で採用され、従来の株主総会に近い双方向性を実現します。
この形式では、株主の参加意識が高まり、より活発な議論が期待できます。質問内容がテキスト化されることで議事録作成も効率化され、後日の検証も容易になります。
また、普段は発言しにくい株主も気軽に質問できる環境が整い、株主総会の民主化に貢献します。
株主は都合の良い時間に総会の内容を確認でき、繰り返し視聴することも可能です。主にハイブリッド型の補完サービスとして提供され、リアルタイム参加が困難な株主への配慮として活用されています。
この形式の最大のメリットは、時間的制約を完全に解消できることです。海外在住の株主や、業務の都合でリアルタイム参加が困難な株主も、後日ゆっくりと総会内容を確認できます。
また、複数の企業の株主総会が同日開催される場合でも、すべての内容をチェックすることが可能になります。企業側も、より多くの株主に情報を届けられるため、透明性向上に寄与します。
ただし、議決権行使はライブ配信中に限定されるケースが多く、純粋な情報提供手段としての位置づけが一般的です。
 バーチャル株主総会の導入は、企業と株主の双方にとって多くのメリットをもたらします。従来のリアル開催と比較して、コスト削減や参加のしやすさといった実用的な利点から、感染症対策やデジタル化推進といった社会的意義まで幅広い効果が期待できるでしょう。
バーチャル株主総会の導入は、企業と株主の双方にとって多くのメリットをもたらします。従来のリアル開催と比較して、コスト削減や参加のしやすさといった実用的な利点から、感染症対策やデジタル化推進といった社会的意義まで幅広い効果が期待できるでしょう。
ここでは、具体的なメリットについて詳しく解説していきます。
さらに移動時間の節約効果も見逃せません。会場への往復に半日から一日を要していた株主も、自宅や職場からアクセスするだけで参加可能となります。
また、身体的な制約がある方や高齢の株主にとっても、移動の負担がなくなることで参加へのハードルが大きく下がります。
大規模なホテルや会議場を借りる場合、数百万円から数千万円の費用が発生することも珍しくありませんが、バーチャル開催であればこれらの費用を大幅にカットできます。
会場設営に伴う人件費や備品レンタル費用も不要となります。従来は音響設備、照明、椅子やテーブルの配置、受付スタッフの配備など多岐にわたる準備が必要でしたが、オンライン開催では最小限の技術スタッフで対応可能です。
また録画配信により、株主は重要な発言や質疑応答の部分を繰り返し視聴することが可能となります。複雑な財務内容や事業戦略について、理解が深まるまで何度でも確認できるため、より質の高い情報提供が実現できるでしょう。
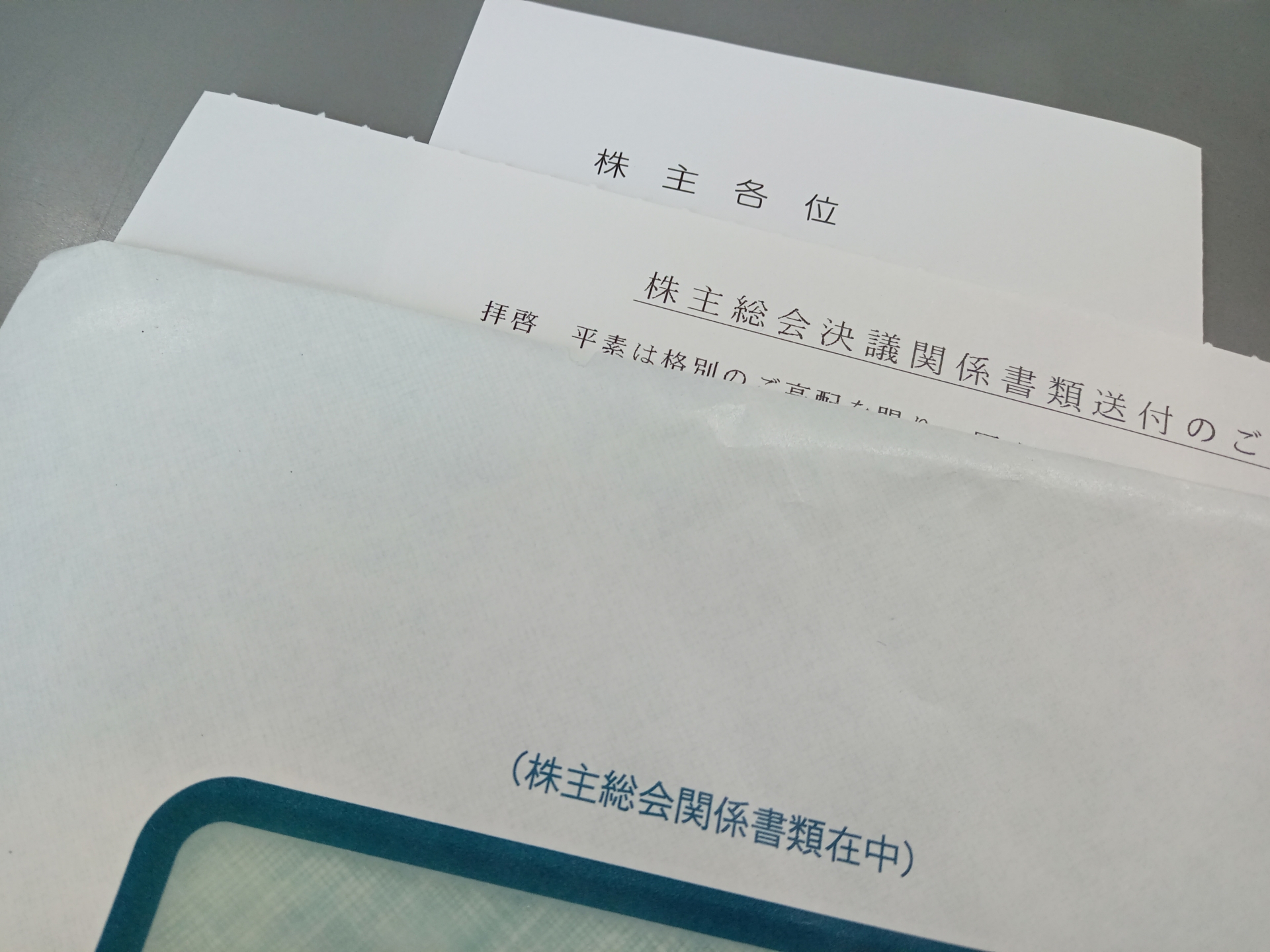 バーチャル株主総会にはメリットがある一方で、導入時に検討すべきデメリットも存在します。
バーチャル株主総会にはメリットがある一方で、導入時に検討すべきデメリットも存在します。
技術的な課題から運営面での困難まで、様々な問題点が指摘されています。これらのデメリットを事前に把握し、適切な対策を講じることが、バーチャル株主総会を成功させるためには不可欠でしょう。
また、通信環境が不安定な地域に住む株主や、十分な通信速度を確保できない環境の株主は、映像や音声が途切れるなどの問題に直面する恐れがあります。
企業側としても、想定以上の参加者がアクセスした場合のサーバー負荷や回線容量の問題に対処する必要があるでしょう。
IDやパスワードによる認証システムを導入しても、なりすましや不正アクセスのリスクを完全に排除することは難しいのが現状です。特に議決権行使を伴う出席型のバーチャル株主総会では、株主本人による適正な権利行使を確保するため、より厳格な本人確認措置が求められます。
二段階認証やブロックチェーン技術の活用なども検討されていますが、これらの導入にはコストや技術的な複雑さが伴います。また、本人確認の手続きが煩雑になりすぎると、株主の利便性を損なう結果となりかねません。
セキュリティの確保と参加のしやすさのバランスを取ることが、企業にとって重要な課題となっています。
対面での質疑応答と比べて、オンラインでは微妙なニュアンスや感情の伝達が困難になり、十分な対話が実現しにくくなる場合があるため注意が必要です。
これにより、株主の真意や詳細な意見を汲み取ることが難しくなり、建設的な議論の場としての株主総会の機能が低下する恐れがあります。
 バーチャル株主総会を成功させるためには、計画的で段階的な準備が不可欠です。従来のリアル株主総会とは異なる特有の課題があるため、技術面、法務面、運営面すべてにおいて入念な準備が求められます。
バーチャル株主総会を成功させるためには、計画的で段階的な準備が不可欠です。従来のリアル株主総会とは異なる特有の課題があるため、技術面、法務面、運営面すべてにおいて入念な準備が求められます。
開催形式の決定から当日の運営、事後処理まで、各段階で適切な対応を行うことで、株主にとって参加しやすく、企業にとっても効果的な株主総会を実現できるでしょう。
安定した回線速度と接続性能、同時接続可能人数、セキュリティレベルを重点的に評価する必要があります。株主の操作性も重要で、高齢の株主でも簡単にアクセスできるユーザーインターフェースが求められるでしょう。議決権行使機能、質問投稿機能、本人認証システムなど、開催形式に応じた必要機能を備えているかも確認が必要です。
また、システム障害やサイバー攻撃に対するリスク対策、バックアップ体制の充実度も選定基準となります。複数のベンダーから提案を受け、デモンストレーションを通じて実際の使用感を確認することが重要です。
コスト面だけでなく、セキュリティ、機能、サポート体制の充実度を総合的に判断しましょう。
特にインターネットに不慣れな株主への配慮として、書面による詳細な説明資料の同封が効果的でしょう。
事前のテスト接続機会の提供や、問い合わせ窓口の設置も重要です。招集通知の発送は、公開会社では開催日の2週間前、非公開会社では1週間前までに行う必要があります。
なお電子メールでの通知を希望する株主には、事前に承諾を得た上で電磁的方法による発送も可能です。
事前登録制にすることで、当日のアクセス集中を避け、スムーズな参加を実現できるでしょう。登録システムでは、株主の基本情報確認、議決権数の表示、事前質問の受付機能も統合します。
さらに高齢株主への配慮として、電話での登録サポートや、家族による代理登録の仕組みも検討する必要があります。
株主からの技術的問い合わせに対応する専用コールセンターの設置も必要で、十分な回線数と熟練オペレーターの確保が求められるでしょう。
加えてバックアップシステムの準備も欠かせません。メイン配信システムに障害が発生した場合の切り替え手順を明確化し、予備回線や代替配信手段を用意します。
議長や司会者への技術サポート要員も配置し、進行中のトラブルにも即座に対応できる体制を整えましょう。
リハーサルを複数回実施し、様々なトラブルシナリオでの対応訓練を行うことで、当日の安定運営を確保できます。
開始30分前には配信テストを実施し、音声・映像品質、接続状況を確認しましょう。株主の入室受付は開始15分前から開始し、本人確認と議決権数の照合を行います。
なお受付時には、株主への操作説明や注意事項の案内も重要です。質問投稿方法、議決権行使手順、技術トラブル時の対処法を分かりやすく説明します。
まず議長は画面を通じて株主とのコミュニケーションを図るため、声のトーンや話すスピードに特別な配慮が必要です。資料の画面共有機能を活用し、説明内容を視覚的に補完することで理解促進を図りましょう。
質疑応答では、事前質問と当日質問の両方に対応します。チャット機能やテキスト投稿を通じて受け付けた質問を整理し、関連性の高いものから順次回答していくと良いでしょう。
投票システムでは、各株主の議決権数を正確に反映し、重複投票の防止機能も組み込むと良いでしょう。投票期間中は進捗状況をモニタリングし、技術的問題が発生した場合の対応準備も怠らないようにしましょう。
また集計結果の発表では、賛成・反対・棄権の票数を明確に表示し、可決・否決の判定根拠も分かりやすく説明します。事前の書面投票分と当日の電子投票分を合算した最終結果を、株主が理解しやすい形で提示することが重要です。
さらに投票データの保存と監査証跡の確保も法的要件として必須となるため、システム上での適切に記録管理を行う必要があります。
 バーチャル株主総会は、開催形式や配信方法によって必要な機材や運営体制が大きく異なります。特に初めて導入する場合は、進行管理や会場設備の確認、配信ツールの設定、機材手配など、専門的な準備が欠かせず、多くの手間を取られてしまうことも少なくありません。
バーチャル株主総会は、開催形式や配信方法によって必要な機材や運営体制が大きく異なります。特に初めて導入する場合は、進行管理や会場設備の確認、配信ツールの設定、機材手配など、専門的な準備が欠かせず、多くの手間を取られてしまうことも少なくありません。
これら全てを社内だけで完結するのは難しく、外部の配信支援サービスを活用するケースが増えています。
株式会社Airz(エアーズ)は、国際機関や省庁、上場企業を含む1,000回以上の配信支援実績を持ち、ハイブリッド型から完全オンライン型まで幅広く対応可能です。
支援内容には、進行管理、会場選定、配信ツール設定、映像・音響機材の手配・設置、当日の運営サポート、アーカイブ動画の納品などが含まれます。
さらに、本人確認や通信障害対策など、バーチャル株主総会特有の課題にも対応できる体制も整えています。
大切な株主総会を確実に成功させるために、Airzのサービス活用を検討してみてはいかがでしょうか。
本記事では、バーチャル株主総会の基本や種類、メリット・デメリット、具体的な開催手順までをわかりやすく解説します。バーチャル株主総会を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
Table of Contents
バーチャル株主総会とは
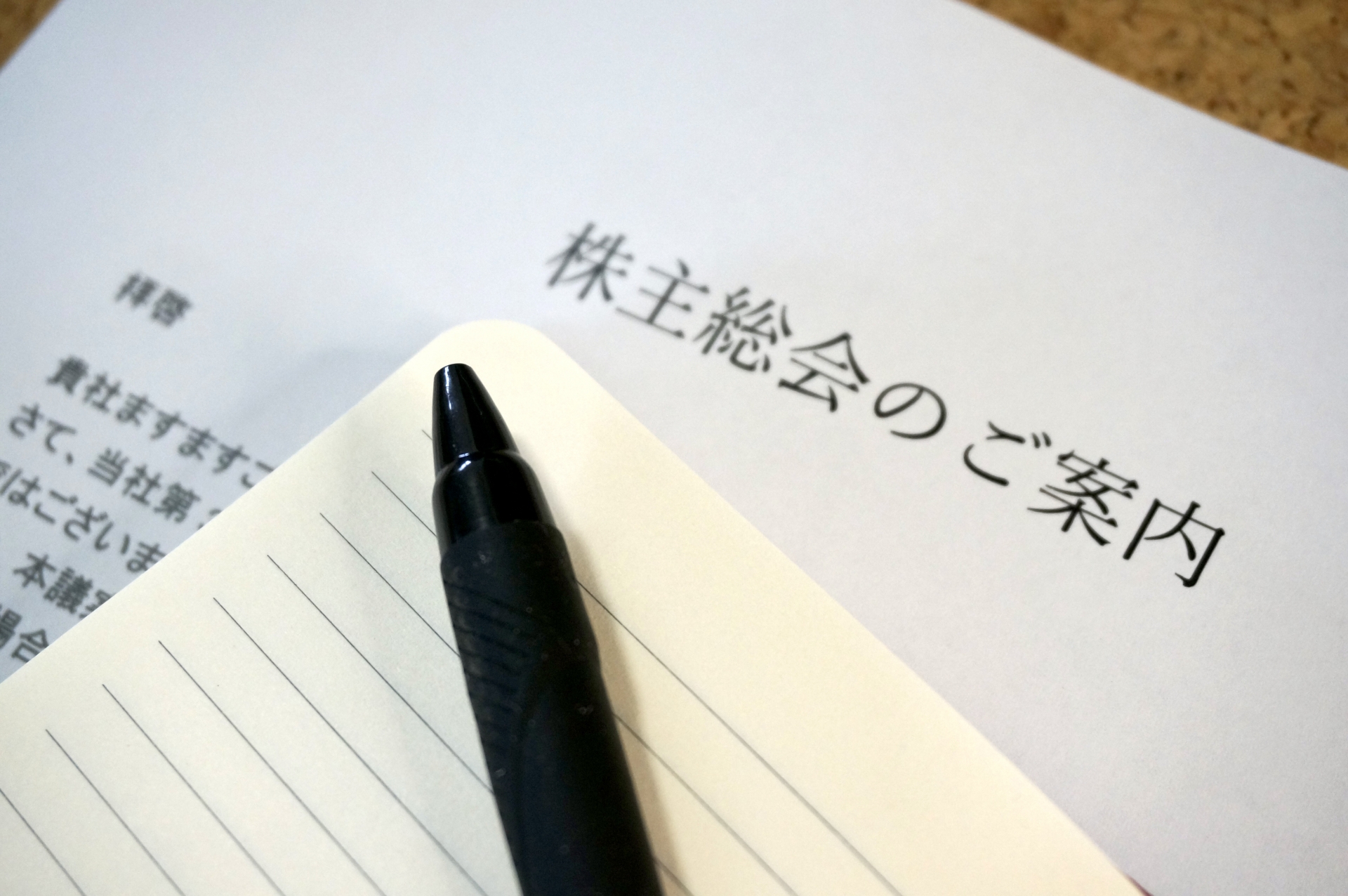 バーチャル株主総会とは、インターネットを利用して株主がオンライン上で参加・出席できる株主総会のことです。従来の株主総会は、会場に株主が集まる形式でしたが、バーチャル株主総会では自宅や職場など遠隔地からでも参加が可能になります。
バーチャル株主総会とは、インターネットを利用して株主がオンライン上で参加・出席できる株主総会のことです。従来の株主総会は、会場に株主が集まる形式でしたが、バーチャル株主総会では自宅や職場など遠隔地からでも参加が可能になります。
近年、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、多くの企業がバーチャル株主総の導入を検討しており、株主の利便性向上や感染症対策として注目されています。
バーチャル株主総会の種類
 バーチャル株主総会は、開催方式によっていくつかの種類に分類されます。主要な分類として、実際の会場とオンライン参加を組み合わせた「ハイブリッド型」と、完全にオンラインで実施する「バーチャルオンリー型」があります。
バーチャル株主総会は、開催方式によっていくつかの種類に分類されます。主要な分類として、実際の会場とオンライン参加を組み合わせた「ハイブリッド型」と、完全にオンラインで実施する「バーチャルオンリー型」があります。
さらに配信方法や参加者の権限によって細かく分けられ、それぞれ異なる特徴とメリットを持っています。
完全バーチャル型の株主総会
完全バーチャル型(バーチャルオンリー型)の株主総会は、物理的な会場を設けず、取締役や株主がすべてオンラインで出席し、議事進行や議決権行使を行う形式です。2024年3月31日時点で64社・延べ108回、同年11月30日時点では71社・延べ138回の開催が確認されています。
(参照:第4回スタートアップ・DX・GXワーキンググループ資料 バーチャルオンリー総会の現状と課題について)
その性質上、開催地や移動の制約を受けずに全国や海外の株主が容易に参加できるほか、会場費などの運営コストを削減でき、感染症や災害時にも開催が可能です。
従来は、会社法298条の規定により完全バーチャル型での開催が難しいとされてきました。しかし、2021年6月の産業競争力強化法改正で「場所の定めのない株主総会」が制度化され、特定の要件を満たす上場企業に限り開催が可能となりました。
ただし、経済産業大臣と法務大臣の事前確認と定款変更が必要であり、会社法の原則どおり株主からの質問や動議を受け付ける必要があります。制度の詳細は経済産業省の制度説明ページを参照してください。
ハイブリッド型の株主総会
ハイブリッド型の株主総会は、会場とオンライン参加を併用する形式で行う株主総会です。取締役陣は会場に集まり、株主は会場かオンラインかを選択して出席します。経済産業省のガイドラインでは、特定の形式を推奨しているわけではなく、各社の業態や株主構成に応じて検討すべき「追加的な選択肢」と位置づけられています。
オンライン参加には、議決権行使の有無によって「参加型」と「出席型」があります。参加型は総会の様子を視聴できるものの法的な出席とはならず、議決権も行使できません。一方、出席型は会場参加と同等に質問や議決権行使が可能で、法律上の「出席」として扱われます。
日本では書面投票や電子投票制度が整備され、多くの会社が総会前に議決権行使結果を把握していますが、オンライン出席はこうした制度の趣旨と整合を図りつつ参加機会を広げる手段として活用されます。
一方向配信型の株主総会
一方向配信型の株主総会は、企業から株主に向けて映像と音声を配信するのみで、株主からの発言や質問は受け付けない形式です。主にハイブリッド参加型で採用され、株主は総会の様子を視聴することはできますが、双方向のやり取りは行われません。この形式は導入コストが比較的低く、技術的なハードルも下がるため、初めてバーチャル株主総会を実施する企業に適しています。株主にとっては、遠方からでも総会の雰囲気を感じられ、経営陣の報告や質疑応答を聞くことができるメリットがあります。
ただし、株主との直接的な対話機会が制限されるため、エンゲージメント向上の観点では課題もあります。事前に株主からの質問を受け付けて総会で回答するなど、補完的な仕組みを用意することが重要です。
双方向配信型の株主総会
双方向配信型の株主総会は、企業と株主の間で相互にコミュニケーションが取れる形式です。株主はオンライン上で質問を投稿したり、チャット機能を使って意見を述べたりすることができます。ハイブリッド出席型やバーチャルオンリー型で採用され、従来の株主総会に近い双方向性を実現します。
この形式では、株主の参加意識が高まり、より活発な議論が期待できます。質問内容がテキスト化されることで議事録作成も効率化され、後日の検証も容易になります。
また、普段は発言しにくい株主も気軽に質問できる環境が整い、株主総会の民主化に貢献します。
オンデマンド配信型の株主総会
オンデマンド配信型の株主総会は、ライブ配信終了後に録画映像を視聴できる形式です。株主は都合の良い時間に総会の内容を確認でき、繰り返し視聴することも可能です。主にハイブリッド型の補完サービスとして提供され、リアルタイム参加が困難な株主への配慮として活用されています。
この形式の最大のメリットは、時間的制約を完全に解消できることです。海外在住の株主や、業務の都合でリアルタイム参加が困難な株主も、後日ゆっくりと総会内容を確認できます。
また、複数の企業の株主総会が同日開催される場合でも、すべての内容をチェックすることが可能になります。企業側も、より多くの株主に情報を届けられるため、透明性向上に寄与します。
ただし、議決権行使はライブ配信中に限定されるケースが多く、純粋な情報提供手段としての位置づけが一般的です。
バーチャル株主総会のメリット
 バーチャル株主総会の導入は、企業と株主の双方にとって多くのメリットをもたらします。従来のリアル開催と比較して、コスト削減や参加のしやすさといった実用的な利点から、感染症対策やデジタル化推進といった社会的意義まで幅広い効果が期待できるでしょう。
バーチャル株主総会の導入は、企業と株主の双方にとって多くのメリットをもたらします。従来のリアル開催と比較して、コスト削減や参加のしやすさといった実用的な利点から、感染症対策やデジタル化推進といった社会的意義まで幅広い効果が期待できるでしょう。
ここでは、具体的なメリットについて詳しく解説していきます。
参加者の移動コストが削減される
バーチャル株主総会では、株主が会場まで足を運ぶ必要がなくなるため、交通費や宿泊費といった移動に関するコストを大幅に削減できます。特に遠方に住む株主にとって、従来は数万円かかっていた移動費用が一切不要となることは大きな経済的メリットといえるでしょう。さらに移動時間の節約効果も見逃せません。会場への往復に半日から一日を要していた株主も、自宅や職場からアクセスするだけで参加可能となります。
また、身体的な制約がある方や高齢の株主にとっても、移動の負担がなくなることで参加へのハードルが大きく下がります。
会場費用などの開催費用が安い
企業側にとって最も大きなメリットの一つが、会場レンタル費用の削減です。大規模なホテルや会議場を借りる場合、数百万円から数千万円の費用が発生することも珍しくありませんが、バーチャル開催であればこれらの費用を大幅にカットできます。
会場設営に伴う人件費や備品レンタル費用も不要となります。従来は音響設備、照明、椅子やテーブルの配置、受付スタッフの配備など多岐にわたる準備が必要でしたが、オンライン開催では最小限の技術スタッフで対応可能です。
録画配信で後から視聴可能
リアルタイムでの参加が困難な株主に対して、録画配信によるアーカイブ視聴機能を提供できることも大きなメリットです。仕事や家庭の事情で当日参加できない株主も、後日自分の都合の良い時間に総会の内容を確認できるようになります。また録画配信により、株主は重要な発言や質疑応答の部分を繰り返し視聴することが可能となります。複雑な財務内容や事業戦略について、理解が深まるまで何度でも確認できるため、より質の高い情報提供が実現できるでしょう。
バーチャル株主総会のデメリット
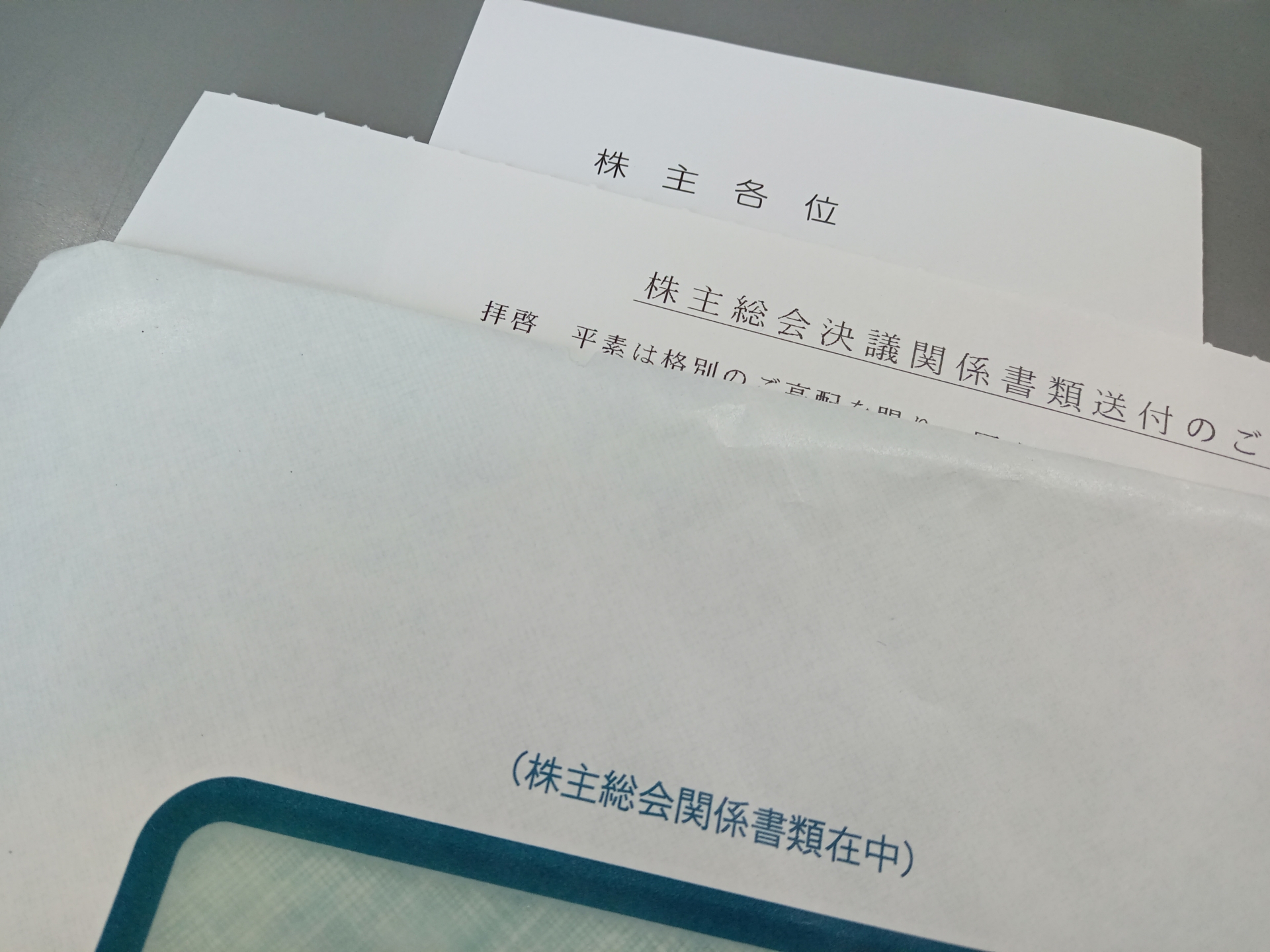 バーチャル株主総会にはメリットがある一方で、導入時に検討すべきデメリットも存在します。
バーチャル株主総会にはメリットがある一方で、導入時に検討すべきデメリットも存在します。
技術的な課題から運営面での困難まで、様々な問題点が指摘されています。これらのデメリットを事前に把握し、適切な対策を講じることが、バーチャル株主総会を成功させるためには不可欠でしょう。
安定したインターネット環境が必要になる
バーチャル株主総会への参加には、安定したインターネット環境が必須条件となります。特に高齢の株主など、デジタル機器に慣れ親しんでいない方にとって、この技術的ハードルは参加を阻む大きな要因となる可能性があります。また、通信環境が不安定な地域に住む株主や、十分な通信速度を確保できない環境の株主は、映像や音声が途切れるなどの問題に直面する恐れがあります。
企業側としても、想定以上の参加者がアクセスした場合のサーバー負荷や回線容量の問題に対処する必要があるでしょう。
本人確認が困難な場合がある
オンライン環境では、参加者の本人確認が従来の対面形式と比べて困難になります。IDやパスワードによる認証システムを導入しても、なりすましや不正アクセスのリスクを完全に排除することは難しいのが現状です。特に議決権行使を伴う出席型のバーチャル株主総会では、株主本人による適正な権利行使を確保するため、より厳格な本人確認措置が求められます。
二段階認証やブロックチェーン技術の活用なども検討されていますが、これらの導入にはコストや技術的な複雑さが伴います。また、本人確認の手続きが煩雑になりすぎると、株主の利便性を損なう結果となりかねません。
セキュリティの確保と参加のしやすさのバランスを取ることが、企業にとって重要な課題となっています。
直接的な対話機会が減る
バーチャル株主総会では、株主と経営陣との直接的なコミュニケーションが制限される傾向があります。対面での質疑応答と比べて、オンラインでは微妙なニュアンスや感情の伝達が困難になり、十分な対話が実現しにくくなる場合があるため注意が必要です。
これにより、株主の真意や詳細な意見を汲み取ることが難しくなり、建設的な議論の場としての株主総会の機能が低下する恐れがあります。
バーチャル株主総会の開催手順
 バーチャル株主総会を成功させるためには、計画的で段階的な準備が不可欠です。従来のリアル株主総会とは異なる特有の課題があるため、技術面、法務面、運営面すべてにおいて入念な準備が求められます。
バーチャル株主総会を成功させるためには、計画的で段階的な準備が不可欠です。従来のリアル株主総会とは異なる特有の課題があるため、技術面、法務面、運営面すべてにおいて入念な準備が求められます。
開催形式の決定から当日の運営、事後処理まで、各段階で適切な対応を行うことで、株主にとって参加しやすく、企業にとっても効果的な株主総会を実現できるでしょう。
配信プラットフォームを選定する
配信プラットフォームの選定は、バーチャル株主総会の成功を左右する重要な要素です。安定した回線速度と接続性能、同時接続可能人数、セキュリティレベルを重点的に評価する必要があります。株主の操作性も重要で、高齢の株主でも簡単にアクセスできるユーザーインターフェースが求められるでしょう。議決権行使機能、質問投稿機能、本人認証システムなど、開催形式に応じた必要機能を備えているかも確認が必要です。
また、システム障害やサイバー攻撃に対するリスク対策、バックアップ体制の充実度も選定基準となります。複数のベンダーから提案を受け、デモンストレーションを通じて実際の使用感を確認することが重要です。
コスト面だけでなく、セキュリティ、機能、サポート体制の充実度を総合的に判断しましょう。
株主への事前通知を行う
バーチャル株主総会の開催には、従来の招集通知に加えて、オンライン参加に関する詳細な情報提供が必要です。配信サイトのURL、アクセス方法、必要な機器・環境、操作手順書を分かりやすく記載しなければなりません。特にインターネットに不慣れな株主への配慮として、書面による詳細な説明資料の同封が効果的でしょう。
事前のテスト接続機会の提供や、問い合わせ窓口の設置も重要です。招集通知の発送は、公開会社では開催日の2週間前、非公開会社では1週間前までに行う必要があります。
なお電子メールでの通知を希望する株主には、事前に承諾を得た上で電磁的方法による発送も可能です。
参加登録システムを構築する
オンライン参加者の本人確認と参加管理のため、専用の登録システム構築が必要です。株主番号とパスワードによる認証システム、二段階認証の導入により、なりすまし防止とセキュリティ強化を図ります。事前登録制にすることで、当日のアクセス集中を避け、スムーズな参加を実現できるでしょう。登録システムでは、株主の基本情報確認、議決権数の表示、事前質問の受付機能も統合します。
さらに高齢株主への配慮として、電話での登録サポートや、家族による代理登録の仕組みも検討する必要があります。
当日の技術サポート体制を整備
バーチャル株主総会当日は、技術的トラブルに迅速対応できる体制構築が重要です。専門技術者を配置し、配信システムの監視、音声・映像品質の確認、接続トラブルへの対応を行います。株主からの技術的問い合わせに対応する専用コールセンターの設置も必要で、十分な回線数と熟練オペレーターの確保が求められるでしょう。
加えてバックアップシステムの準備も欠かせません。メイン配信システムに障害が発生した場合の切り替え手順を明確化し、予備回線や代替配信手段を用意します。
議長や司会者への技術サポート要員も配置し、進行中のトラブルにも即座に対応できる体制を整えましょう。
リハーサルを複数回実施し、様々なトラブルシナリオでの対応訓練を行うことで、当日の安定運営を確保できます。
配信開始と株主の受付開始
株主総会の開始前には、配信システムの最終チェックと株主の受付業務を並行して進めます。開始30分前には配信テストを実施し、音声・映像品質、接続状況を確認しましょう。株主の入室受付は開始15分前から開始し、本人確認と議決権数の照合を行います。
なお受付時には、株主への操作説明や注意事項の案内も重要です。質問投稿方法、議決権行使手順、技術トラブル時の対処法を分かりやすく説明します。
議事進行と質疑応答を実施
バーチャル株主総会の議事進行では、従来の株主総会以上に明確で分かりやすい進行が求められます。まず議長は画面を通じて株主とのコミュニケーションを図るため、声のトーンや話すスピードに特別な配慮が必要です。資料の画面共有機能を活用し、説明内容を視覚的に補完することで理解促進を図りましょう。
質疑応答では、事前質問と当日質問の両方に対応します。チャット機能やテキスト投稿を通じて受け付けた質問を整理し、関連性の高いものから順次回答していくと良いでしょう。
電子投票の集計と結果発表
バーチャル株主総会における電子投票は、リアルタイムでの集計と迅速な結果発表が可能です。投票システムでは、各株主の議決権数を正確に反映し、重複投票の防止機能も組み込むと良いでしょう。投票期間中は進捗状況をモニタリングし、技術的問題が発生した場合の対応準備も怠らないようにしましょう。
また集計結果の発表では、賛成・反対・棄権の票数を明確に表示し、可決・否決の判定根拠も分かりやすく説明します。事前の書面投票分と当日の電子投票分を合算した最終結果を、株主が理解しやすい形で提示することが重要です。
さらに投票データの保存と監査証跡の確保も法的要件として必須となるため、システム上での適切に記録管理を行う必要があります。
バーチャル株主総会はAirzにお任せください
 バーチャル株主総会は、開催形式や配信方法によって必要な機材や運営体制が大きく異なります。特に初めて導入する場合は、進行管理や会場設備の確認、配信ツールの設定、機材手配など、専門的な準備が欠かせず、多くの手間を取られてしまうことも少なくありません。
バーチャル株主総会は、開催形式や配信方法によって必要な機材や運営体制が大きく異なります。特に初めて導入する場合は、進行管理や会場設備の確認、配信ツールの設定、機材手配など、専門的な準備が欠かせず、多くの手間を取られてしまうことも少なくありません。
これら全てを社内だけで完結するのは難しく、外部の配信支援サービスを活用するケースが増えています。
株式会社Airz(エアーズ)は、国際機関や省庁、上場企業を含む1,000回以上の配信支援実績を持ち、ハイブリッド型から完全オンライン型まで幅広く対応可能です。
支援内容には、進行管理、会場選定、配信ツール設定、映像・音響機材の手配・設置、当日の運営サポート、アーカイブ動画の納品などが含まれます。
さらに、本人確認や通信障害対策など、バーチャル株主総会特有の課題にも対応できる体制も整えています。
大切な株主総会を確実に成功させるために、Airzのサービス活用を検討してみてはいかがでしょうか。