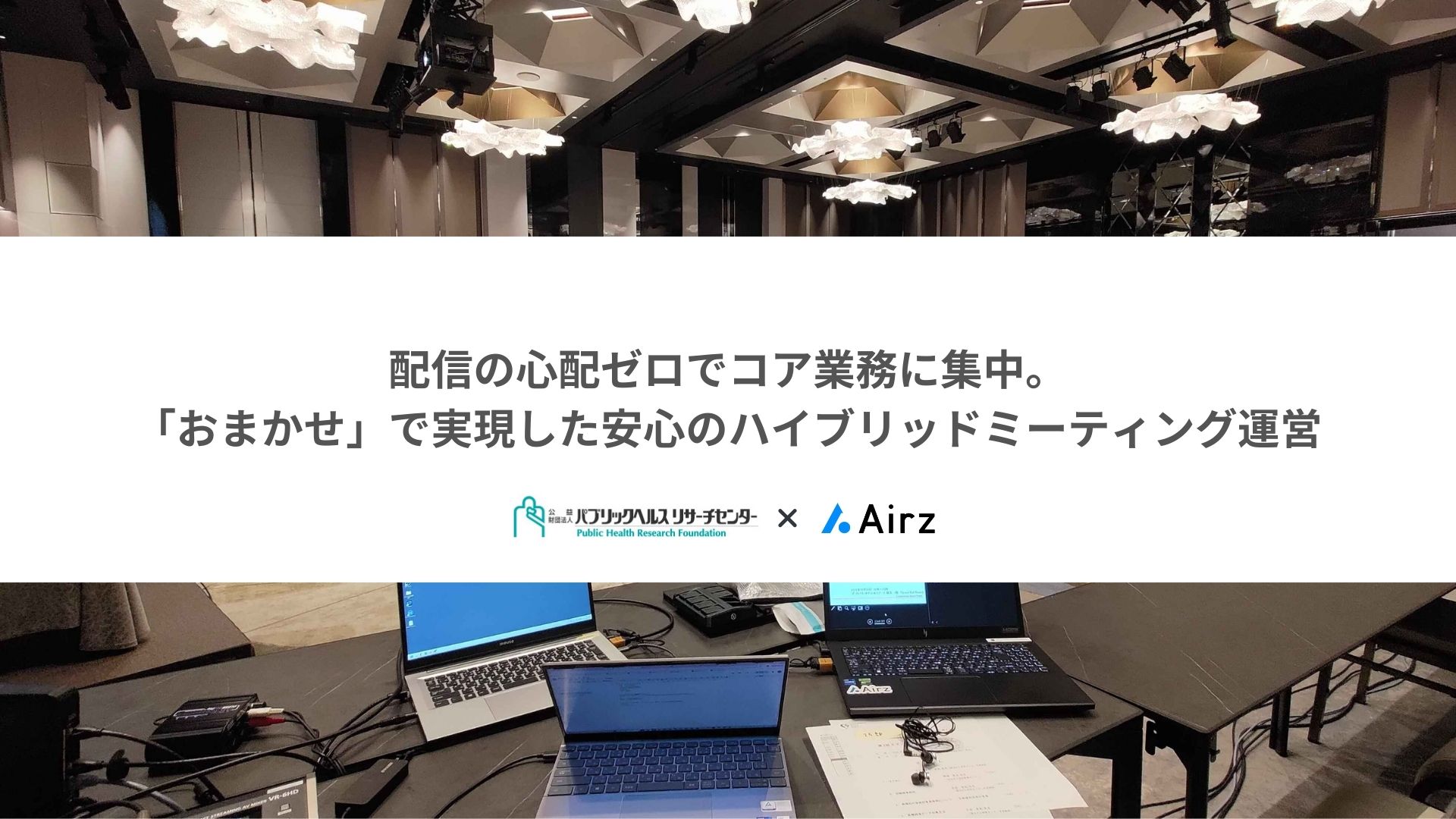【完全比較】配信形式の違いと選び方|ライブ・オンデマンド・ダウンロードなどを徹底解説
 更新日
更新日

動画や音声コンテンツが身近になった今、どの「配信形式」を選ぶかは成果を大きく左右します。
ライブ配信、オンデマンド、ストリーミング、ダウンロード、インタラクティブ配信など、多様な形式にはそれぞれ異なる特性やメリット・デメリットがあります。
本記事では、主要な配信形式の基本や特徴をわかりやすく整理し、目的に応じた選び方や配信品質を高めるためのポイントまで解説します。ぜひ最適な配信方法を検討する際の参考にしてください。
 配信形式とは、インターネット上で動画や音声コンテンツを視聴者に届けるための技術的な仕組みや方法を指します。
配信形式とは、インターネット上で動画や音声コンテンツを視聴者に届けるための技術的な仕組みや方法を指します。
現在の動画配信業界では、主にライブ配信、オンデマンド配信、ストリーミング配信、ダウンロード配信、インタラクティブ配信の5つの形式が使われています。それぞれの配信形式には独自の特徴があり、配信の目的や視聴環境、技術的要件に応じて最適な選択が必要です。
配信日時があらかじめ決まっているため、オンデマンド配信と比較して高い視聴率を期待できます。
この配信形式では、最新情報の素早い伝達や均質な情報共有が可能になり、視聴者との関係性強化にも効果的です。企業の製品発表会やウェビナー、個人配信者によるゲーム実況など、幅広い分野で活用されています。
視聴者は一時停止や再生速度の変更、繰り返し視聴といった機能を活用でき、学習コンテンツや研修動画などで特に重宝されています。
YouTubeやNetflixなどの動画プラットフォームで広く採用されている配信形式といえます。
現在の動画配信サービスにおいて最も主流となっている技術です。この配信方式では、視聴者のネットワーク環境に応じて自動的に画質を調整する「アダプティブビットレート機能」が搭載されており、安定した視聴体験を実現します。
また、動画ファイルが視聴者の端末に完全にダウンロードされないため、著作権保護の観点からも優れています。
インターネット接続が不安定な環境や、オフラインでの視聴を前提とした場合に適している配信方法といえます。
一度ダウンロードが完了すれば、ネットワーク環境に左右されることなく高品質な映像を楽しめるでしょう。教育コンテンツや企業研修動画など、重要な情報を確実に伝達したい場合に重宝されます。
視聴者の参加意識を高め、エンゲージメントの向上に効果的です。この配信形式では、視聴者からのコメントや質問に配信者がリアルタイムで応答したり、アンケート結果を即座に共有したりできます。
ウェビナーやオンライン授業、ライブコマースなどの分野で特に注目されており、参加者同士の交流も促進できるでしょう。

配信形式にはそれぞれ異なる特徴があり、目的や用途に応じて最適な形式を選択することが重要です。ここでは、各配信形式の具体的なメリットについて詳しく解説していきます。
実際に多くの企業では、製品発表会や株主総会などの重要なイベントでライブ配信を活用しています。視聴者からのコメントや質問にその場で回答できるため、双方向のコミュニケーションが生まれ、視聴者の満足度向上につながります。
また、生放送特有の緊張感や一回性が、視聴者の注目度を高める効果も期待できます。ライブ配信では最新情報を素早く伝達できるため、ニュース配信や緊急事態の情報共有にも適しています。
この形式では、一時停止や巻き戻し、再生速度の変更も自由に行えるため、学習効果の向上が期待できるでしょう。特に研修動画や教育コンテンツでは、理解が難しい部分を繰り返し視聴したり、重要なポイントでメモを取ったりできるため、視聴者の理解度が大幅に向上します。
配信者側にとっても、事前に動画を完成させておけるため、内容をしっかりと作り込めるといったメリットがあります。
HTTPベースで動作するストリーミングは、一般的なWebサーバーやCDNで配信できるため、大規模な配信にも対応しやすい特徴があります。また、アダプティブビットレート機能により、視聴者のネットワーク環境に応じて自動的に画質が調整され、途切れのない視聴体験を提供できます。
さらに、視聴データの分析も容易で、マーケティング活動にも活用できる点が企業にとって大きな価値となります。
特に教育分野では、この特性が大きな価値を持ちます。研修動画や講義コンテンツをあらかじめダウンロードしておけば、通勤時間や休憩時間などの隙間時間を有効活用して学習を進められます。
また、通信量を気にする必要がないため、長時間の動画でも安心して視聴できます。
インタラクティブ配信は、特にライブイベントやウェビナーに向いています。講演中に視聴者から質問を受け付けたり、アンケート機能を使って即座に意見を集約したりできるため、参加型のイベント運営が可能になります。
エンゲージメントの向上により、ブランドロイヤリティの構築や長期的な顧客関係の構築にも大きく貢献する配信形式といえるでしょう。
 動画配信には様々な配信形式があり、それぞれにデメリットも存在します。ここでは、主要な配信形式におけるデメリットを詳しく解説していきます。
動画配信には様々な配信形式があり、それぞれにデメリットも存在します。ここでは、主要な配信形式におけるデメリットを詳しく解説していきます。
特に複数のカメラを使用する場合や、スイッチャーを介した映像切り替えを行う際は、トラブルの発生確率が高まります。
また、インターネット回線の不安定さも大きな課題となるでしょう。配信中に回線が切断されると、視聴者への配信が停止し、復旧まで時間を要することがあります。
視聴者は好きな時間にコンテンツを視聴できる一方で、配信者との双方向コミュニケーションは難しく、質疑応答やチャットでのやり取りができないため、参加型のイベントには向きません。
さらに、情報の鮮度という点でも課題があり、ニュースや時事問題を扱うコンテンツでは、配信時点の情報がすぐに古くなってしまう可能性もあります。
インターネット回線速度が不十分な場合、動画の読み込みが遅くなったり、再生が途中で止まったりする問題が発生します。特にモバイル回線を使用している視聴者では、データ通信量の制限により画質が自動的に低下することもあります。
さらに、ネットワークの混雑時間帯では、他のインターネットトラフィックの影響を受けやすく、安定した配信が困難になることがあります。
特に長時間のセミナーや研修動画では、ファイルサイズが非常に大きくなり、ダウンロードに時間がかかることもあります。ダウンロード完了まで視聴を開始できないため、即座に内容を確認したい視聴者にとってはストレスとなるでしょう。
チャット機能やQ&A機能を活用する場合、専任のモデレーターが必要となり、人的リソースの確保が課題となります。特に大規模なイベントでは、多数のコメントや質問に対応するため、複数のスタッフが必要です。
また、不適切なコメントや荒らし行為への対応も重要な課題の一つです。事前のガイドライン策定や、リアルタイムでの監視体制構築が必要になります。
 動画配信を成功させるには、ただ配信するだけでなく、配信の目的に合った形式を選ぶことが非常に重要です。形式によって、視聴者との接し方や参加のしやすさ、情報の伝わり方が大きく変わるためです。
動画配信を成功させるには、ただ配信するだけでなく、配信の目的に合った形式を選ぶことが非常に重要です。形式によって、視聴者との接し方や参加のしやすさ、情報の伝わり方が大きく変わるためです。
ここでは、具体的な配信目的ごとに最適な形式を詳しくご紹介します。目的に合わせた形式選びのポイントを押さえることで、より効果的で視聴者に届く動画配信を実現できます。
学習者は自分のペースで内容を理解する必要があるため、一時停止や巻き戻し、繰り返し視聴ができるオンデマンド配信の特性は、学習効果を大幅に向上させます。実際、多くの企業研修や大学のオンライン講義でも、オンデマンド配信が採用されています。
受講者は通勤時間や昼休みなど、自分の都合に合わせて学習を進められるため、継続的な学習が促進されます。また、理解が難しい箇所も何度でも視聴できるため、個人の理解度に応じた柔軟な学習が可能です。
さらに、オンデマンド配信では事前に動画を制作できるため、内容の品質を十分に検討し、編集によってわかりやすい構成に仕上げることができます。テロップや図表の挿入、章立てなどの工夫を加えることで、学習者の理解をより深める配信が実現できるでしょう。
ライブ配信では、視聴者がチャット機能を通じて配信者と直接やり取りできるため、従来のテレビ番組では味わえない参加感を提供できます。この双方向性により、視聴者はコンテンツの一部として参加している感覚を得られ、エンゲージメントが大幅に向上します。
さらに、ライブ配信特有の「今この瞬間しか見られない」という希少性は、視聴者の集中度を高める効果があります。予期しないハプニングや自然な反応が生まれやすく、コンテンツの魅力を一層高めてくれるでしょう。
インタラクティブ配信では、商品のデモンストレーションを行いながら、視聴者が気になるポイントをその場で確認できます。たとえば、化粧品の配信では色味や質感、家電製品では操作方法や機能について、視聴者の知りたい情報を即座に提供可能です。
さらに、限定特典やタイムセールなどの要素を組み合わせることで、視聴者の購買行動を促進する効果も期待できます。
ストリーミング配信では、CDN(コンテンツデリバリーネットワーク)を活用することで、世界中の視聴者に高品質な映像を届けることが可能です。視聴者の地理的な位置に関係なく快適な視聴体験を提供できるため、グローバルなイベントや発表会に適しています。
さらに、ストリーミング配信では、視聴者のデバイスや通信環境に応じて自動的に画質を調整するアダプティブビットレート機能が利用できます。これにより、スマートフォン、PC、タブレットなど、さまざまなデバイスで安定して視聴可能です。
動画ファイルを視聴者のデバイスに保存して視聴するため、インターネット接続が不安定な環境でも途切れることなく視聴できます。企業の機密情報を含む研修動画や有料コンテンツの配信において、この特性は非常に価値があります。
さらに、DRM(デジタル著作権管理)技術と組み合わせることで、不正コピーや転載を防止でき、知的財産の保護も実現可能です。
 配信形式はさまざまなスタイルがあり、目的や規模によって適している配信形式が大きく変わります。それぞれの特徴とメリット・デメリットを理解した上で、最適な配信形式を選びましょう。
配信形式はさまざまなスタイルがあり、目的や規模によって適している配信形式が大きく変わります。それぞれの特徴とメリット・デメリットを理解した上で、最適な配信形式を選びましょう。
Airzは1,000回以上の配信支援実績を持ち、セミナー・学会・株主総会・国際会議・商品発表会など多彩な案件を成功に導いてきました。ZoomやWebex、YouTube、Teamsなど全主要ツールに対応し、会場手配から機材準備、テクニカルリハーサル、当日のオペレーション、アーカイブ作成までワンストップで対応可能です。
さらに、双方向音声や高画質映像の安定出力、バーチャルスタジオによる演出など、Airzならではの技術力と演出力で、初めての配信から大規模イベントまで安心して任せられます。
目的に最適な配信形式と運営プランを提案し、主催者・参加者双方が満足できるイベントを実現します。気になる方は、ぜひAirzへご相談ください。
ライブ配信、オンデマンド、ストリーミング、ダウンロード、インタラクティブ配信など、多様な形式にはそれぞれ異なる特性やメリット・デメリットがあります。
本記事では、主要な配信形式の基本や特徴をわかりやすく整理し、目的に応じた選び方や配信品質を高めるためのポイントまで解説します。ぜひ最適な配信方法を検討する際の参考にしてください。
Table of Contents
配信形式とは?基本概念と種類の解説
 配信形式とは、インターネット上で動画や音声コンテンツを視聴者に届けるための技術的な仕組みや方法を指します。
配信形式とは、インターネット上で動画や音声コンテンツを視聴者に届けるための技術的な仕組みや方法を指します。
現在の動画配信業界では、主にライブ配信、オンデマンド配信、ストリーミング配信、ダウンロード配信、インタラクティブ配信の5つの形式が使われています。それぞれの配信形式には独自の特徴があり、配信の目的や視聴環境、技術的要件に応じて最適な選択が必要です。
ライブ配信の特徴
ライブ配信は、リアルタイムで映像や音声を視聴者に届ける配信形式です。「インターネット生放送」や「インターネット生中継」とも呼ばれ、配信者と視聴者が同じ時間を共有できる点が最大の魅力といえるでしょう。配信日時があらかじめ決まっているため、オンデマンド配信と比較して高い視聴率を期待できます。
この配信形式では、最新情報の素早い伝達や均質な情報共有が可能になり、視聴者との関係性強化にも効果的です。企業の製品発表会やウェビナー、個人配信者によるゲーム実況など、幅広い分野で活用されています。
オンデマンド配信の特徴
オンデマンド配信は、事前に制作した動画をサーバーにアップロードし、視聴者がいつでも好きなタイミングで視聴できるようにする配信形式です。配信前に動画を完成させるため、収録のやり直しや編集による品質向上が可能で、より完成度の高いコンテンツを配信できるでしょう。視聴者は一時停止や再生速度の変更、繰り返し視聴といった機能を活用でき、学習コンテンツや研修動画などで特に重宝されています。
YouTubeやNetflixなどの動画プラットフォームで広く採用されている配信形式といえます。
ストリーミング配信の特徴
ストリーミング配信は、動画データを視聴者の端末にダウンロードしながら同時に再生する配信形式です。データを受信すると同時に視聴が開始されるため、大容量の動画ファイルでも待機時間なく視聴を始められます。現在の動画配信サービスにおいて最も主流となっている技術です。この配信方式では、視聴者のネットワーク環境に応じて自動的に画質を調整する「アダプティブビットレート機能」が搭載されており、安定した視聴体験を実現します。
また、動画ファイルが視聴者の端末に完全にダウンロードされないため、著作権保護の観点からも優れています。
ダウンロード配信の特徴
ダウンロード配信は、動画ファイル全体を視聴者の端末に保存してから再生する配信形式です。インターネット接続が不安定な環境や、オフラインでの視聴を前提とした場合に適している配信方法といえます。
一度ダウンロードが完了すれば、ネットワーク環境に左右されることなく高品質な映像を楽しめるでしょう。教育コンテンツや企業研修動画など、重要な情報を確実に伝達したい場合に重宝されます。
インタラクティブ配信の特徴
インタラクティブ配信は、視聴者が配信内容に対してリアルタイムで反応や参加ができる双方向性を持った配信形式です。チャット機能や投票機能、質疑応答システムなどを組み合わせることで、従来の一方向的な動画配信を超えた体験を提供します。視聴者の参加意識を高め、エンゲージメントの向上に効果的です。この配信形式では、視聴者からのコメントや質問に配信者がリアルタイムで応答したり、アンケート結果を即座に共有したりできます。
ウェビナーやオンライン授業、ライブコマースなどの分野で特に注目されており、参加者同士の交流も促進できるでしょう。
配信形式別のメリット

配信形式にはそれぞれ異なる特徴があり、目的や用途に応じて最適な形式を選択することが重要です。ここでは、各配信形式の具体的なメリットについて詳しく解説していきます。
ライブ配信はリアルタイム感がある
ライブ配信の最大の魅力は、配信者と視聴者が同じ時間を共有できるリアルタイム性にあります。この特性により、視聴者は「今この瞬間に起きていることを見ている」という臨場感を味わえるでしょう。実際に多くの企業では、製品発表会や株主総会などの重要なイベントでライブ配信を活用しています。視聴者からのコメントや質問にその場で回答できるため、双方向のコミュニケーションが生まれ、視聴者の満足度向上につながります。
また、生放送特有の緊張感や一回性が、視聴者の注目度を高める効果も期待できます。ライブ配信では最新情報を素早く伝達できるため、ニュース配信や緊急事態の情報共有にも適しています。
オンデマンド配信は視聴者の都合に合わせられる
オンデマンド配信は、視聴者が自分の都合の良いタイミングで動画を視聴できる点が最大のメリットです。24時間いつでもアクセス可能なため、時差のある海外の視聴者や、忙しいビジネスパーソンでも無理なく視聴できます。この形式では、一時停止や巻き戻し、再生速度の変更も自由に行えるため、学習効果の向上が期待できるでしょう。特に研修動画や教育コンテンツでは、理解が難しい部分を繰り返し視聴したり、重要なポイントでメモを取ったりできるため、視聴者の理解度が大幅に向上します。
配信者側にとっても、事前に動画を完成させておけるため、内容をしっかりと作り込めるといったメリットがあります。
ストリーミング配信は容量を気にしなくて良い
ストリーミング配信では、視聴者の端末に動画ファイル全体をダウンロードする必要がないため、デバイスの容量を気にせずに視聴できます。特に大容量の高画質動画でも、ストレージ容量の制約を受けることなく楽しめるでしょう。HTTPベースで動作するストリーミングは、一般的なWebサーバーやCDNで配信できるため、大規模な配信にも対応しやすい特徴があります。また、アダプティブビットレート機能により、視聴者のネットワーク環境に応じて自動的に画質が調整され、途切れのない視聴体験を提供できます。
さらに、視聴データの分析も容易で、マーケティング活動にも活用できる点が企業にとって大きな価値となります。
ダウンロード配信はオフライン視聴が可能
ダウンロード配信の最大のメリットは、一度ダウンロードすれば、インターネット接続がない環境でも動画を視聴できることです。移動中の電車内や飛行機の中、通信環境が不安定な場所でも、快適に動画を楽しめるでしょう。特に教育分野では、この特性が大きな価値を持ちます。研修動画や講義コンテンツをあらかじめダウンロードしておけば、通勤時間や休憩時間などの隙間時間を有効活用して学習を進められます。
また、通信量を気にする必要がないため、長時間の動画でも安心して視聴できます。
インタラクティブ配信は視聴者との交流ができる
インタラクティブ配信では、視聴者が配信内容に能動的に参加できるため、従来の一方向的な動画視聴とは全く異なる体験を提供できます。リアルタイムでのコメントやチャット機能により、視聴者同士のコミュニケーションも活発になるでしょう。インタラクティブ配信は、特にライブイベントやウェビナーに向いています。講演中に視聴者から質問を受け付けたり、アンケート機能を使って即座に意見を集約したりできるため、参加型のイベント運営が可能になります。
エンゲージメントの向上により、ブランドロイヤリティの構築や長期的な顧客関係の構築にも大きく貢献する配信形式といえるでしょう。
配信形式別のデメリット
 動画配信には様々な配信形式があり、それぞれにデメリットも存在します。ここでは、主要な配信形式におけるデメリットを詳しく解説していきます。
動画配信には様々な配信形式があり、それぞれにデメリットも存在します。ここでは、主要な配信形式におけるデメリットを詳しく解説していきます。
ライブ配信は機材トラブルのリスクがある
ライブ配信の最大のデメリットは、配信中に発生する機材トラブルのリスクです。カメラの故障、マイクの音声途切れ、エンコーダーの不具合など、様々な機器で問題が生じる可能性があります。特に複数のカメラを使用する場合や、スイッチャーを介した映像切り替えを行う際は、トラブルの発生確率が高まります。
また、インターネット回線の不安定さも大きな課題となるでしょう。配信中に回線が切断されると、視聴者への配信が停止し、復旧まで時間を要することがあります。
オンデマンド配信はリアルタイム感に欠ける
オンデマンド配信の大きなデメリットは、リアルタイム性がない点です。視聴者は好きな時間にコンテンツを視聴できる一方で、配信者との双方向コミュニケーションは難しく、質疑応答やチャットでのやり取りができないため、参加型のイベントには向きません。
さらに、情報の鮮度という点でも課題があり、ニュースや時事問題を扱うコンテンツでは、配信時点の情報がすぐに古くなってしまう可能性もあります。
ストリーミング配信は通信環境に依存する
ストリーミング配信は視聴者の通信環境に大きく依存するため、安定した視聴体験を保証できません。インターネット回線速度が不十分な場合、動画の読み込みが遅くなったり、再生が途中で止まったりする問題が発生します。特にモバイル回線を使用している視聴者では、データ通信量の制限により画質が自動的に低下することもあります。
さらに、ネットワークの混雑時間帯では、他のインターネットトラフィックの影響を受けやすく、安定した配信が困難になることがあります。
ダウンロード配信は容量確保が必要
ダウンロード配信では、視聴者側でのストレージ容量確保が大きな課題となります。高画質の動画ファイルは数GBに及ぶことも多く、スマートフォンやタブレットでは容量不足が問題になりがちです。特に長時間のセミナーや研修動画では、ファイルサイズが非常に大きくなり、ダウンロードに時間がかかることもあります。ダウンロード完了まで視聴を開始できないため、即座に内容を確認したい視聴者にとってはストレスとなるでしょう。
インタラクティブ配信は運営負担が大きい
インタラクティブ配信は、リアルタイムでの視聴者とのやり取りが可能な反面、運営側の負担が大幅に増加します。チャット機能やQ&A機能を活用する場合、専任のモデレーターが必要となり、人的リソースの確保が課題となります。特に大規模なイベントでは、多数のコメントや質問に対応するため、複数のスタッフが必要です。
また、不適切なコメントや荒らし行為への対応も重要な課題の一つです。事前のガイドライン策定や、リアルタイムでの監視体制構築が必要になります。
配信目的に応じた配信形式の選び方
 動画配信を成功させるには、ただ配信するだけでなく、配信の目的に合った形式を選ぶことが非常に重要です。形式によって、視聴者との接し方や参加のしやすさ、情報の伝わり方が大きく変わるためです。
動画配信を成功させるには、ただ配信するだけでなく、配信の目的に合った形式を選ぶことが非常に重要です。形式によって、視聴者との接し方や参加のしやすさ、情報の伝わり方が大きく変わるためです。
ここでは、具体的な配信目的ごとに最適な形式を詳しくご紹介します。目的に合わせた形式選びのポイントを押さえることで、より効果的で視聴者に届く動画配信を実現できます。
教育目的ならオンデマンドが最適
教育目的の配信では、オンデマンド配信がおすすめです。学習者は自分のペースで内容を理解する必要があるため、一時停止や巻き戻し、繰り返し視聴ができるオンデマンド配信の特性は、学習効果を大幅に向上させます。実際、多くの企業研修や大学のオンライン講義でも、オンデマンド配信が採用されています。
受講者は通勤時間や昼休みなど、自分の都合に合わせて学習を進められるため、継続的な学習が促進されます。また、理解が難しい箇所も何度でも視聴できるため、個人の理解度に応じた柔軟な学習が可能です。
さらに、オンデマンド配信では事前に動画を制作できるため、内容の品質を十分に検討し、編集によってわかりやすい構成に仕上げることができます。テロップや図表の挿入、章立てなどの工夫を加えることで、学習者の理解をより深める配信が実現できるでしょう。
エンタメ系はライブ配信が効果的
エンターテインメント系のコンテンツでは、ライブ配信がおすすめです。音楽ライブ、ゲーム実況、トークショーなどでは、リアルタイムの臨場感と視聴者との双方向コミュニケーションが最大の魅力となります。ライブ配信では、視聴者がチャット機能を通じて配信者と直接やり取りできるため、従来のテレビ番組では味わえない参加感を提供できます。この双方向性により、視聴者はコンテンツの一部として参加している感覚を得られ、エンゲージメントが大幅に向上します。
さらに、ライブ配信特有の「今この瞬間しか見られない」という希少性は、視聴者の集中度を高める効果があります。予期しないハプニングや自然な反応が生まれやすく、コンテンツの魅力を一層高めてくれるでしょう。
商品紹介はインタラクティブ配信
商品紹介では、視聴者との双方向のやり取りが可能なインタラクティブ配信がおすすめです。商品の詳細な説明に加え、視聴者からの質問にリアルタイムで答えられるため、購買意欲を直接的に高めることができます。インタラクティブ配信では、商品のデモンストレーションを行いながら、視聴者が気になるポイントをその場で確認できます。たとえば、化粧品の配信では色味や質感、家電製品では操作方法や機能について、視聴者の知りたい情報を即座に提供可能です。
さらに、限定特典やタイムセールなどの要素を組み合わせることで、視聴者の購買行動を促進する効果も期待できます。
参加者数が多い場合はストリーミング
大規模な視聴者を想定した配信では、ストリーミング配信がおすすめです。数千人から数万人規模の同時視聴にも対応でき、安定した配信品質を維持できるためです。ストリーミング配信では、CDN(コンテンツデリバリーネットワーク)を活用することで、世界中の視聴者に高品質な映像を届けることが可能です。視聴者の地理的な位置に関係なく快適な視聴体験を提供できるため、グローバルなイベントや発表会に適しています。
さらに、ストリーミング配信では、視聴者のデバイスや通信環境に応じて自動的に画質を調整するアダプティブビットレート機能が利用できます。これにより、スマートフォン、PC、タブレットなど、さまざまなデバイスで安定して視聴可能です。
限定公開にはダウンロード配信
特定の対象者のみに配信したい場合や、オフライン環境での視聴を想定する場合は、ダウンロード配信がおすすめです。ダウンロード配信は、セキュリティ性が高く、視聴者の環境に左右されない安定した再生が可能です。動画ファイルを視聴者のデバイスに保存して視聴するため、インターネット接続が不安定な環境でも途切れることなく視聴できます。企業の機密情報を含む研修動画や有料コンテンツの配信において、この特性は非常に価値があります。
さらに、DRM(デジタル著作権管理)技術と組み合わせることで、不正コピーや転載を防止でき、知的財産の保護も実現可能です。
最適な配信形式についてはAirzへご相談ください
 配信形式はさまざまなスタイルがあり、目的や規模によって適している配信形式が大きく変わります。それぞれの特徴とメリット・デメリットを理解した上で、最適な配信形式を選びましょう。
配信形式はさまざまなスタイルがあり、目的や規模によって適している配信形式が大きく変わります。それぞれの特徴とメリット・デメリットを理解した上で、最適な配信形式を選びましょう。
Airzは1,000回以上の配信支援実績を持ち、セミナー・学会・株主総会・国際会議・商品発表会など多彩な案件を成功に導いてきました。ZoomやWebex、YouTube、Teamsなど全主要ツールに対応し、会場手配から機材準備、テクニカルリハーサル、当日のオペレーション、アーカイブ作成までワンストップで対応可能です。
さらに、双方向音声や高画質映像の安定出力、バーチャルスタジオによる演出など、Airzならではの技術力と演出力で、初めての配信から大規模イベントまで安心して任せられます。
目的に最適な配信形式と運営プランを提案し、主催者・参加者双方が満足できるイベントを実現します。気になる方は、ぜひAirzへご相談ください。